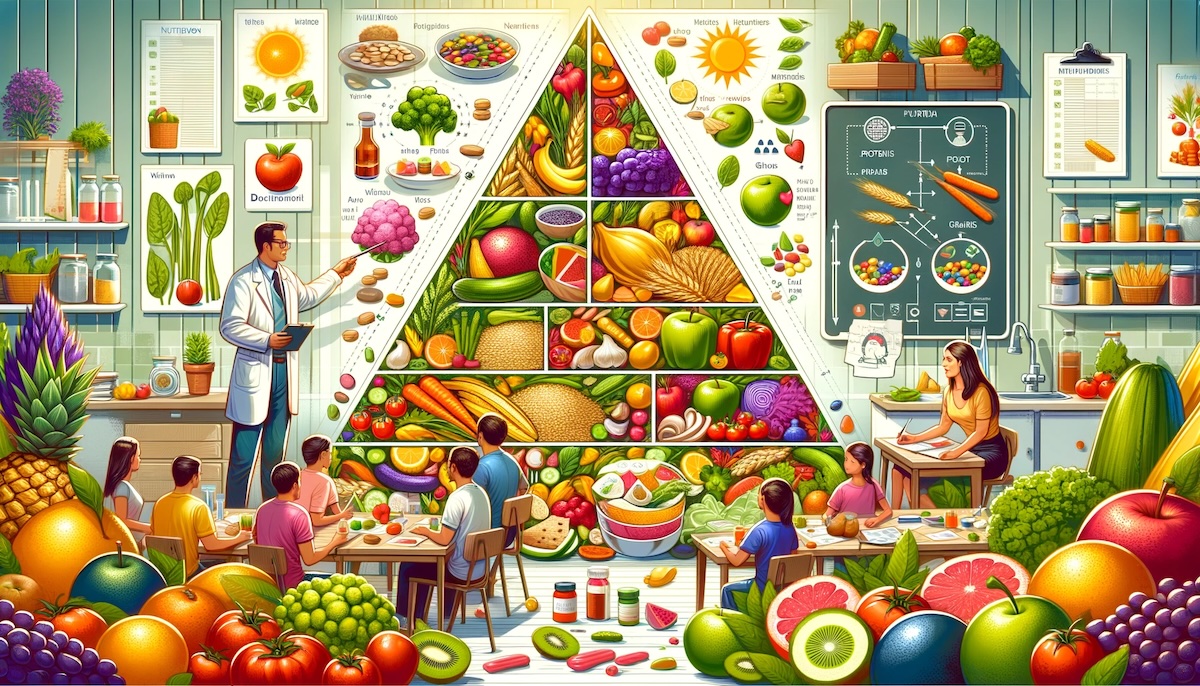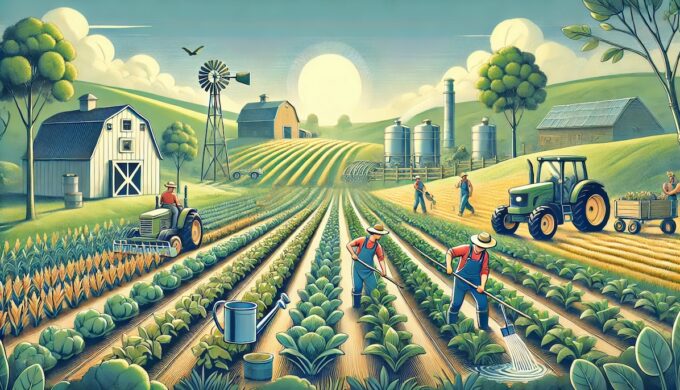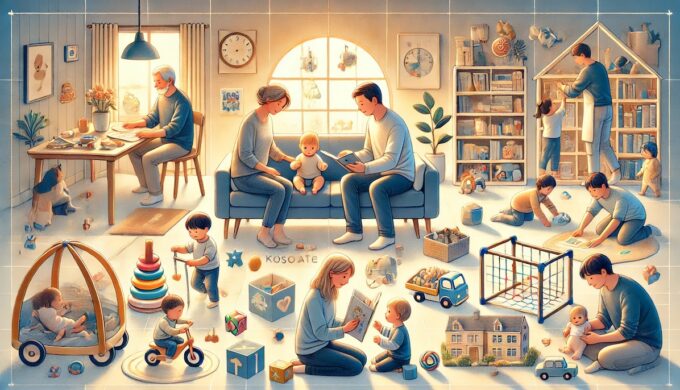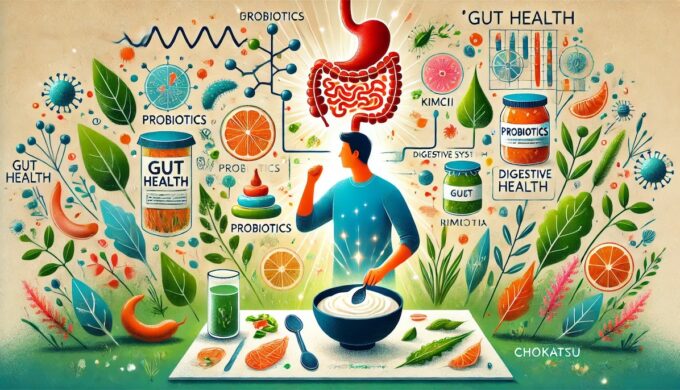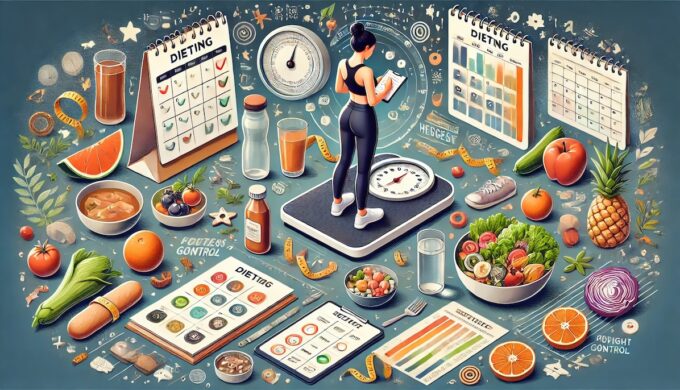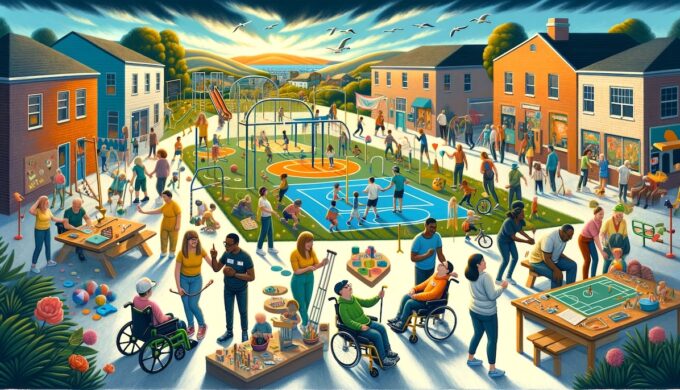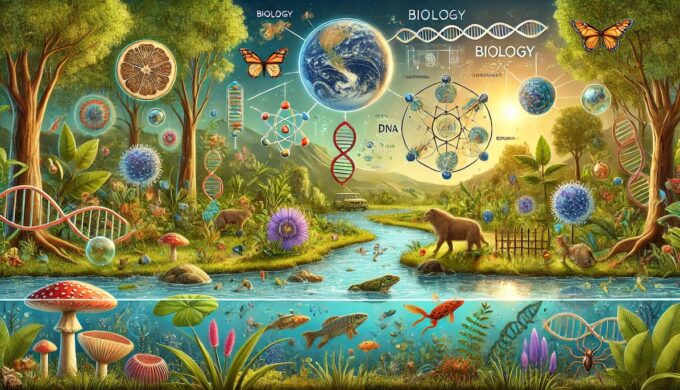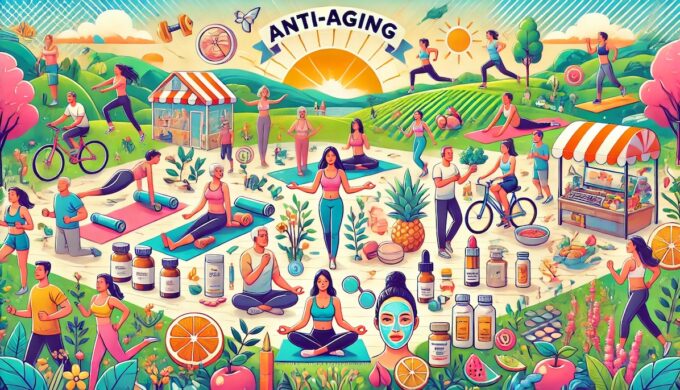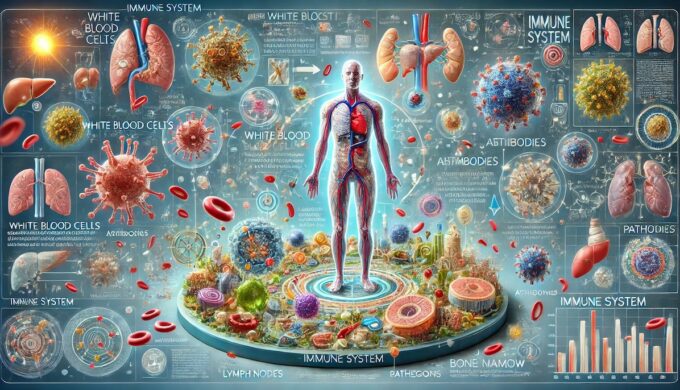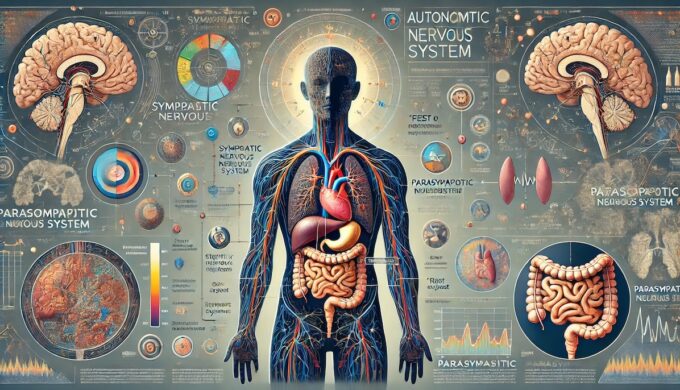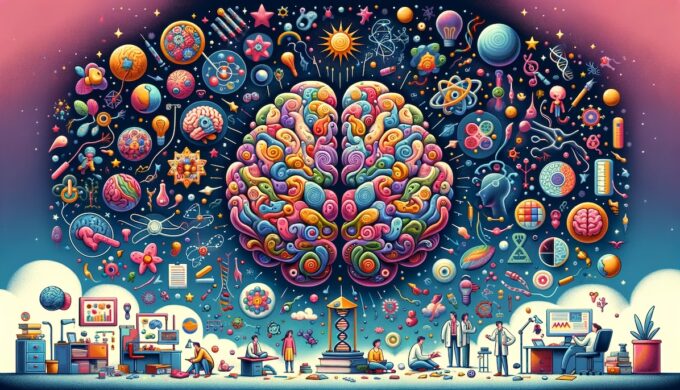栄養学(栄養科学)について知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
栄養学(Nutritional Science)とは、食物とその成分が人間の健康や成長、体の機能に与える影響を研究する学問です。これには、栄養素の吸収、代謝、役割、および病気予防や治療における栄養の重要性が含まれます。栄養学は、健康的な食生活を促進し、個々の健康を最適化するための科学的な知識を提供します。
まずはじめに、栄養学がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 栄養士・管理栄養士:最新の栄養学の知識や研究を学び、実践に役立てたい
- 医療従事者:患者の健康管理や治療において、栄養学の知識を活用したい
- 健康コーチ・フィットネストレーナー:クライアントの健康やパフォーマンス向上のために、栄養に関するアドバイスを提供したい
- 学生:栄養学を専攻しており、基礎から応用までの知識を深めたい
- 教育者:学生に栄養学を教えるための教材や教授法を探している
- 保護者:家族の食生活を改善し、健康をサポートするための知識を得たい
- 一般の健康志向の人々:自己の健康管理や食生活の改善のために、栄養学の知識を学びたい
- 料理研究家・シェフ:健康的で栄養価の高い料理を作るための知識を深めたい
- 公衆衛生専門家:地域やコミュニティの健康促進活動に栄養学の知識を役立てたい
- 研究者:栄養学の分野での最新の研究成果やトピックを理解し、自分の研究に応用したい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう!
紙書籍 まとめ買いキャンペーン
・2〜4冊…2%還元
・5〜9冊…5%還元
・10冊以上…10%還元
詳しく見る 2月12日まで
おすすめ5選)栄養学の本
栄養学がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
一生役立つ きちんとわかる 栄養学
書籍情報
「体にいい」のには理由がある!
基本のきからしっかり学べる栄養の本これから栄養と健康について学ぼうとするすべての方へ、栄養学の基礎知識から最新トピックまでを網羅し、マンガと図解を多用して解説した本です。
マンガでは2匹のネコが栄養知識を楽しく、きびしく?指導。
知っているようで意外と知らない食と栄養のあれこれがわかりやすいビジュアルによって深く知識に定着します。各栄養素の効率のよい食べ方、症状別のおすすめレシピ、食品ごとの栄養成分や栄養を逃さない調理法など、栄養知識を毎日のごはんに活かすための情報もたっぷり!
各栄養素の摂取基準や、各栄養素を多く含む食品リスト、さまざまな食品の栄養成分の含有量など役立つ最新データも満載しており、栄養事典としてもご活用いただけます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
正しい知識で健康をつくる あたらしい栄養学
書籍情報
最新食品成分表(八訂)、食事摂取基準2020年版に対応!
基本から新常識まで。一生使える知識があれば健康な身体になれる!【海藻やキノコのカロリーが増えた? 最新の栄養学トピックスをご紹介】
amazon.co.jp書籍情報より引用
5年ごとに改訂される「食品標準成分表」と「日本人の食事摂取基準」。
2020年の改訂では、エネルギー量の算出方法が変更され、海藻やキノコのエネルギー量が大幅に増加しました。
第1章「話題の栄養学」では、この解説のほか、フレイルやサルコペニア、免疫力を高める食品など、近年話題の栄養学トピックスを、イラストや写真を使ってわかりやすく紹介しています。
【読み切りスタイルで必要な情報がすぐ見つかる】
栄養について役立つ情報をテーマに分けて、1~2ページでコンパクトに紹介。
「食品」「症状」「栄養素」から必要な箇所だけ拾い読みできます。
【栄養を生かす食べ方のアイデア満載。毎日の食事に役立つ! 】
栄養成分の知識があっても、家での食事に生かすのは、案外むずかしいもの。
そこで本書では、食品ページには、「栄養を効率的にとるコツ」を症状別ページには、緩和が期待できる「食品選びのポイント」を掲載。
必要な栄養成分をむだなくおいしく摂ることにより、おうちごはんでの健康づくりをサポートします。
評判・口コミ
おいしく食べて、体ととのう まいにちの栄養学
書籍情報
何となく不調は食事で改善できる!
amazon.co.jp書籍情報より引用
YouTubeで大人気の管理栄養士が教える
あなたの心身を元気にする「日本一やさしい栄養レッスン」
なかなかとれない疲れや体のだるさ、気持ちの落ち込み、季節の体調不良など、“何となく不調”を感じていませんか。
実は、その体調不良の陰には栄養不足や栄養の偏りが隠れていることが多いのです。
大切なのは、体のしくみや栄養素のことを知って、自分に合う食事を選択できること。
それだけで、おのずと不調がやわらぎ、体がラクになっていきます。
女性のための栄養学を研究し、体調不良のお悩みを食事で改善してきた管理栄養士のあこさん(「あこの栄養学」YouTube登録者数23万人/2024年11月時点)。
毎日忙しく頑張っている人たちに伝えたい、栄養知識と食事法を凝縮したバイブルです。
気になるところから読んでいくだけで、自分の体質や体調に合った食べ物を選ぶ知識が身につきます。
「こんなことを知りたかった!」「わかりやすいから、やってみようと思える!」
そんな情報をカラービジュアルとともにたっぷり紹介しました。
忖度なしの栄養学 科学的根拠に基づいた「ボディメイク×ニュートリション」の新バイブル
書籍情報
正しい知識は選べる!
巷で認識されている、間違った知識にメスを入れるような切り口があっても面白い――。
同書はそんなコンセプトのもとでスタートしました。お決まりの方法論に忖度しない、エビデンスでひも解く、身体を変えるための科学的知識を収めた一冊です。
巻末には、逆引きの索引を設け、興味を持ったワードをすぐに検索できる仕様になっております。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典
書籍情報
筋トレ効果を最大限に高めるために、いつ、何を、どのように摂取すればよいか――
効率的な栄養摂取&食事法がわかる
■筋肥大のための食事と栄養摂取のバイブル筋肉を増やすためにはトレーニングだけではなく、同じくらい食事も重要であることが明らかとなっています。
本書では、「スポーツ科学」「栄養学」「ボディビル」の理論と研究データから導き出した、筋トレ効果を最大限に高めるための栄養摂取と食事法の最新メソッドを徹底解説。
「食事や栄養摂取で筋トレ効果を高めたい」「体脂肪を減らしたい」「筋肉をつけて健康的な体をつくりたい」など、筋肉づくりのための正しい知識と実践テクニックを網羅しました。
■トレーニー必見!筋肉のために必要な栄養素と摂取法がわかる前半では、筋肉の性質と筋肥大のしくみ、各栄養素の働きと摂取バランスなど、筋肥大をねらうために知っておきたい栄養学の情報を丁寧に解説しました。
・筋トレの前後、1日の生活サイクルにおけるタンパク質の効果的な摂取タイミング
・タンパク質だけではない、筋肥大効果を高める糖質、脂質の摂取バランス
・筋肉の成長に貢献してくれる有効な栄養素と食品
など、タンパク質の摂り方の重要性とともに、筋肉をつくるためには何を、どのくらい、どのように摂取すればよいかという効果的な栄養バランスがわかります。
■毎日の生活に取り入れたい、筋トレと食事の実践テクニックがわかる後半では、トレーニングと食事、栄養摂取を日常生活に効果的に組み込むための実践テクニックを徹底紹介。
amazon.co.jp書籍情報より引用
・プロテインとサプリメントの選び方と活用法
・筋トレ中、筋トレ前後の食事術やアルコールとのつき合い方
・トレーニングの組み立て方、コンディショニング、休養のとり方
・手軽に作れる高タンパクレシピ、活用したいコンビニ商品
など、無理なく続けられる工夫を提案しています。
巻末には、主な高タンパク食品の栄養成分表を掲載。
栄養バランスの管理や毎日の食事選びに役立ちます。
注目の新刊)栄養学の本
栄養学がわかる本の注目の新刊を、1冊、紹介します。
ひとり暮らしの栄養手帖 自分の体と心を守るための栄養学
書籍情報
毎日忙しく働くあなたに、“ひとり暮らしのベストな栄養の摂り方“を提案!
「仕事で疲れきって自炊する気がしない」
「落ち込んだときほど、気力がなくて適当な食事になる」
「筋トレしていても、偏った食事で非効率かも」
自分の食事と栄養の状態が心配になったときに役立つ、ひとり暮らしなら持っておきたい1冊です。・現代人に足りない栄養素って?
・女性と男性の栄養の摂り方は筋肉量がカギ?
・ダイエットするなら、むしろ食べなさい?!
・朝ごはんは体と心のやる気スイッチ?
・自分メンテは25歳からスタートさせるべき?そんな、気になる体の仕組みや栄養の働きの基本から、朝、昼、晩、3食の献立例、外食のポイントや冷凍食品の賢い活用法、心身の不調に効果的な食べ物など、具体的な知識をコミックとイラストを交えてわかりやすく紹介。
何を食べるかで未来の自分がつくられるなら…、今これだけは知っておきたい「自分の体と心を守るための栄養学」が、もっとラクに、心地よく過ごすために役立つはずです。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ロングセラー)栄養学の本
栄養学がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
いちばんわかりやすい栄養学の基本講座
書籍情報
食べ物や食事の選択肢が増えるなか、個人の「食」に対する価値観も多様化しています。個人の価値観に見合った、健康によい食事を摂るためには「食」に対する適切な知識を持たなければなりません。
この本では、前半で栄養学の基本と各栄養素の働きをイラスト入りでやさしく解説。後半では、食品の栄養分と体に効く摂り方を詳しく紹介しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
日本食品標準成分表、日本人の食事摂取基準に対応。
小説みたいに楽しく読める栄養学講義
書籍情報
何をどのくらい食べればいいの?
栄養価の高い食物ってなに?
栄養素を摂り過ぎたり,足りないと体はどうなる?毎日の食にかかわる知識を基礎からわかりやすく解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
人の健康を支える栄養学の世界へようこそ
かしこく摂って健康になる くらしに役立つ栄養学【第2版】
書籍情報
『日本人の食事摂取基準(2020年版)』など、最新データに対応!
楽しく読めて役に立つ栄養学のテキスト!■正しい知識と毎日の食事で、家族の健康を守る
amazon.co.jp書籍情報より引用
食事から摂取する栄養は、私たちの体をつくります。本書では、正しい栄養学の知識を、写真やイラストを多用してわかりやすく解説しました。
バランスのとれた食事をとるコツ、ライフステージにあった栄養のとり方など、家庭で役立つ情報が満載です。
■知っておきたい栄養成分をキャラクターで紹介!
炭水化物・たんぱく質・脂質の三大栄養素をはじめ、ビタミン・ミネラルなど、知っておきたい栄養成分の基礎知識や働きについて、その特徴をキャラクターとともに紹介しています。
■最新データに対応!
本書は『日本人の食事摂取基準(2020年版)』をはじめ、最新データに対応した改訂版です。
食生活とSDGsの関わり、フード・マイレージ、食品ロスなど、話題のトピックについても解説しています。
よくわかる栄養学 マンガと図解で身につく
書籍情報
今のあなたにぴったりの栄養の知識、食べ方のコツが満載!
なぜバランスのとれた食事が大切なのか、そもそもバランスの良い食生活とは?
栄養の基本からコツ、不調時の対策まで、マンガと図解で楽しくやさしく学べる1冊。
「これを食べると健康になる」といった巷に溢れる情報を、正しく読み解ける知識が身につきます。
■不足すると?とりすぎると?
5大栄養素の働きととり方を詳しく解説■ずっと今の食生活を続けていい?
ライフステージにあった食事を解説■この不調は栄養で改善できる?
25の不調・病気の栄養対策を解説■この食品にはどんな栄養素が?
amazon.co.jp書籍情報より引用
160食品の成分や食べ方のコツを解説
基礎・栄養素・栄養医療の実践からなる カラーアトラス栄養学 [第8版] オールカラービジュアル栄養図解
書籍情報
これほどの栄養学の知識が一冊で学べる書籍は類がないといえる納得のいく情報量に加え、各自の必要なレベルに応じた膨大な数の図版もオールカラーで掲載。
正しい知識を基に情報を選択しなければならない栄養士や管理栄養士、また食事療法やサプリメント開発者にも大いに役立つ最高傑作の栄養学の教科書!現在の医療や療法の現場において栄養学は欠かすことのできない必須の知識となっていることは明らかであり、予防医学としての位置づけも確立されてきている。
本書は、栄養学を学ぶ学生、栄養士、食事療法士、薬剤師、医師、看護師、栄養系の資格を目指す方、栄養に興味のある一般の方など、あらゆる人々に対応した構成となっており、栄養学の最新基礎知識および栄養素、栄養医療の実践を完全に網羅している。また、健康と栄養の関係はたいへん複雑であり、栄養に関する誤りや非伝染性疾患に対処するために正しい選択をしなくてはならない場面において、栄養学の基礎知識は不可欠である。
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書は栄養素とその作用を個別に観察するだけでなく、実際の食事という観点からも栄養や食品を論じている。
評判・口コミ、出版社ポスト
行動栄養学とはなにか?
書籍情報
健康の鍵は、「食べ物」よりもその「食べ方」にあった!
食事はつねに、どれを食べ、どれを食べないかの選択です。
そして、「いつ」「どこで」「誰と」「どのように」食べるかーーその組み合わせは無限大です。そんな日々の営みである食と、その積み重ねの結果である健康との関連を栄養データから読みとき、栄養の本質を探りました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
日本の栄養学の権威である著者40年の集大成です。
健やかに食べたいすべての人に!
本当に役立つ栄養学 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学
書籍情報
「食物繊維は体にいいから消化もいい」と語っている学生に、そもそも消化ができないものを食物繊維ということを説明すると、では「消化できないものが体に必要なのか」ときかれて、これは正しい食の知識が必要だと感じた著者。
amazon.co.jp書籍情報より引用
体にいい、悪いで語られがちな食べものについて、多くの人がわかっているようでわかっていないという実態を感じて、現在わかっている食の科学を理解し、正しい情報の受け取り方ができるようにという思いで執筆した1冊。栄養学的な面と、複雑な体の代謝のしくみをなるべくやさしい言葉で解説します。
食品によっては、時代的背景も関係していたり、健康ブームの空気にのって「良い食べもの」になっているものも。食と代謝はまだまだ解明されていないことも多いのですが、わかっていることをクリアにしながら、誤った認識に陥らない方向を示します。
サクッとわかる ビジネス教養 栄養学
書籍情報
「栄養」と言われても、あまりにも身近すぎて空気のような存在に思えるかもしれません。
しかし、わたしたちが毎日食べている食事、その一つ一つの食材についての栄養素が気になったり、ジムで筋トレをしているとき、プロテインの効果的な摂り方を知りたくなったりと、「栄養」について、ふと関心を持つきっかけは、誰にでもあるのではないでしょうか。
本書では、栄養学の基礎知識から、「糖質」「筋肉」「肥満」など気になるテーマの解説、最新の栄養トピックまで、〝食べる”最新常識を、イラスト図解でサクッとまとめました。
栄養学の基本をさらっと知りたい方にも、仕事や食生活に活かしたい方にも。
amazon.co.jp書籍情報より引用
見るだけでも様々なパフォーマンスが向上する、最初に手に取りたい1冊です。
スポーツ栄養学 第2版 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる
書籍情報
スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは?
運動と食事をどのように組み合わせれば、健康の維持増進につながるのか?好評を博した『スポーツ栄養学』を、最新の知見を盛り込み、大幅改訂。
amazon.co.jp書籍情報より引用
減量やダイエット、腸内細菌と運動との関係、ビタミン・ミネラルの内容などを新たに追加し、より充実した内容とする。
栄養学によくある質問と回答
栄養学について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
栄養学とは何ですか?
回答: 栄養学は、食品と栄養素が人間の健康にどのように影響するかを科学的に研究する学問です。
栄養素の摂取、消化、吸収、代謝、排出の過程を理解し、健康な食生活の指針を提供します。
栄養学で研究される主な栄養素にはどのようなものがありますか?
回答: 栄養学では、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が研究されます。
これらは体のエネルギー供給、成長、体の修復、生理機能の維持などに必要です。
栄養バランスとは何ですか?
回答: 栄養バランスとは、健康を維持するために必要な各種栄養素を適切な比率で摂取することです。
バランスの取れた食事は、エネルギーや必須栄養素を効率的に体に供給し、病気のリスクを減少させる効果があります。
過剰な栄養摂取が体に及ぼす影響は何ですか?
回答: 過剰な栄養摂取は肥満や様々な慢性疾患のリスクを高めることが知られています。
例えば、過剰な糖質や脂質の摂取は心血管疾患や2型糖尿病のリスクを増加させ、過剰な塩分摂取は高血圧につながることがあります。
栄養不足が引き起こす一般的な問題は何ですか?
回答: 栄養不足は、免疫力の低下、成長障害、筋肉の減少、疲労感、集中力の低下など、体のさまざまな機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
特に、ビタミンやミネラルの不足は貧血や骨粗しょう症などの病気を引き起こすことがあります。
栄養学のスキルが活かせる職種とは?
栄養学に関する知識や経験を習得することによって、さまざまな職業で活躍することができます。
栄養学は、人々の健康と福祉に直接関わる重要な分野であり、予防医療や健康増進、病気の管理など多岐にわたる役割を担います。
以下は、栄養学の専門知識を活かして担当できる仕事の例です:
- 栄養士/管理栄養士:
- 病院、学校、福祉施設、スポーツチームなどで働き、個々の栄養ニーズに合わせた食事計画を作成し、栄養指導を行います。病気の予防や治療、健康維持のための栄養管理を担当します。
- 公衆衛生栄養士:
- 地域社会の健康増進を目指し、公衆衛生プログラムの設計・実施を行います。健康教育や栄養に関する啓発活動を通じて、地域住民の健康状態を改善します。
- スポーツ栄養士:
- アスリートやスポーツチームに対して、パフォーマンス向上と回復を目的とした栄養指導を行います。トレーニングや競技に最適な食事計画を提供します。
- 食品開発者/食品科学者:
- 食品メーカーで働き、健康的で栄養価の高い新製品の開発を行います。食品の品質管理、栄養価の分析、食品安全の確保にも関与します。
- 研究者:
- 大学や研究機関で、栄養に関する基礎研究や応用研究を行います。新しい栄養成分の発見や、食事と健康の関係についての研究を通じて、科学的知識を拡充します。
- 栄養コンサルタント:
- 個人や企業に対して、栄養に関する専門的なアドバイスを提供します。健康増進プログラムの設計や、企業の福利厚生プログラムの一環として栄養指導を行います。
- 教育者:
- 大学や専門学校で栄養学を教える。栄養士や管理栄養士を目指す学生に対して、栄養学の基礎から応用までを指導します。
- ヘルスカウンセラー/ウェルネスコーチ:
- クライアントに対して、健康的なライフスタイルの実践を支援します。栄養バランスの取れた食事、運動、ストレス管理など総合的な健康管理の指導を行います。
- ライター/ジャーナリスト:
- 栄養に関する記事や書籍を執筆し、一般の人々に健康情報を提供します。雑誌、新聞、ウェブサイトなどで栄養に関するトピックを取り上げます。
- 政府機関職員:
- 健康政策の立案や実施に関わり、国民の健康増進を目的としたプログラムの策定に寄与します。食品規制や栄養政策の管理にも関わります。
栄養学の専門知識は、人々の健康をサポートするために不可欠であり、教育、研究、臨床、ビジネスなど多岐にわたる分野で応用されます。
栄養学の知識を活かして、健康的な食生活を推進し、病気の予防や治療に貢献することができます。
まとめ
栄養学について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、栄養学がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。