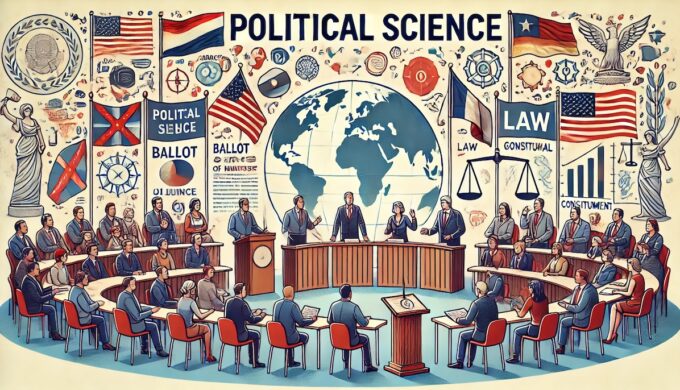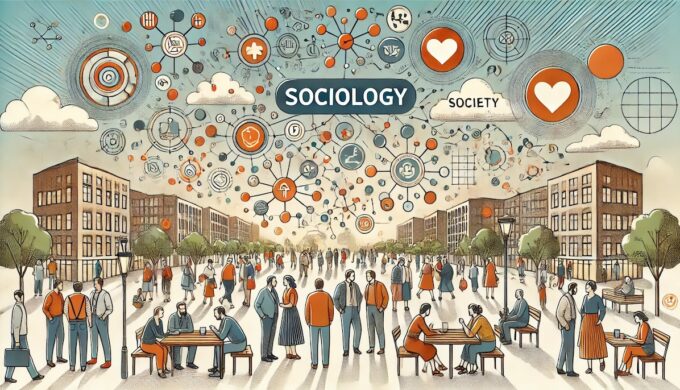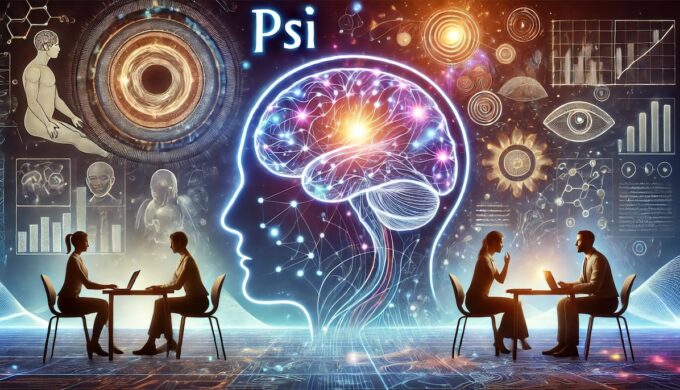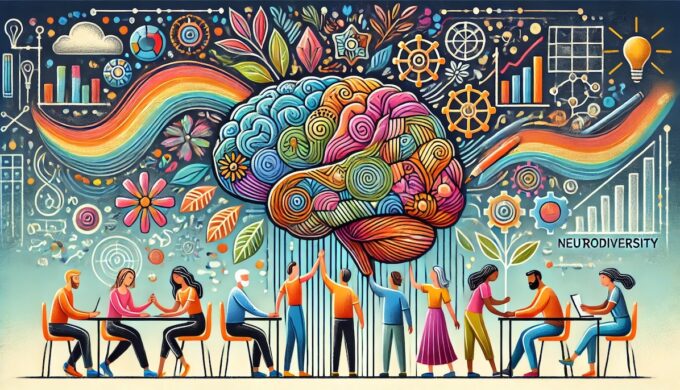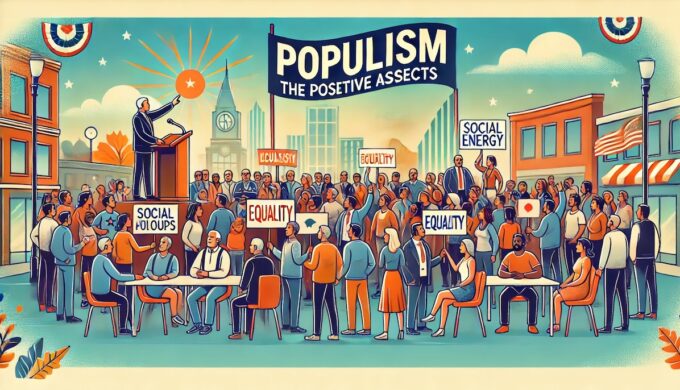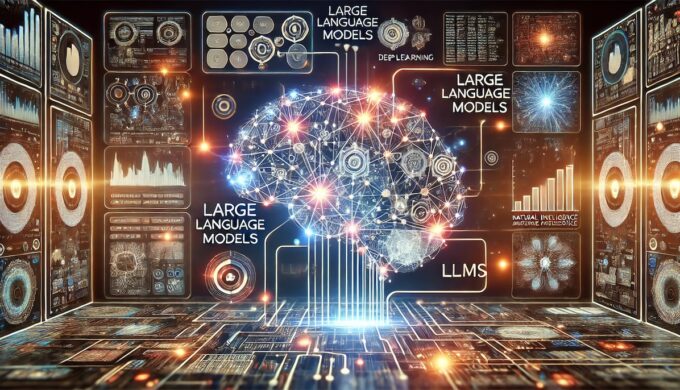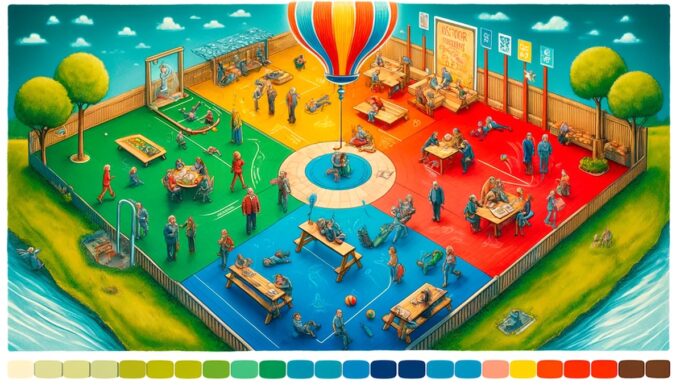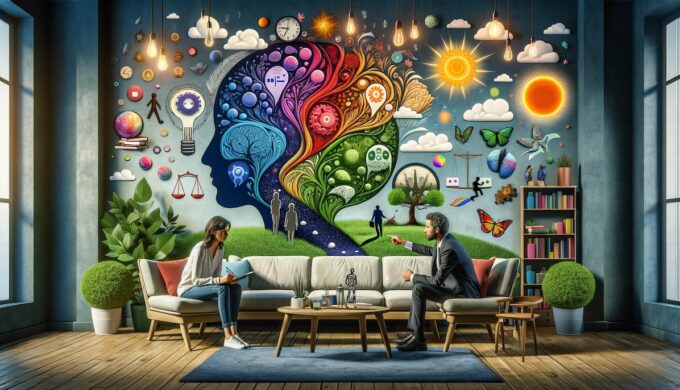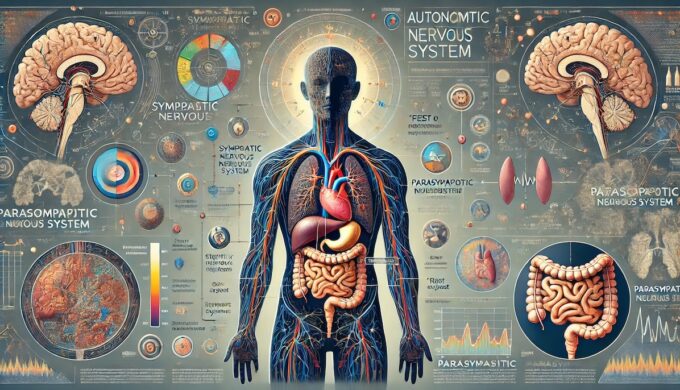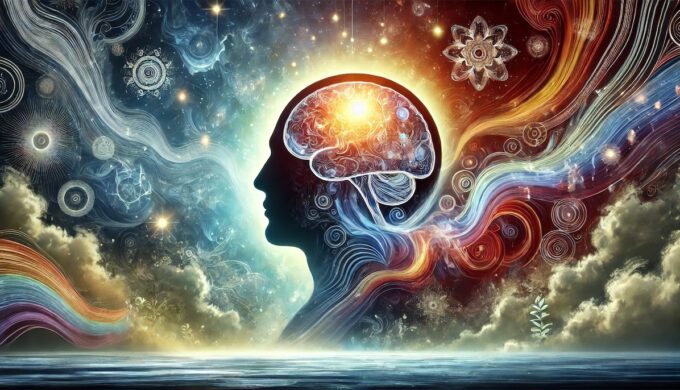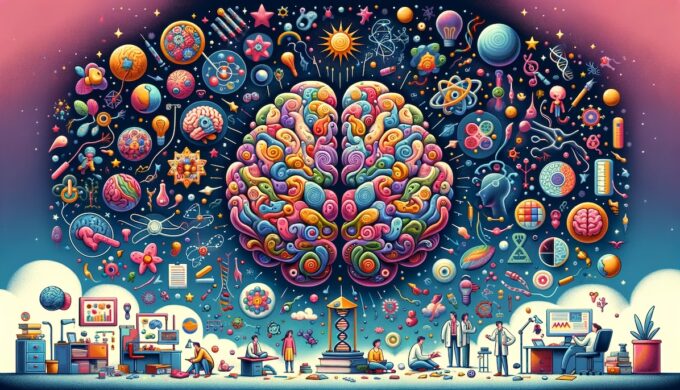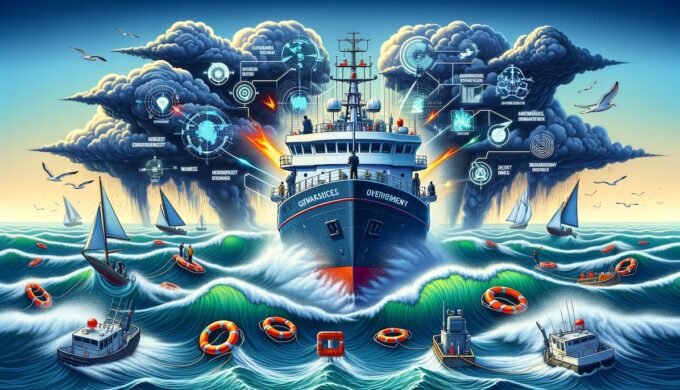無意識バイアス(無意識の偏見、アンコンシャス・バイアス)について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
無意識バイアスとは、私たちが気づかないうちに持っている先入観や偏見のこと。これは、経験や社会的な影響に基づく思考のショートカットであり、人々や状況を判断する際に自動的に影響を及ぼします。多様性と公平性を促進するためには、これらのバイアスに気づき、対処することが重要です。
まずはじめに、無意識バイアスがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- ビジネスリーダーやマネージャー:多様性と包括性を職場で推進し、偏見を減らしたい
- HRプロフェッショナル:採用、評価、昇進のプロセスでの無意識の偏見に対処したい
- ダイバーシティ&インクルージョン担当者:組織内での意識改革と教育プログラムを開発したい
- 教育者:生徒や学生に対して無意識の偏見の影響について教えたい
- 研究者:社会心理学や行動経済学の観点からアンコンシャスバイアスを研究している
- 社会活動家やNGO関係者:公平性と社会正義の推進に関心がある
- パーソナルデベロップメントに興味のある人:自己認識を深め、偏見を意識し克服したい
- コンサルタント:クライアントに多様性と包括性に関するアドバイスを提供したい
- ソーシャルサービスの専門家:多文化間のコミュニケーションやサービス提供での偏見を理解したい
- 政策立案者:公共政策やプログラムにおけるアンコンシャスバイアスの影響を評価したい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!
紙書籍 まとめ買いキャンペーン
・5〜9冊…最大5%ポイント還元
・10〜11冊…最大10%ポイント還元
・12冊以上…最大15%ポイント還元
詳しく見る 7月14日(月)まで
おすすめ5選)無意識バイアスの本
無意識バイアスがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
無意識のバイアス 人はなぜ人種差別をするのか
書籍情報
私たちは見て判断するのではない。
判断して見ているのだ。
悪意の有無に関係なく存在する偏見、バイアス。それがいかにして脳に刻まれ、他者に伝染し、ステレオタイプを形作っているかを知ることなしに人種差別を乗り越えることなどできない。
米国の学校・企業・警察署の改革に努める心理学者が解く無意識の現実とは。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
無意識のバイアスを克服する 個人・組織・社会を変えるアプローチ
書籍情報
私たちが意識的に持つ信念と衝突する、意図的でない偏見に満ちた行動。
職場や医療現場、教育の場、警察など、私たちは、それが存在し、その場を腐敗させ、時には致命的な影響さえ与えることを知っている。
しかし、そうした偏見を払拭するには、多大な努力が必要だ。10年にわたってこの問題に取り組んできた著者は、科学的研究と多くのインタビューとを織り交ぜながら、我々の心と行動がどのように変化していくのかを明らかにする。
ジョンズ・ホプキンス病院の医師が使用した診断チェックリストが医療における男女の差別的扱いをなくしたこと、スウェーデンの幼稚園で教師がジェンダー・ステレオタイプを根絶するためにした工夫、オレゴン州の警察でマインドフルネスの実践と専門トレーニングにより武力行使が驚くほど減少したこと—
著者は何が有効で、それはなぜなのかを探っていく。偏見に満ちた行動は変えられる。
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書に概説されているアプローチは、私たち自身と、私たちの世界を作り直す方法を示している。
評判・口コミ
アンコンシャス・バイアス―無意識の偏見― とは何か
書籍情報
「オーケストラには男性演奏者が多い」「女性管理職が増えていかない」——これにはアンコンシャス・バイアスが影響していた!
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)とは、自分自身が気づかずにもつ偏った見方や考え方のこと。
グーグルが社員教育に導入したことから広く知られるようになったが、この影響は組織に限ったことではない。
個人の「キャリア」「収入」「成果」「人間関係」にまで影響してしまうのだ。本書では、数々の事例と調査結果とともに、バイアス(偏見)の真実、生じる理由、その影響と対策までを徹底解説する。
個人が「本来もっている能力」を発揮したい/させたい人、必読。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
あなたにもある無意識の偏見 アンコンシャスバイアス
書籍情報
人間関係に悪影響を与える「無意識の偏見」。
失言や好まれざる態度を抑え、致命的な失敗をしないための知恵を教える!
政治家の失言、テレビCM炎上の正体!
単身赴任中と聞くと、父親だと思う…
amazon.co.jp書籍情報より引用
シニアはパソコン、スマホが苦手…
定時退社の社員は、頑張っていない…
評判・口コミ
「男女格差後進国」の衝撃 無意識のジェンダー・バイアスを克服する
書籍情報
今の日本であなたの娘は輝けますか?
2019年12月、世界のリーダーに影響力を持つ「世界経済フォーラム」が発表した「ジェンダー・ギャップ指数」で、日本は前年度より順位を落とし153か国中121位だった。
政府が女性活躍政策を推進しても、諸外国の改善と比較する相対評価では、まったく追いついていけない。長年ジェンダー問題について取材・執筆・実践に取り組んできた著者は「多くの人が、『日本は男女格差が大きい』と実感せずに暮らしていることが、日本が変わっていかない一番大きな原因」と指摘する。
本書では、2015年から2017年までの3年間で、女性活躍を最優先課題として本気で取り組んだ各国の女性リーダーの割合の変化を紹介、例えばカナダの閣僚の女性割合は30%から50%に、インドネシアの最高経営責任者は5%から30%に拡大している。
政府や経済界が本気で取り組めば、わずか3年間で女性リーダーをここまで増やすことが可能なのだ。本書では、諸外国の取り組みを紹介しつつ「日本で男女格差が縮まらない理由」を考察、国内の成功例を挙げながら、次世代のためにできることを提案する。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
注目の新刊)無意識バイアスの本
無意識バイアスがわかる本の注目の新刊を、紹介します。
今月は該当する新刊が見つかりませんでした。
ロングセラー)無意識バイアスの本
無意識バイアスがわかる本のロングセラーを、8冊、紹介します。
なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか 逃れられないバイアスとの「共存」のために
書籍情報
あなたの思う「正しい! 」は危険信号?
amazon.co.jp書籍情報より引用
「自分は偏っていないと思えば思うほど、自分の偏向が見えなくなり、自覚がなくなる」
「高い自尊心を持つ理性的な人ほど、自身のバイアスによる盲点ができてしまう」
「自分の見解を論理的に考えれば考えるほど、それが真実だと思い込む」
誰もが持つ「防御反応」であるバイアス。
さまざまな偏見や思い込みからフラットになるために、興味深い実例とデータをあげて、わかりやすく案内する。
評判・口コミ
あなたのチームがうまくいかないのは「無意識」の思いこみのせいです
書籍情報
これからのリーダーに知っておいてほしい「たった1つ」のこと
amazon.co.jp書籍情報より引用
=アンコンシャス・バイアス(無意識の思いこみ)を知ること
近年、GoogleやJohnson&Johnsonが社内教育で取りいれはじめ、話題の「アンコンシャス・バイアス」
「アンコンシャス・バイアス」に気づくと、メンバーと良好な関係を築くことができ、成果の上がる最高のチームになる!
こんなことありませんか?
■定時に帰ろうとするメンバーにイラッ!
■お茶出しをする男性に違和感…
■あの人は理系だから…と決めつける
■今どきの若者の考えていることはわからない
■会議中に良いアイデアがうかんでも発言しない
これ全部、アンコンシャス・バイアスです。
2万人以上のリーダーを育成してきた著者による、リーダーが陥る「無意識の思いこみ」に対処するトレーニングを紹介!
ほんの少し意識の置きどころを変えるだけで、仕事の成果が劇的に変わる!
「アンコンシャス・バイアス」マネジメント 最高のリーダーは自分を信じない
書籍情報
アンコンシャス・バイアス =「無意識の偏見」「無意識の思い込み」「無意識の偏ったものの見方」
日本では2013年ごろから、ビジネス雑誌や新聞・テレビでも取り上げられるようになってきた。
グーグルが、「アンコンシャス・バイアス」と名づけた社員教育活動を始めたことで一躍、有名になった言葉でもある。なぜ、今、注目されているのか?
最大の理由は、組織の発展において、多様性が重要になってきているからだ。たとえば、リーダーがメンバーに対して、
「彼女は2歳の子どもがいるから」→泊まりがけの出張は無理だな。
「彼は売れていないから」→何をやらせても、ダメに決まっている。
「プライベートを優先するタイプだから」→昇格が数年遅れても、問題ないだろう。
といったことを、勝手に決めつけている。
日常、職場でよく見聞きする光景ではないだろうか。本書は、リーダーが身につけておきたい“必須知識"となった「アンコンシャス・バイアス」について、まずはどういうものかを知る、そして自分自身のバイアスに気づく方法、さらにはどのように対処していくか、メンバーみんなでバイアスに振り回されないチームになる方法を、事例をふんだんに交えながら解説する。
ダイバーシティ&インクルージョンの時代、まずは経営者や管理職をはじめとするリーダーから、自分自身の無意識の思い込みや、無意識の偏ったものの見方に気づき、意識して対処する--たったそれだけで、組織の未来は劇的に変わるのだ。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
バイアス習慣を断つためのワークショップ――ジェンダー公正を進める職場づくり
書籍情報
ウィスコンシン大学マディソン校の科学・工学分野女性リーダーシップ研究所(WISELI)が、ジェンダーに関する偏見を中心とした「無意識のバイアス」を克服するべく、スタッフ採用ワークショップのため開発したテキストの翻訳書。
amazon.co.jp書籍情報より引用
職場で使えるジェンダー・ハラスメント対策ブック: アンコンシャス・バイアスに斬り込む戦略的研修プログラム
書籍情報
ジェンダー・ハラスメントも少しずつ認知されてきてはいるが、具体的な定義はあまり理解されていない。
ジェンダー・ハラスメントは多くの職場で発生しているものの、加害者/被害者ともにハラスメントであることを気づかないケースも多い。本書ではハラスメントの具体例や、研修後のアンケート、落語研修の台本など、研修の意図と内容を丁寧に紹介しているので、読みながら自身の偏見に気づき、対策を講じていけるはずである。
著者は特に「自分には偏見があることに気づいていない」状態のアンコンシャス・バイアス(潜在的ステレオタイプ)に着目して研修プログラムを作成している。
その研修プログラムはジェンダー・ハラスメントだけでなくあらゆる差別解消にも効果が期待できるため、今後ぜひとも広がっていってほしい。内閣府男女共同参画局や連合が近年アンコンシャス・バイアスを紹介するようになったが、「自分の考えが偏見にあたることに気づいていない」といった誤った意味で使用しており、著者はその問題を指摘している。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ、出版社ポスト
思い込みにとらわれない生き方
書籍情報
「思い込みがない」こそ、一番の思い込み!
家庭や職場、近所であなたを縛っている「アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)」から自由になり人間関係をすっきりさせる一冊。「なぜか、人間関係がうまくいかない」
「相手に良かれと思って言ったことが相手を怒らせてしまった」
という誰にでも起こりうるトラブル。その原因の多くが、「無意識の思い込みによる認知の歪みや偏り(アンコンシャス・バイアス)」によるものというのが、本書の主眼。
著者が学長をつとめる昭和女子大学でも盛んに啓蒙活動を行っています。この「思い込みがある」ことを認識したうえで、正しく相手を理解することが、これからの多様性社会において求められています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
「アンコンシャス・バイアス」を正しく理解し、生きやすくなるヒントを伝える一冊。
働く女性の教科書 アンコンシャスバイアスを外したら仕事も生き方ももっと充実する
書籍情報
女性の皆さん、「女性だから○○すべき」と自分のやりたいことにブレーキをかけてませんか?
サポート役でいいと自分に言い聞かせてませんか?
しかたがないと夢をあきらめてませんか?ブレーキをかけてしまうのは、アンコンシャスバイアスという無意識の思い込みのせいです。
けれど、無意識なので94%は潜っていて気づけません。これまで結婚や出産、育児、介護などを理由に多くの優秀な女性たちが辞めていくのを見てきました。
私自身も男性社会の中で社会的偏見を感じて、押しつぶされそうになりながらも働き続けて、管理職そして幹部になりました。
その過程の中で試行錯誤しながらアンコンシャスバイアスを外すテクニックを体得していき、仕事をおもしろくするためには「コツ」があることもわかりました。
現在では、そのコツを、延べ2万7千人以上の多くの女性たちにお伝えしています。本書は、当時の私と同様に職場や人間関係に悩み苦しんでいる女性の皆さんに伝えておきたいことをめいっぱい書いています。
40年以上の勤務経験から、実際に試してみて効果的だった、アンコンシャスバイアスを外すテクニックを紹介しながら、仕事をおもしろくするためのポイントや女性の強みを活かす方法、リーダーとして必要なスキルを伝えています。
最後に私から、もっと女性として輝きたいと思っているあなたの背中を押すエールを送ります。「こうあるべき」の生き方から自分を解放して、仕事も生き方ももっと充実させていきましょうね。
amazon.co.jp書籍情報より引用
あなたの生きづらさ「昭和な呪い」のせいでした 古い価値観から心を解放するマインドエクササイズ
書籍情報
昭和な呪いを解き自分らしさを取り戻す方法
「昭和な呪い」と聞いて、何を思い浮かべますか?
本書では、私たちが知らず知らずのうちに抱える“昭和な”古い価値観や無意識の偏見に縛られた固定観念に注目。
現在、婚活コンサルタントとして活躍している著者は、現代の婚活において、異性との駆け引きのテクニックよりも、こうした“昭和的な呪い”から心を解放することの方が重要であると気づきました。幼少期、児童養護施設という特別な環境で育ち、そこから独自の視点と強さを培う自己啓蒙法を編みだし、CA、タレントなど数々の夢に挑戦し、自己実現してきた著者。
現在、その経験を活かし、心理学とコーチングを基に、心から望むライフデザインを自己決定できるための婚活支援コンサルタント事業に取り組んでいます。この本は、著者の婚活コンサル受講生たちが効果を実感し高評価を得た選りすぐりのワークを掲載。
典型的な「昭和な呪い」のフレーズも紹介しつつ、私たちの中に根付く古い価値観を見つめ直し、それを解くための具体的なステップを提供するガイドブックとして、あなたを「自分らしい生き方」へと導きます。時代に合った自分らしさを取り戻すための第一歩を本書を参考にしながら踏み出してみませんか?
amazon.co.jp書籍情報より引用
無意識バイアスによくある質問と回答
無意識バイアスについて、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
無意識バイアスとは何ですか?
回答: 無意識バイアスとは、個人が自覚せずに持つ先入観や偏見のことです。
これらは、社会的なステレオタイプや過去の経験に基づいて無意識のうちに形成され、人々が他者を評価したり、意思決定を行ったりする際に影響を及ぼすことがあります。
無意識バイアスは、人種、性別、年齢、外見、文化背景などに関連する先入観によってもたらされることが多いです。
無意識バイアスはどのようにして形成されますか?
回答: 無意識バイアスは、個人の育った環境、文化、社会的なステレオタイプ、過去の経験や教育などによって形成されます。
人間の脳は情報を迅速に処理するため、しばしば簡略化や一般化に頼りますが、これが偏見や先入観を生む原因となることがあります。
無意識バイアスが職場でどのような影響を与える可能性がありますか?
回答: 無意識バイアスは職場で多くの問題を引き起こす可能性があります。
採用、昇進、仕事の割り当て、業績評価などの決定に無意識の先入観が影響を及ぼし、多様性や公平性の欠如をもたらすことがあります。
これは特定のグループに対する不公平な扱いを引き起こし、職場の士気や生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。
無意識バイアスを認識し克服するための方法はありますか?
回答: 無意識バイアスを克服するためには、まず自己認識を高めることが重要です。
自分自身の思考や決定がバイアスに影響されている可能性を認め、反省することから始めます。
多様な視点や文化を学ぶ、異なるバックグラウンドを持つ人々との対話を求める、研修やワークショップに参加するなど、意識的に先入観を見直す機会を持つことも効果的です。
無意識バイアスはダイバーシティとインクルージョンにどのように関係していますか?
回答: 無意識バイアスは、ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)の取り組みにおいて大きな障害となり得ます。
無意識の先入観は、特定のグループを排除したり、不公平な扱いをしたりすることで、職場や社会全体の多様性を損なう可能性があります。
ダイバーシティとインクルージョンの目標を達成するためには、無意識バイアスに取り組み、それを減らす努力が必要です。これにより、より公平で包摂的な環境を実現することができます。
無意識バイアスのスキルが活かせる職種とは?
無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)の知識や経験を活かせる仕事を10個、紹介します:
- ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)コンサルタント
- 企業組織において多様性と包括性を推進し、無意識の偏見を軽減するための戦略立案と実行支援を専門的に行います。
- 人事・採用担当者
- 採用面接や人事評価プロセスにおいて無意識の偏見の影響を最小化し、公正で客観的な人材選考と評価制度の構築・運用を担当します。
- 企業研修講師・組織開発トレーナー
- 管理職やリーダー向けにアンコンシャスバイアスに関する意識啓発研修や、バイアス軽減のためのスキル向上プログラムを実施します。
- チームマネジメント・プロジェクトマネージャー
- チーム運営において多様なメンバーの能力を最大限に引き出し、偏見のない公正な意思決定とコミュニケーションを実現します。
- カスタマーサービス・接客業務の品質管理者
- 顧客対応において無意識の偏見が服務態度に影響しないよう、スタッフの教育訓練と品質管理体制の構築を行います。
- マーケティングリサーチャー・消費者行動分析者
- 市場調査や消費者分析において、調査者や分析者の無意識の偏見が結果に与える影響を考慮した客観的な調査設計と分析を実施します。
- 教育機関のカウンセラー・学生支援担当者
- 学校現場において生徒や学生に対する無意識の偏見を認識し、公平で包括的な教育環境づくりと学習支援を提供します。
- 医療・福祉現場の質向上担当者
- 医療従事者や介護職員が患者・利用者に対して持つ無意識の偏見を軽減し、質の高い医療・福祉サービスの提供体制を構築します。
- 法務・コンプライアンス専門家
- 職場でのハラスメントや差別問題の予防と対策において、無意識の偏見がもたらすリスクを理解した法的対応と予防策の立案を行います。
- 公共政策・社会保障制度設計者
- 行政サービスや社会制度の設計において、政策立案者や実施者の無意識の偏見が特定の集団に不利益をもたらさないよう配慮した制度設計を担当します。
これらの仕事では、無意識レベルで働く偏見や先入観を科学的に理解し、より公正で包括的な組織運営や社会システムの構築に貢献する専門性が重要な価値を提供します。
まとめ
無意識バイアス(無意識の偏見、アンコンシャス・バイアス)について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、無意識バイアスがわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。