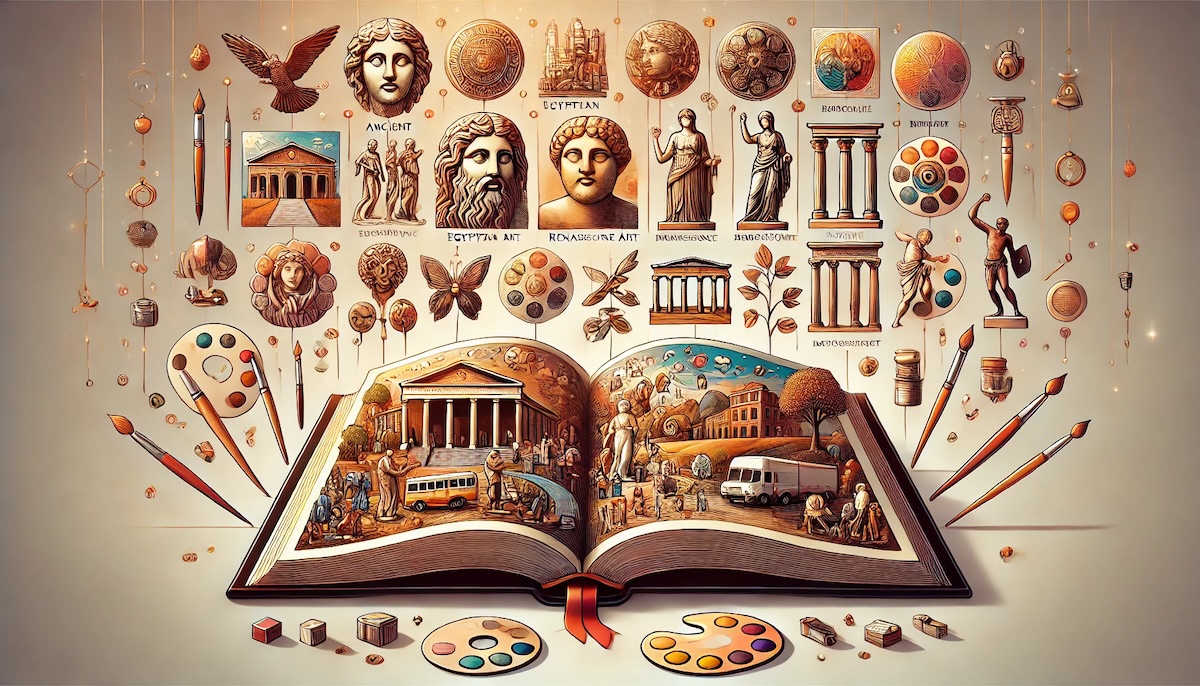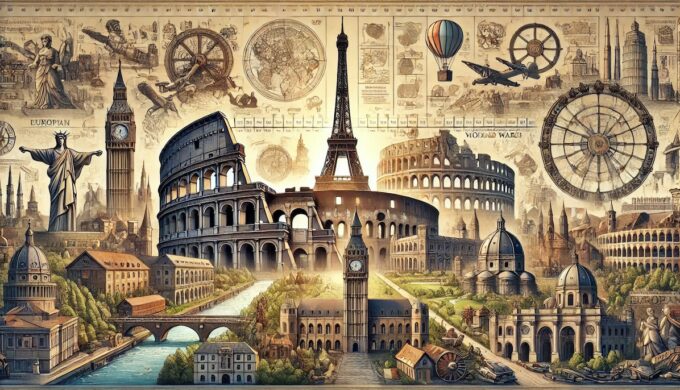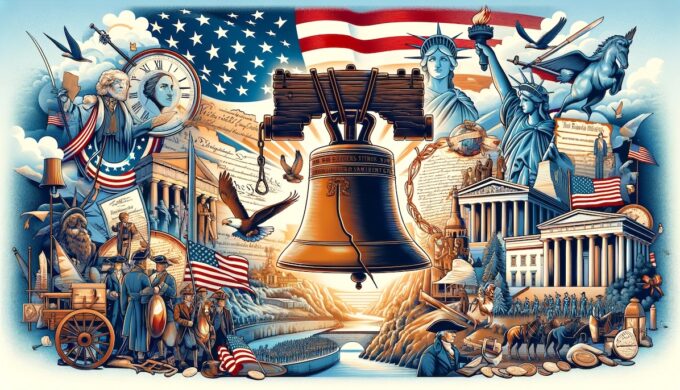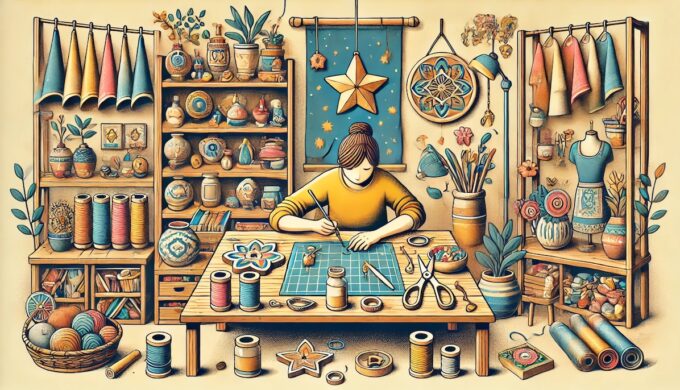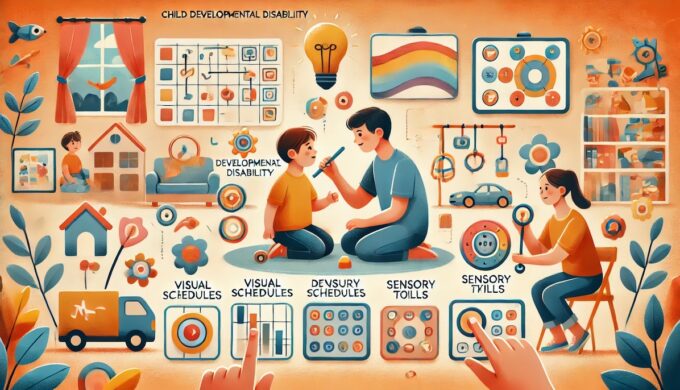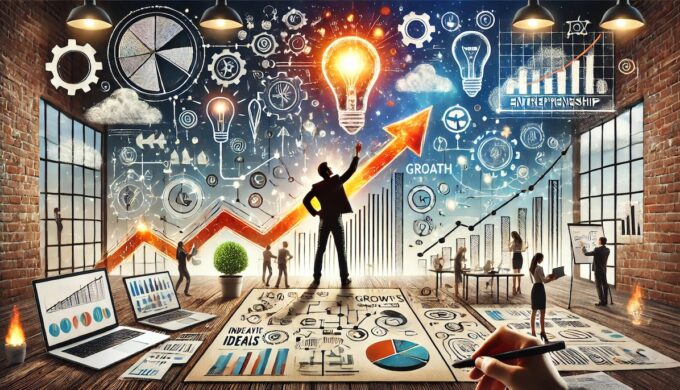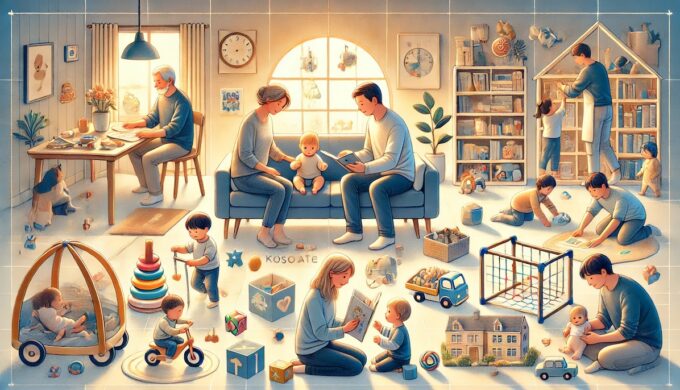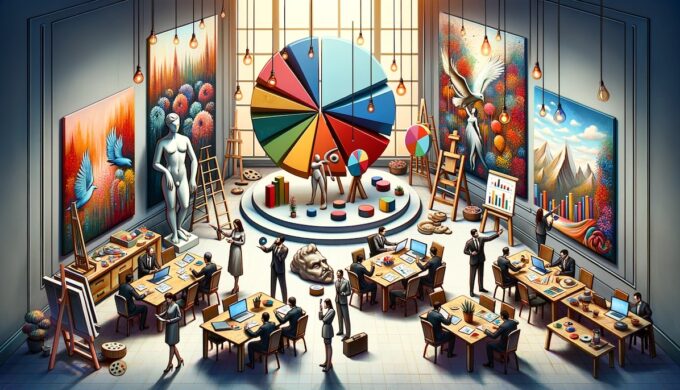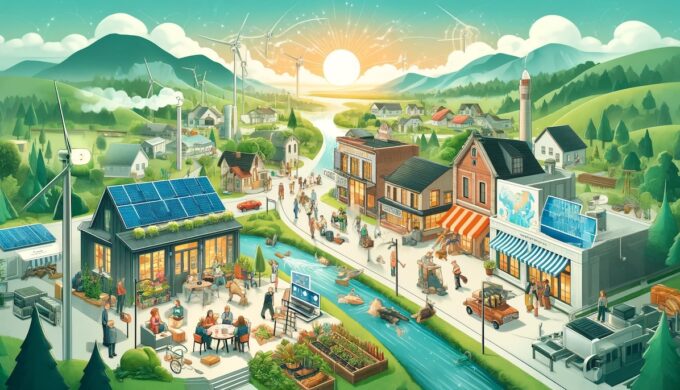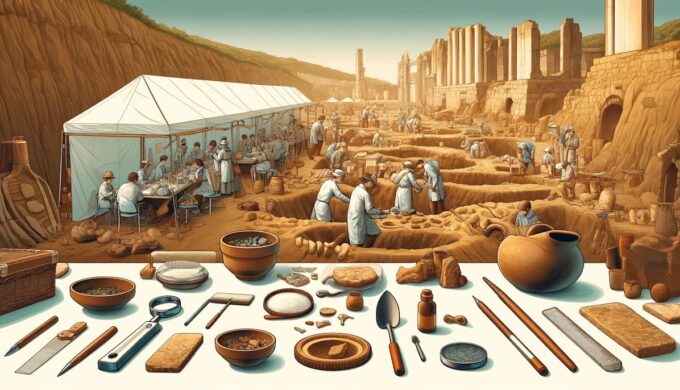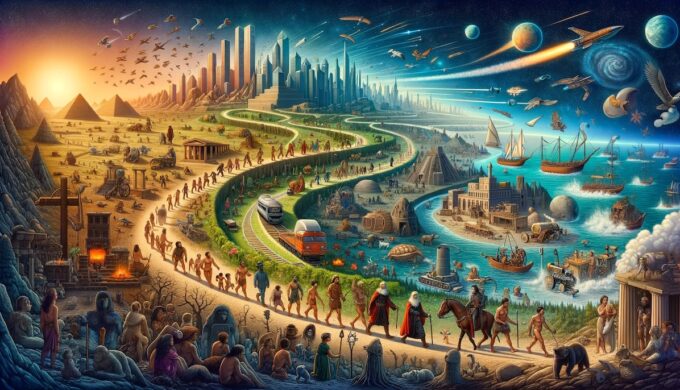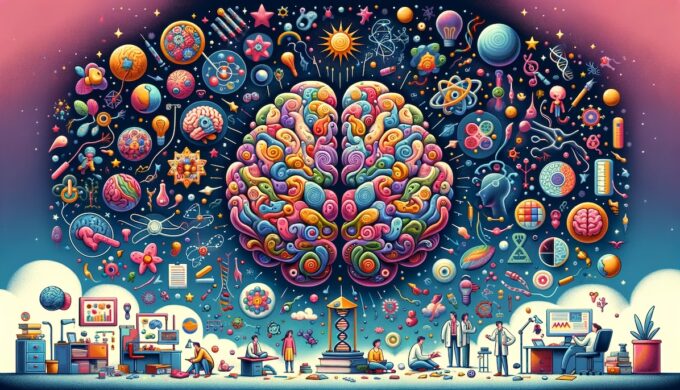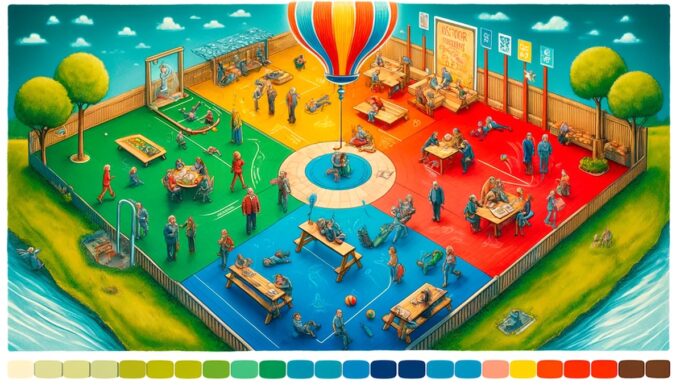美術史について知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
美術史とは、絵画や彫刻、建築などの美術作品がどのように誕生し、発展してきたかを時代や文化の背景とともに研究する学問です。アーティストや作品の意図、社会的な影響などを探りながら、美術の変遷や多様性を理解します。アートをより深く楽しむための視点を提供してくれます。
まずはじめに、美術史がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 美術愛好者:美術作品を鑑賞する際に、歴史的な背景や文脈を理解して、より深い鑑賞体験を楽しみたい
- 美術学生・研究者:美術史の理論や時代ごとの特徴、重要な作品や画家について学び、学問的な研究に活かしたい
- 美術館・ギャラリーの職員:展示作品の解説や教育プログラムに役立てるために、美術史の知識を深めたい
- アートコレクター:作品の歴史的な価値や背景を理解し、コレクションの品質を高めたい
- 美術教師・教育者:美術史を体系的に学び、生徒や学生に効果的に教えたい
- 歴史や文化に興味がある人:美術を通じて、各時代の文化的、社会的背景を学び、歴史に対する理解を深めたい
- 旅行者:美術館や歴史的な建造物を訪れる前に、美術史の知識を身につけ、訪問先の作品や文化遺産をより深く理解したい
- 芸術家・クリエイター:過去の美術様式や技法を学び、創作活動にインスピレーションを得たい
- 一般教養として学びたい人:美術史を通じて、幅広い文化的知識や教養を身につけたい
- 美術評論家やアートジャーナリスト:美術作品や展覧会を評価・批評するために、美術史の知識を深めたい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
最大45%還元
紙書籍 ポイントフェア
3/2(月)まで
今すぐチェック
おすすめ5選)美術史の本
美術史がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
「なんかよかった」で終わらない 絵画の観方 美術館が面白くなる大人の教養
書籍情報
美術館に行って楽しめる人、楽しめない人の違いは、ちょっとした観方の差だった!?
amazon.co.jp書籍情報より引用
・解説がないと楽しめない
・展覧会に行ってもなんとなく良かったで終わってしまう
・好きな絵があるのに、良さを言語化できない
もしかして、こんな悩みを抱えていませんか?
美術館に行くのが好きなのに、絵画に興味はあるのに、なんとなく楽しみきれない。
そんな悩みを抱えている人は少なくないと思います。
その効果的な解決方法は、自分なりの絵画の観方を身につけることです。
そうすることで、まるでピントの合ったメガネをかけるように、色鮮やかにそして今までと違ったように作品を鑑賞することができます。
でも残念なことに、絵画の観方は、基本的に誰も教えてくれません。
そこで、東大の美術史で学んだ筆者が、今回こっそりと絵画の観方、そのコツをまとめました。
オフィーリアはそもそも何を描いているのか、どこに着目したら良いのか。
モナ・リザはなぜ凄いのか。
有名絵画を含む 130 点以上の作品を使って、絵画の観方を解説をしています。
具体的に本書で解説している観方の秘密は「物語」と「歴史」の知識。
この二つの知識を身につけることで、自然と絵画の観方が身についていきます。
本書を読むことで初見の絵にも対応できる基礎力が養われ、美術館がもっと楽しくなること間違いなしです。
絵画が好きな方、教養を身につけたい方におすすめの本書、ぜひ一読ください。
解きながら楽しむ 大人の西洋美術史
書籍情報
楽しく解いて、深まる教養――西洋美術史を学びたい、大人のためのワークブック!
古代ギリシャ・ローマから20世紀まで、西洋美術史の大きな流れを、わかりやすく丁寧な解説で学べます。美術鑑賞の習慣づけにもぴったり!
* 毎日、気軽に・手軽に楽しく取り組めます
amazon.co.jp書籍情報より引用
* クイズや問題を解きながら読み進められます
* 日付を記入することで、学習の記録を残せます
美術の物語 ポケット版
書籍情報
世界中で絶賛! 今世紀最高の美術入門書!
◉ラスコーの洞窟壁画から現代アートまで、絶えず変化しながらも繋がっている壮大な美術史のすべてを網羅した決定版。
amazon.co.jp書籍情報より引用
◉豊富な美術作品を鑑賞しながら、平易な文体で“物語”を読むように美術史を楽しむことができる。入門・基本書として最高の一冊。
◉歴史の流れに沿った28の章立てで、時代毎に美術様式や芸術運動を整理。圧倒的な知識を持つ美術史家による充実した解説。
◉本文内で論じられる美術作品は、必ずその作品の写真を掲載。カラー図版376点、モノクロ図版64点収録。
『美術の物語 ポケット版』は、元本『美術の物語』に比べてページ数こそ668ページから1048ページへと増えたものの、大きさは大判から新書に近いサイズに、また重量は約1800gから約750gへといずれも半分以下にサイズダウン。
いつでも読みやすく、どこへでも持ち運びやすいので、すでに『美術の物語』をお持ちでも、「ポケット版」をお勧めします。
いちばん親切な 西洋美術史
書籍情報
本書は西洋美術入門者の方にもわかるよう、絵画やそれにまつわる写真などを大きく、ふんだんに掲載し、難しい用語にはルビを付け、丁寧に解説しています。
エジプト・メソポタミアに始まり、古代ギリシャ、ルネサンス・バロック・ロココに印象派などから、世紀末美術を経て、現代美術、その後の展開まで、美術史の全体像をしっかり学びながら、楽しく西洋美術を学べる一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
絵を見る技術 名画の構造を読み解く
書籍情報
・なぜ、この絵に惹きつけられるのだろう?
amazon.co.jp書籍情報より引用
・この絵の主役はどこ?
・前情報なしに、どう見たらいいの?
・バランスや構図が良いとか悪いとか、みんな何を見て言っているの?
ちゃんと絵の中にヒントがあるんです。
センスがなくても、知識がなくても、目の前の絵画を「自分の目で見る」、 そして「良し悪しを判断する」ことは、できるんです。
謎を解くカギは、ぜんぶ絵の中にあります。
絵の研究は、「意味」と「形」の二本柱。
この本では、これまであまり触れられてこなかった、「造形」の面から歴史的名画を見ていきます。
描かれたモノを「見る」ためには、少し見方を訓練していないと気づかないものです。
ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ルーベンス、 ベラスケス、フェルメール、ゴッホ、セザンヌ―― 超有名なあの名画、知られざるあの傑作、 どう見たらいいか迷う抽象絵画、20世紀を代表する写真まで―― どう見たらいいか、初めて分かるようになります。たくさんのカラー作品が練習問題。 はじめて見る絵でも、パズルを解くように絵を読み解いていく面白さ、 味わってみませんか? 「どういう絵に対しても使える本書で紹介した絵の見方は、 コンパスのような役割を果たしてくれるはず。 名画がどうして名画と呼ばれるのか。 今まで見ようとしなかった真実が、きっと見え始めるでしょう」――著者
注目の新刊)美術史の本
美術史がわかる本の注目の新刊を、紹介します。
今月は該当する新刊が見つかりませんでした。
ロングセラー)美術史の本
美術史がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる
書籍情報
美術史を知らずして世界とは戦えない!
西洋美術の知識は、ビジネスマンの必須教養。
amazon.co.jp書籍情報より引用
1日30分×20項目=10時間でざっと学べる、大好評『大学4年間』シリーズの最新企画。
これからの時代を生き抜くために必要な教養としての「西洋美術史」を、テレビなどでもおなじみ、ダ・ヴィンチ研究の泰斗・池上英洋東京造形大学教授が見開き完結でわかりやすく解説します。
改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト
書籍情報
美術検定対策本『美術検定公式テキスト 西洋・日本美術史の基本』と『美術検定 3級速習ブック』の2冊分を1冊にまとめ、再構成いたしました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
西洋美術、日本美術をそれぞれ「見てわかる」「読んでわかる」「ポイントでわかる」という構成でコンパクトにまとめています。
美術の入門者にとっても、手軽に美術史の大きな流れをつかむことの出来る内容になっています。
増補新装 カラー版 西洋美術史
書籍情報
古代から20世紀末まで、西洋美術の流れをコンパクトにまとめ、図版340点をオールカラーで掲載。
用語解説、カラー年表及び関連地図を添えた、美術愛好者の手引きとして、また、学生の参考書として最適の美術史入門書。高階秀爾(元国立西洋美術館館長・東京大学名誉教授)監修。
amazon.co.jp書籍情報より引用
多くの研究者・学生・美術愛好者に読まれ続ける美術書最大のベストセラー。
コンパクトなサイズで西洋美術の歴史をあますところなく伝える、美術関係者必携の書。
西洋美術史入門
書籍情報
本書は西洋美術入門者の方にもわかるよう、絵画やそれにまつわる写真などを大きく、ふんだんに掲載し、難しい用語にはルビを付け、丁寧に解説しています。
エジプト・メソポタミアに始まり、古代ギリシャ、ルネサンス・バロック・ロココに印象派などから、世紀末美術を経て、現代美術、その後の展開まで、美術史の全体像をしっかり学びながら、楽しく西洋美術を学べる一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
鑑賞のための 西洋美術史入門
書籍情報
美術用語って難しい、あの本では眠くなった…そんなあなたにこの1冊。
わかりやすい言葉と豊富なイラストでとにかく詳しく解説。
西洋美術のとっておきテキストです。【本の案内役リトルキュレーターが一緒に作品を鑑賞】
ギリシャ美術から現在進行形の美術の歴史をコンパクトに読みやすくまとめた、美術鑑賞の入門書です。
美術の解説書では知っている前提の専門用語や美術の概念、よく出てくる言い回しを引っ張り出して、Q&Aで誰にでもわかる言葉で説明します。本文はもちろん、はみ出し情報もとてもためになります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ふたりの学芸員さんのおしゃべり、美術に全く興味の無かったネコさんの素直な質問。
これらは理解をグッと身近にして「あぁそういうことネ」と最後まで読めます。
評判・口コミ
カラー版 1時間でわかる西洋美術史
書籍情報
西洋美術に対して、どことなく苦手意識を抱いている入門者に向け、名作の豊富な図版とともに、オールカラーでていねいに解説する西洋美術史ガイド新書です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
教養として西洋美術に親しむための基礎的な知識について、知識ゼロの状態からでも本書で一気に学びなおすことができます。
美術史を築いた巨匠の意外な人間味あふれるエピソードも収録。
世界史における西洋美術の果たした歴史的な役割を読み解くビジネスパーソン必見の内容です。
西洋美術史 (美術出版ライブラリー 歴史編)
書籍情報
最新の⻄洋美術史にして、永久保存版!
古代から現代アートまで、通史とポイントがすぐにわかる。「美術」の起源から、現代まで、全11章構成、約700点におよぶ豊富なビジュアルとともに通史を学ぶ、最新の「西洋美術史」が刊行します。本書は数々の美術系大学で教科書にも採用されている「ライブラリー 歴史編」のシリーズ第二弾。圧倒的な歴史のボリュームをこの一冊で学べる、待望シリーズの登場です。
本書の特徴は、重要項目を見開きごとに掲載し、そのポイントがひと目でわかる構成です。どのページからも読み始められるレイアウトで、これから美術を学ぶ人にも、さらに知識を深めたい人にも使いやすい内容となっています。執筆者は第一線で活躍する研究者15名。最新の視点から、いま私たちが学ぶべきポイントを、わかりやすく解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
美術館に行く前3時間で学べる 一気読み西洋美術史
書籍情報
美術館に行く前の3時間で学べる!
amazon.co.jp書籍情報より引用
絵画の歴史がすっきり分かり、展覧会巡りが楽しくなる!
技法の知識が深まり、自分なりの絵の見方が身に付く
アルタミラやラスコーなどの先史時代の美術から現代のバンクシーまで。約2万年以上にわたる西洋美術史の流れを108のエピソードで一気に学べる入門書。ざっくりと流れが把握できるだけでなく、名画の裏話、画家の恋愛事情、色彩の秘密、時代の変化によってどんな絵画の技法が生まれたのか、オールドマスターの画家の描き方が近現代の画家たちにどんな影響を与えたのかを、美術家ならではの視点で紹介します。絵画の歴史、知識が頭に入ると、自分なりの絵の見方が身に付き、美術展巡りの楽しみがぐっと深まります。
日本美術史
書籍情報
第一線の研究者による、 最新の日本美術史! 縄文から現代まで全10章構成。
500点以上にもおよぶ豊富なビジュアルとともに日本美術の通史を学ぶ、最新の『日本美術史』が刊行。本書の魅力は、歴史の重要項目を見開きごとに掲載し、そのポイントがひと目でわかる構成です。
どのページから読み始めても、前後の時代との関連性がわかる画期的なレイアウトにより、これから日本美術史を学ぼうとする人にはもちろん、さらに美術の知識を深めたいという人にも使いやすい内容となっています。25名の第一線で活躍する研究者たちが贈る「最新」の美術史を通じて、日本美術とは何か、そしてわたしたち日本人とは何かを知る手がかりとなる一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
美術史によくある質問と回答
美術史について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
美術史とは何ですか?
回答: 美術史は、過去から現代に至るまでの美術作品、美術運動、スタイル、そしてこれらを創造した芸術家たちに関する研究と解析の分野です。
この分野では、作品が作られた文化的、社会的、政治的背景を探ります。
美術史を学ぶメリットは何ですか?
回答: 美術史を学ぶことで、文化や時代を超えた人々の表現と思考を理解することができます。
また、視覚的な批評能力や批判的思考スキルを養うことができ、多様な文化への理解を深めることができます。
美術史の主な時代区分はどのようなものがありますか?
回答: 美術史は一般的に以下のような時代区分で語られます:
古代美術、中世美術、ルネサンス美術、バロック美術、近代美術、そして現代美術。
これらの各時代は特有のスタイルやテーマを持っています。
美術史で最も影響力のある美術運動は何ですか?
回答: 影響力のある美術運動には、ルネサンス、バロック、ロマン主義、印象派、キュビズム、モダニズムなどがあります。
これらの運動はそれぞれの時代において美術の方向性を大きく変え、後の芸術に多大な影響を与えました。
美術史の知識を日常生活にどのように活用できますか?
回答: 美術史の知識は、美術館や展覧会を訪れた際に作品の深い理解に役立ちます。
また、デザインやファッション、映画など他の創造的な分野での参考にもなり、文化的な対話や社会的な議論に貢献することができます。
美術史のスキルが活かせる職種とは?
「美術史」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- 美術館学芸員
- 美術館やギャラリーで美術品の収集、保存、展示企画を担当。
- 展覧会のキュレーションや解説文の作成、来館者への案内を行う。
- 美術史研究者
- 大学や研究機関で美術史を専門的に研究し、論文や著作を執筆。
- 美術作品や芸術運動の歴史的背景を研究し、美術史の新しい知見を提供。
- 美術史講師・教授
- 大学や専門学校で美術史を教え、学生に対して美術の歴史や理論を指導。
- 美術史に関する講義やセミナーを開催し、次世代の美術専門家を育成する。
- アートディーラー
- 美術品の売買を行い、コレクターや投資家に対して美術作品の価値をアドバイス。
- 美術史の知識を活かして、時代やスタイルに基づいた美術品の評価を行う。
- 美術評論家
- 美術作品や展覧会に関する批評やレビューを執筆し、メディアで発表。
- 美術作品の歴史的背景や社会的文脈を解説し、一般の人々に美術の理解を深める。
- アートコンサルタント
- コレクターや企業に対して、美術作品の購入やコレクションの形成に関するアドバイスを提供。
- 美術史の知識を活かして、投資価値のある美術品を見極め、購入をサポート。
- 展覧会キュレーター
- 美術館やギャラリーで特定のテーマに基づいた展覧会を企画・実施。
- 美術作品の選定や展示レイアウトを行い、テーマに沿った展示内容を構成する。
- 美術出版社の編集者
- 美術関連の書籍やカタログ、雑誌の編集を担当。
- 美術史に関する書籍の企画や執筆者とのやり取りを行い、質の高い出版物を制作。
- 文化財保護専門家
- 美術作品や建造物などの文化財の保存・修復を担当。
- 美術史の知識を基に、文化財の歴史的背景や価値を理解し、適切な保護方法を提案。
- 美術ツアーガイド
- 美術館や歴史的建造物のツアーを企画・運営し、美術史に関する解説を提供。
- 観光客や美術愛好家に対して、歴史的背景や作品の意義を分かりやすく説明する。
美術史に関する知識は、教育や研究、展示企画、文化財保護など、多様な分野で活用され、美術や文化に関する深い理解を社会に広める役割を担います。
まとめ
美術史について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、美術史がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。