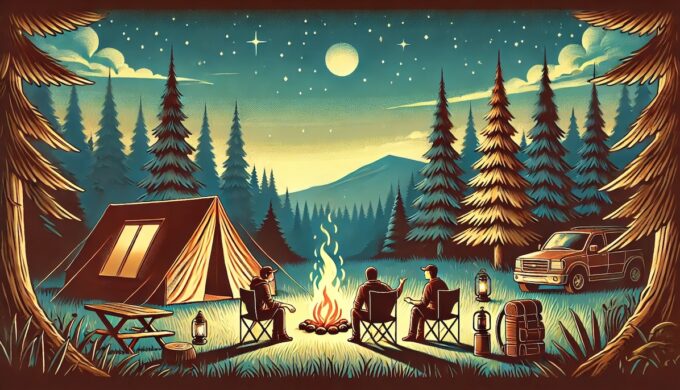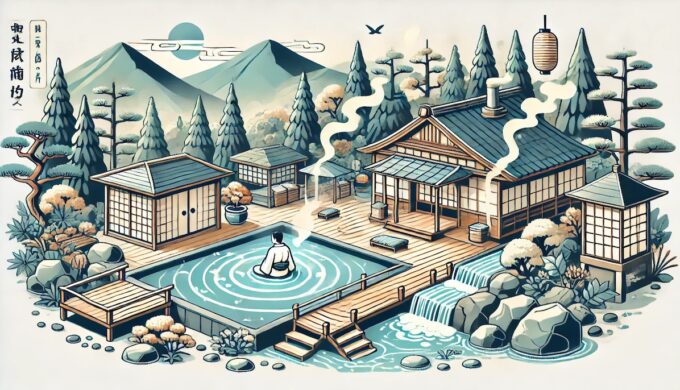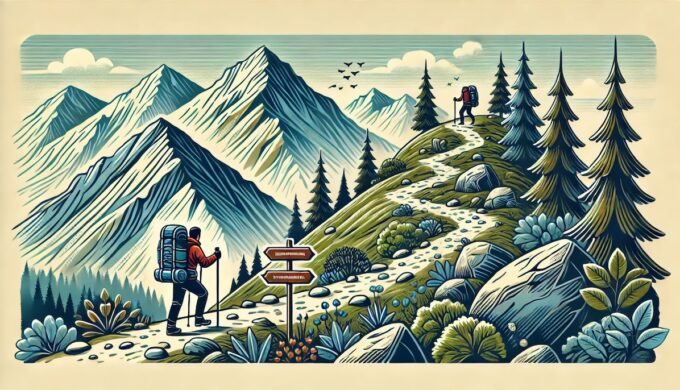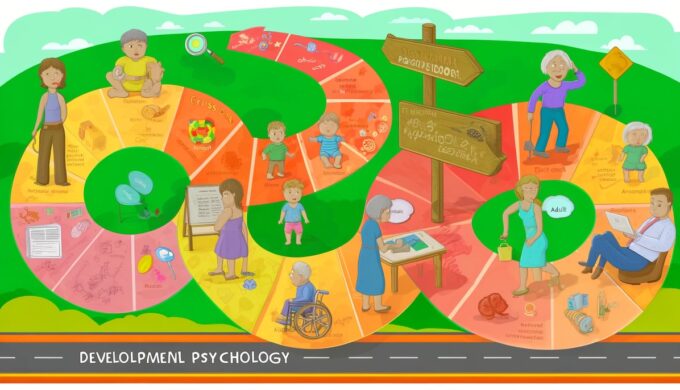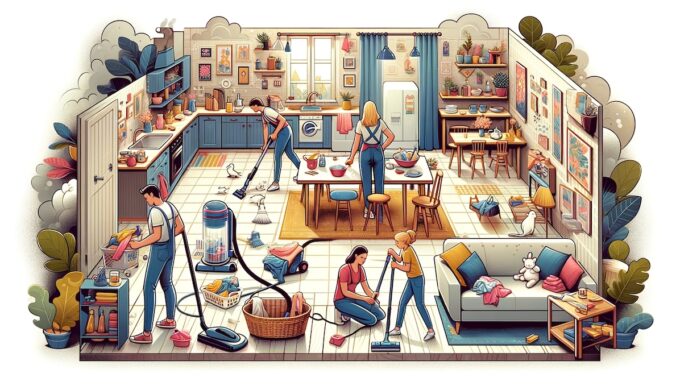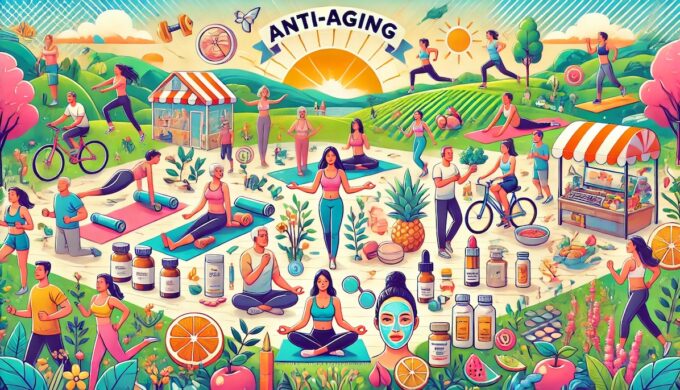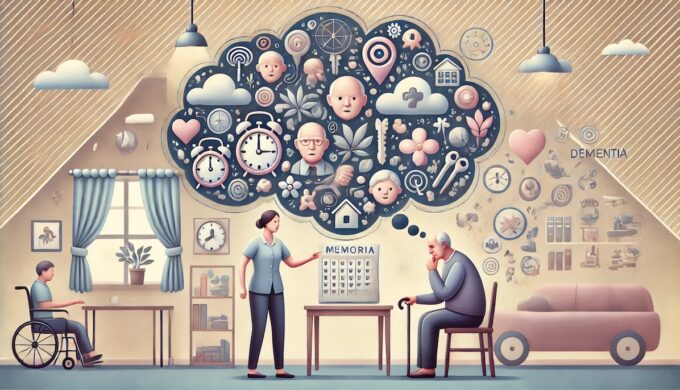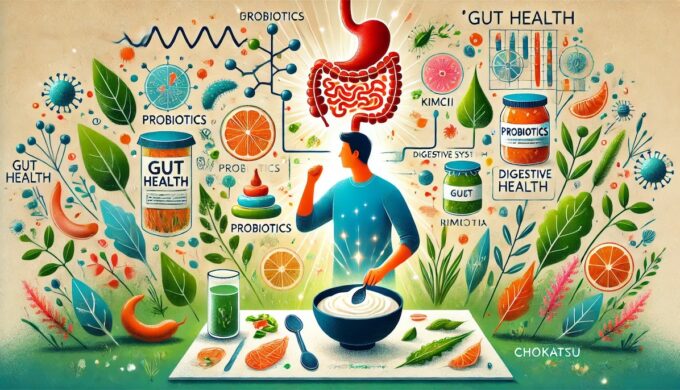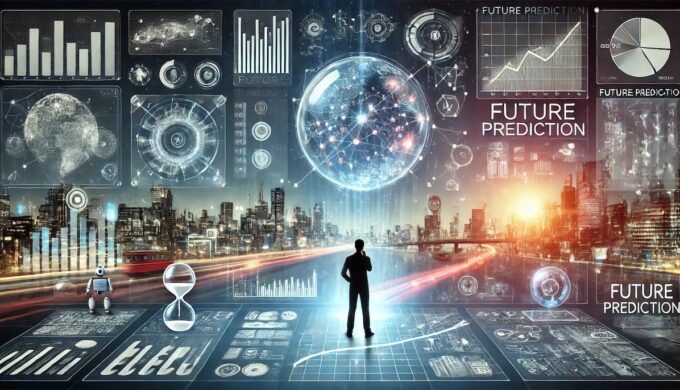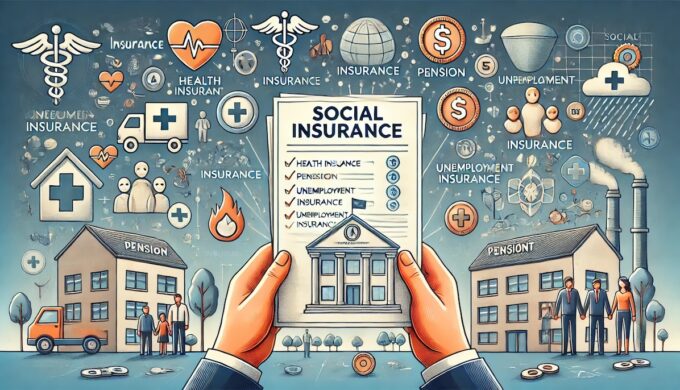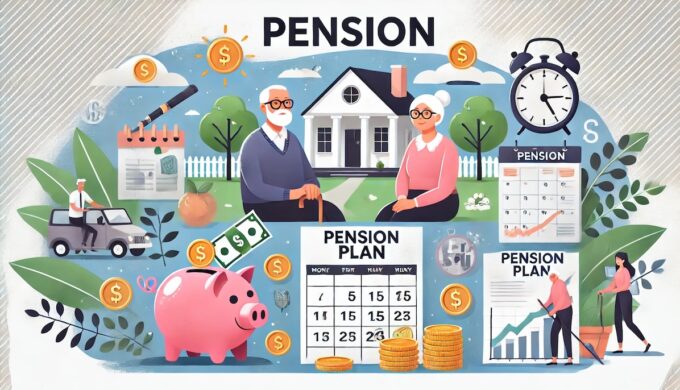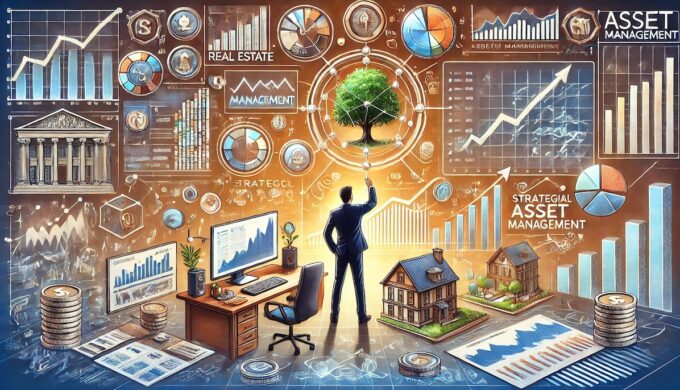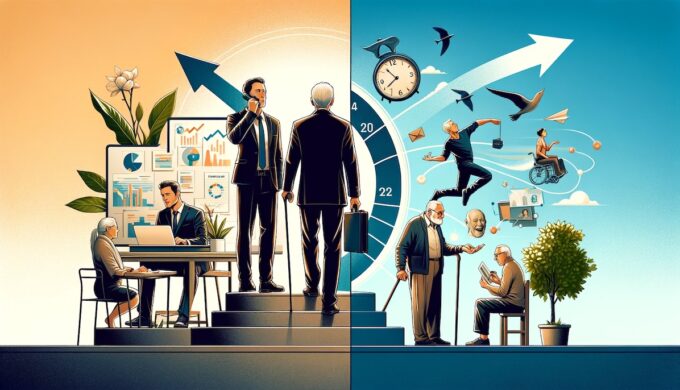老後について知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
老後とは、仕事を引退した後の人生の時期を指します。健康や生活資金の準備が重要で、趣味や家族との時間を楽しむことができる一方、新たな課題も生じることがあります。充実した老後を迎えるためには、計画的なライフプランが大切です。
まずはじめに、老後がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 定年を間近に控えた中高年層:老後の生活設計や資金計画を具体的に考えたい
- 定年後の生活に不安を感じている人:年金、医療、介護など、老後の備えを学びたい
- 老後資金の準備を始めたい現役世代:積立や投資を活用して、老後に備えたい
- 年金制度や仕組みを詳しく知りたい人:受給額や受け取り方法を把握し、生活設計に活かしたい
- 退職後も働き続けたい人:セカンドキャリアやシニア向けの働き方を検討したい
- リタイア後の趣味や生きがいを見つけたい人:余暇の過ごし方や新しい挑戦を考えたい
- 老後の住まいについて考えている人:リフォーム、ダウンサイジング、介護付き住宅などの選択肢を知りたい
- 家族の介護を見据えて準備したい人:老後の介護の実態やサービスについて学びたい
- 親の老後をサポートしたい子世代:親の生活や介護について具体的な情報を得たい
- 健康を維持しながら老後を充実させたい人:運動や食事、メンタルヘルスに関する情報を知りたい
- 老後の収入源を多角化したい人:年金以外の収入(投資、不動産、フリーランスなど)を検討したい
- 社会的なつながりを重視したい人:地域コミュニティやボランティア活動に参加し、孤立を防ぎたい
- 終活やエンディングノートを考えている人:自分らしい最期を迎えるための準備をしたい
- 若い世代で早期リタイアを目指す人:早い段階から老後を見据えて資産形成やライフスタイルを計画したい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
最大45%還元
紙書籍 ポイントフェア
3/2(月)まで
今すぐチェック
おすすめ5選)老後の本
老後がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
最高の老後 「死ぬまで元気」を実現する5つのM
書籍情報
高齢者の2割には病気がないことを知っていますか?
今から備えればまだ間に合うかもしれません。日本人の平均寿命は男性が約81歳、女性は約87歳。
でも、元気に自立した生活を送ることができる期間である「健康寿命」は、男性なら約72歳、女性なら約75歳と報告されています。
日本人は最後の約10年を、支援や介護を受けて生きているのです。・65歳以上の約10人に1人は車椅子か寝たきり
・65歳以上の約5人の1人は認知症
・65歳以上の約3人に1人は5種類以上の薬を毎日飲んでいる
・65歳の約5人の4人は、少なくとも1つ以上の慢性疾患を持つ
・死に直面している人の約10人中7人は自分で意思決定ができないこれらの現実をどうしたら変えられるか、最後の10年を人の助けを借りず健康に暮らすためにはどうしたらよいのか、その答えとなるのが「5つのM」。
カナダおよび米国老年医学会が提唱し、「老年医学」の世界最高峰の病院が、高齢者診療の絶対的指針としているものです。【5つのM】
Mobility ーーからだ
Mind ーーこころ
Multicomplexity ーーよぼう
Medications ーーくすり
Matters Most to Me ーーいきがいニューヨーク在住の専門医が、この「5つのM」を、質の高い科学的エビデンスにのみ基づいて徹底解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
病気がなく歩ける「最高の老後」を送るために、若いうちからできることすべてを考えていきます。
60歳からは、「これ」しかやらない 老後不安がたちまち消える「我慢しない生き方」
書籍情報
「孤独」「健康」「金(お金)」…老後不安の「3K」は「やりたいことだけ」やれば消える!
amazon.co.jp書籍情報より引用
「これまで、高齢者専門の精神科医として6000人を超える高齢者の方々を診てきて、つくづく感じるのは、老いには非常に大きな個人差があるということです。70歳前なのにヨボヨボと老け込んでしまう人もいれば、100歳近くでもキビキビ、生き生きしている人もいます。
その分かれ目はどこにあるかというと、結局のところ、心です。
悲観的だったり、固定観念にとらわれていたり、したいこともせず我慢していたりする人は、老化のスピードが明らかに速いと感じます。
みなさんは、どうでしょうか?
60歳からは人間関係が途絶えて、孤独になって、つまらなくなる……という勝手なイメージを抱いだいていませんか?
60歳からは病気がちになって、食事制限をしたり、薬を飲んだりするのが当たり前だと思っていませんか?
60歳からは収入が減るから、お金を使いすぎないように気をつけなくてはならないと思っていませんか?
そう思っているとしたら、我慢しない生き方なんて、どうして可能なのか、疑問に思うでしょう。
ここから、その疑問を解いていきましょう。
そして、60歳からの人生が自由と幸福に満ちていることを知っていただきたいと思います」
――本書「はじめに」より
「おふたりさまの老後」は準備が10割 元気なうちに読んでおきたい! 68の疑問と答え
書籍情報
【子どものいない夫婦(おふたりさま)の老後はどうなる?】
【おふたりさまはもちろん、おひとりさま・子どもに頼りたくない人も、知っておきたい知識が満載!】
【自分の財産が把握できる「財産管理ノート」付き!(購入特典:Excelファイルもダウンロードできる!)】衝撃の「おふたりさま老後問題」とは?
「夫(妻)の遺産」をすべて相続できるわけではない!さらに、これらもすべて間違いです。
×遺言書を書けば、すべてその通りになる
×体が不自由になったら、施設に入れる
×いつでも持ち家を売って、引越しできる
×自分の貯金はいつでも引き出せるおふたりさまの老後は「お金があれば安心」ではありません。
おふたりさまの老後は、不安や疑問がいっぱい!
・どちらかが介護状態になったらどうする?
・配偶者に先立たれて、ひとりになってしまったらどうする?
・身元保証してくれる人がいなくなったら、入院や施設入居はどうする?
・認知症になってしまったらどうする?
・継承者がいないけど、お墓はどうする?
・高齢者施設って、どんなものがある?
・自分が死んだあとの手続や処理は、誰にお願いすればいい?↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
amazon.co.jp書籍情報より引用
これらの不安や疑問に、本書がすべて答えます!
老後ひとり難民
書籍情報
子どもがいなければ、いずれは“老後ひとり難民”に。
入院できない!施設に入れない!死後は無縁仏に!?準備不足な“おひとりさま”の悲惨な末路。
amazon.co.jp書籍情報より引用
世はおひとりさまブームで、独身人口は増え続けるばかり。だが、そのまま老後を迎えて本当に大丈夫だろうか? 配偶者や子どもなどの“身元保証人”がいない高齢者は、入院だけでなく、施設への入居を断られることも多い。高齢で体が不自由になるなか、認知機能の低下で金銭管理が怪しくなり、果ては無縁仏になるケースも。本書ではこのような現実に直面し、かつ急増している高齢者を「老後ひとり難民」と呼び、起こりがちなトラブルを回避する方法と、どうすれば安心して老後を送れるのかについて解説。読むだけで老後の生き方・考え方が劇的に変わる一冊。
老後の年表 人生後半50年でいつ、何が起きるの…? で、私はどうすればいいの??
書籍情報
老後は多くの問題が降りかかってきます。
ただ、 問題が何歳頃に、どんなふうに起きやすいのかを知っておけば、事前に対策が立てられて、被害を小さくすることができる 場合もあるのです。そこで 本書では、「老後の年表」と銘打ち、何歳ごろに何が起きるのかの一覧を紹介。
amazon.co.jp書籍情報より引用
さらに、解決策も詳しく説明しています。
ですから、 被害が起きた後やその年齢を超した後も、被害を減らせることもあるのです。
老後の問題はなんとなくわかってはいるものの、「そのうち時間ができたら」「ウチは大丈夫」と先延ばしやほったらかしにしている人がほとんど。
しかし、いつ・どのように起きやすいのかを知ることで、そこへ向けて予防策を行動に移す気持ちが一気に高まるのです。
著者は、老後問題について1000人以上から相談を受け、250組以上の家族会議に参加し、79億円以上の財産管理をサポートしてきた老後問題解決コンサルタント。
さらには、経済や法律の専門家、医師、不動産会社などプロフェッショナルによる情報を提供することで、お金(相続含む)、健康、人付き合い、生前整理など、老後にありがちな問題を解決へと導きます!
注目の新刊)老後の本
老後がわかる本の注目の新刊を、2冊、紹介します。
老後ひとりの大正解!
書籍情報
ひとり世帯は年々増え続け、ひとりで老後を迎えることへの不安を抱える人は多くいます。 いまは元気でも、高齢になると賃貸物件を借りる際や入院手続き、将来的に施設へ入居する際などに問題が発生することも。そのようなことにならないために、できる準備の正解と、起こりがちなトラブルを回避する方法、どうすれば安心してひとりの老後を送れるのかについて徹底解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
老後を心おだやかに生きる いのちと向き合う医師の僧侶が伝えたいこと
書籍情報
人生100年時代
-これからの生き方、大切な人との過ごし方-「体が弱った」「今後が不安」と感じるのは自然なこと。
amazon.co.jp書籍情報より引用
約30年、多くのシニアの方と家族に向き合ってきた著者が「医師」と「僧侶」の立場からメッセージを贈ります。
あなたの「体」と「心」がホッとする一冊です。
ロングセラー)老後の本
老後がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
81歳おじいちゃん医師が教える 本当に幸せな老後
書籍情報
「いい人生だった」と笑顔で振り返るために
amazon.co.jp書籍情報より引用
健康・生きがい・人間関係……幸せな老後を迎えるために、今から考えるべきこととは?
人生100年時代といわれる現在、リタイア後の数十年を幸せに過ごせるかどうかは、私たち一人ひとりにとって大きなテーマとなっています。「仕事を辞めたら生きがいがなくなってしまうのではないか」「病気とどう向き合えばいいのか」「介護が必要になったときはどうすればいいのか」と、不安を抱えている人は少なくありません。実際、生命保険文化センターが行った調査(2022年)によると、8割以上の人が自分の老後生活に「不安感あり」と回答しています。
半世紀以上にわたり医療の現場に立ち続け80歳を超えた今も現役の医師として活躍している著者は、これまで数えきれないほどの患者の老後を見守ってきました。そのなかで、充実した現役時代を過ごしてきた人でも決して幸せとはいえない老後を迎えてしまったケースを数多く見てきたといいます。そして幸せな老後は偶然に訪れるものではなく、老いに対して十分な準備を行うことで手に入れることができるものと確信するようになりました。
本書では、医師として55年、そして81年の人生を歩んできた著者が考える「幸せな老後」について解説しています。健康管理の方法、かかりつけ医との上手な付き合い方、家族関係を良好に保つヒント、趣味や社会活動を通じた生きがいづくりなど、幸せな最期を迎えるために何が必要なのかを具体例を交えながら紹介しています。
自身や家族が人生の最終章をより豊かに、より幸せに過ごすためのヒントが詰まった一冊です。
老いる勇気
書籍情報
「18歳の頃の自分に戻れるとしたら、戻りたいですか?」――あなたが中高年世代の方だとしたら、この問いにどう答えますか?著者の元にカウンセリングに来られる50代、60代のほとんどの方は、この質問に「戻りたくない」と答えるそうです。体力や記憶力が若い頃と比べて低下しているにも関わらず、なぜなのでしょうか。
それは、今ある知識や経験が、人生の様々な局面で学び得たものであり、歳を重ねたからこその、物事の深い理解や味わいを知っているからだと著者は言います。
本書は、アドラー心理学とギリシア哲学を学んできた著者が、「今、ここ」を精一杯生き、老いを愉しむための最上の幸福論を説いたものです。
「生産性で人の価値は決まらない」「人生はマラソンではなくダンスである」「大切な人の心の中で生き続ける」「人間は何歳からでも変われる」……、これから老いを迎える人も、老いの真っただ中にいる人も、きっと珠玉の言葉に出合えることでしょう。
amazon.co.jp書籍情報より引用
老後ひとり暮らしの壁 身近に頼る人がいない人のための解決策
書籍情報
老後ひとり暮らしの8割が不安。
でも…
「誰にも余計な世話をかけたくない!」「自分のことは自分で決めたい!」この1冊で、あなたのおひとりさま生活はもっと思い通りになる。
今日の夜、突然倒れたら、あなたはどうしますか?
身元引受人や連帯保証人を頼める人はいますか?
なんでも相談できる人はいますか?数千軒の老後ひとり暮らしをサポートしてきた生前整理、遺品整理のプロが「お金の壁」「健康の壁」「心の壁」「介護の壁」「死後の壁」を越える考え方と方法を解説!
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
年金暮らし ひとり老後のお金と手続き 税理士・社労士が教える最善の暮らし方Q&A大全
書籍情報
ひとり老後の人は「自身が老後難民にならない」
amazon.co.jp書籍情報より引用
ひとり老後の親を持つ人は「親を老後難民にさせない」ための必読書!
日本では今、団塊世代が75歳を迎える「2025年問題」により、ひとり老後の人が急増しています。
さらに、身寄りのない高齢者のために設けられた社会的支援の手が届かない「老後難民」も増え、大きな社会問題になっています。
ひとり老後は、独身の人に限らず、家族のいる人にも離婚や死別によって、ある日突然やってきます。
そのとき、生活資金が足りなくなった、夫婦の年金が1人分に半減した、入院時の身元保証人を頼める人がいない、要介護になったが世話してくれる人がいない、今の家に住めなくなった、などと慌てることがあってはいけません。
ひとり老後になったときは、高齢者のために用意された数多くの社会的保障・支援を利用することが重要です。
例えば、家事を手助けしてくれる代行サービス、住民の輪をつなぐ地域包括支援、孤独死を回避するための見守りサービス、介護や介助をしてくれる公的介護サービス、高齢者の資産を守る任意後見制度や家族信託、死亡届や埋葬などを行ってくれる死後事務委任などがあります。
要は、こうした保障や支援をうまく利用することで、安心・安全な老後を送ることができるのです。
本書は、50代・60代前半のうちにひとり老後にどう備えるか、60代後半・70代でイザひとり老後になったときに生活をどう守るか、具体的な方法を一問一答式でマンガや図解を多用してわかりやすく解説します。
55歳からでも絶対おトク! 定年前後 お金の老後戦略
書籍情報
定年前後のお金の老後戦略は意外と安心
amazon.co.jp書籍情報より引用
使い切ってなんぼの老後のお金
定年前後 お金の老後戦略オールやることリスト
親と私の老後とお金完全読本
書籍情報
老後資金のうち、介護資金は平均約580万円とされますが、親にとっても子にとっても不安は尽きません。人生も終わりよければすべてよし。本誌は、親に介護が必要になったとき、サービスやケアを受けるには実際どれくらいのお金がかかるのか、介護費用を安くする方法や、子どもに迷惑をかけない方法、子も知っておきたい実家リフォームの補助金制度、後見人制度でもしものときに子が親のお金を引き出せるようにしておくなど、親子で一緒に考えておきたいお金のこと、お得な制度の活用方法を紹介します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
老後ひとり、暮らしています。
書籍情報
76歳。そう、私は今、人生最高の時をすごしている。
子供二人は立派に巣立ち、2年前には夫を亡くして寂しい老後……と思いきや、ひとりがこんなに気楽で楽しいなんて。毎日公衆浴場に通い、週に3回はヨガに行き、1日は山に登り、日曜日はジムで運動。自転車で風を切り、YouTubeで学び、コーラをごくごく飲む。最近のおばあさんには、自分なりのルーティンがあり、習ってみたいことが、いくらでもあるのだ。
体調、お金、外見の老化、孤独。待ち受ける人生の不安におののくことなかれ。老後を軽やかに羽ばたく年配者からの辛口アドバイスが全世代を勇気づける必読の書。将来への不安と焦りが消える痛快エッセイ。
amazon.co.jp書籍情報より引用
おひとりさま[老後生活]安心便利帳 2026年版
書籍情報
もうひとりで悩まないで!
お金、健康、介護、相続、葬儀……
「困ったとき、どうすればいい?」「誰が助けてくれるの?」ひとりで暮らす高齢者の不安も、高齢の親と離れて暮らす方の不安もまるっと解消!
amazon.co.jp書籍情報より引用
楽しく賢くムダ知らず 「ひとり老後」のお金の知恵袋
書籍情報
お金との付き合い方を変えれば、人生はまだまだ楽しめます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ひとり暮らしの高齢者がどんどん増えています。
また、人生百年時代を迎えた今日では、「シニアといわれるようになってからどう生きるか」が大きなテーマになります。
そんなひとり暮らしのシニアのみなさんが、特に不安に感じているのが「お金」でしょう。
本書は、お金のやりくりを中心に、体力、気力、感覚や感情などの微妙な衰えも上手にやりくりして、
「ひとり老後」の日々をこれまで以上に幸せに生きていくための考え方やちょっとした知恵、スキルなどをまとめたものです。
肩肘張らずに、「小耳に挟む」ような感覚で、ぜひ気になったところからお読みくださいませ。
この1冊で賢く備える おひとりさまの老後大全
書籍情報
一家に一冊! シニア世代が安心して暮らすための「お困りごと解決本」!
amazon.co.jp書籍情報より引用
近年、65歳以上のひとり暮らしが増えています。
今は配偶者がいても、いずれ身近に頼る人がいなくなる可能性は誰にでもあります。
年金・退職金、医療、介護、働き方、防犯、防災、終活など、日々の暮らしをより楽しく、不安のないものに。
いざというときのためにもしっかり準備していきましょう。
大切な資産を守りながら、病気や亡くなったときに備えていくには何をすればよいのか、セカンドライフを楽しくいきいきと過ごすにはどうすればよいのか、各ジャンルにおけるプロフェッショナルがQ&A形式でわかりやすく解説します。
親御さんへのプレゼントにも最適です。
老後によくある質問と回答
老後について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
老後とは具体的に何歳からを指すのですか?
回答: 老後とは通常、退職後の生活を指し、多くの国で65歳からとされていますが、個人の退職時期や健康状態、生活環境によって異なることがあります。
老後の資金計画はどのように立てるべきですか?
回答: 老後の資金計画を立てる際には、まず必要な生活費を見積もり、それに基づいて退職後に必要な資金総額を算出します。
年金、貯蓄、投資収入など、収入源を確認し、足りない分については追加の貯蓄や投資計画を考慮することが重要です。
老後の健康管理にはどのようなことを心がけるべきですか?
回答: 老後の健康管理には、定期的な健康診断を受けること、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠が重要です。
また、ストレス管理と社会的交流も健康を維持するためには欠かせません。
老後の時間の使い方でおすすめはありますか?
回答: 老後は趣味や旅行、ボランティア活動、新しいスキルの学習など、自分の興味や楽しみを追求する良い機会です。
また、家族や友人との時間を大切にし、充実した社会生活を送ることもおすすめします。
老後の住まいの選び方についてアドバイスはありますか?
回答: 老後の住まいを選ぶ際には、安全性、利便性、医療施設へのアクセスの良さを考慮することが大切です。
また、将来的に必要になるかもしれない介護サービスやコミュニティのサポートもチェックすると良いでしょう。
老後の知見が活かせる職種とは?
「老後」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 老後の資金計画や年金の最適な受け取り方、資産運用についてアドバイスを提供。
- 老後に備えたライフプランの作成をサポート。
- 介護施設スタッフ
- 高齢者の生活支援や介護サービスを提供し、老後の生活を快適にするためのケアを行う。
- 日常生活のサポートやリハビリを実施。
- 年金アドバイザー
- 年金制度の仕組みや受給方法について、高齢者やその家族にわかりやすく説明。
- 年金に関する手続きのサポートを行う。
- シニアライフコンサルタント
- 老後の住まいや健康管理、趣味・生きがいづくりなど、総合的なシニアライフのアドバイスを提供。
- 老後の生活全般について相談を受け、具体的な解決策を提案。
- リタイアメントプランナー
- 定年後の生活設計を支援し、経済面や心理面での準備をサポート。
- 退職金の運用や老後の収入源に関するアドバイスを行う。
- 高齢者向け住宅コンサルタント
- 老後に適した住まいの選択やリフォーム、バリアフリー化のアドバイスを提供。
- 高齢者向けの施設やサービス付き住宅の紹介を行う。
- 介護保険アドバイザー
- 介護保険制度の利用方法や手続きについて、わかりやすく説明し、適切な支援を提供。
- 高齢者が利用できる福祉サービスの提案を行う。
- 健康アドバイザー(シニア向け)
- 老後の健康維持や生活習慣病予防のためのアドバイスを提供。
- 運動や食生活の改善プランを提案。
- セカンドキャリア支援コンサルタント
- 定年後の仕事やボランティア活動、趣味を通じた社会参加をサポート。
- 高齢者の経験やスキルを活かした再就職や活動の提案を行う。
- シニア向けイベント企画者
- 高齢者が楽しめるイベントや講座を企画・運営し、生きがいづくりや社会参加を促進。
- 趣味や健康促進、交流の場を提供する。
老後に関する知識や経験は、ファイナンス、介護、健康、生活支援など、多岐にわたる分野で活用され、高齢者が充実した生活を送れるよう支援する仕事に役立ちます。
まとめ
老後について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、老後がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。