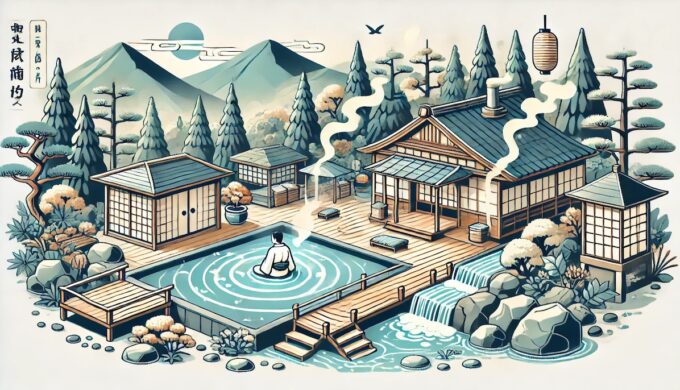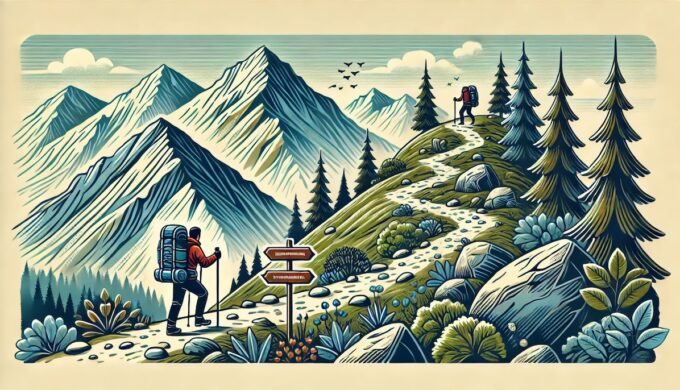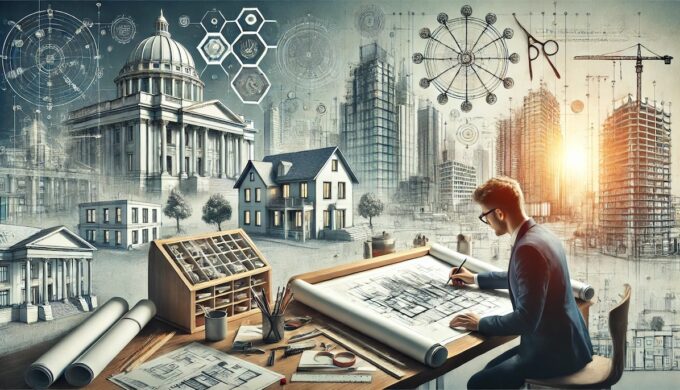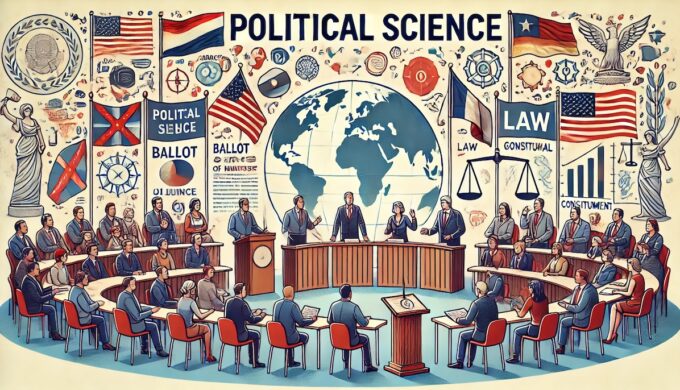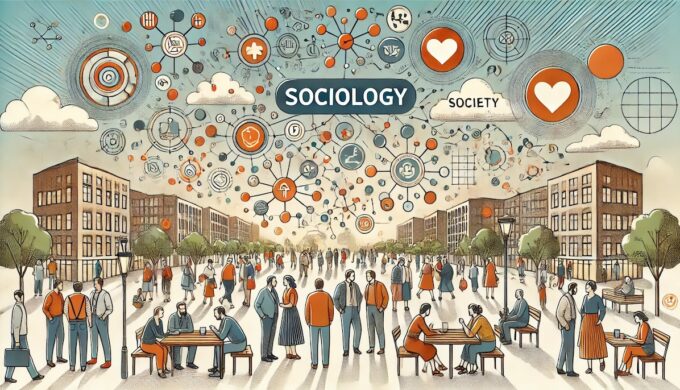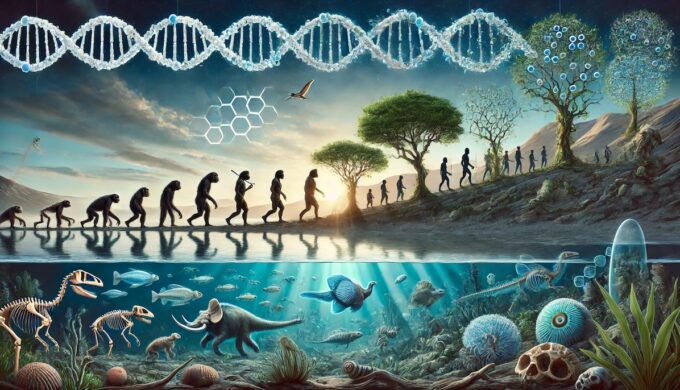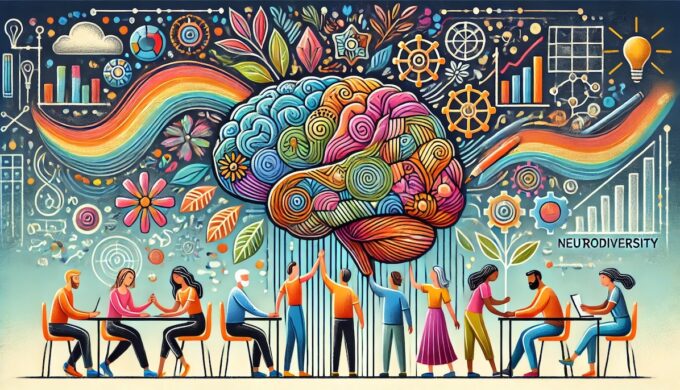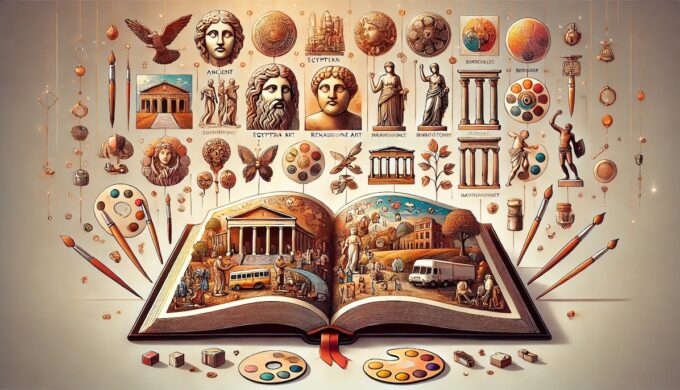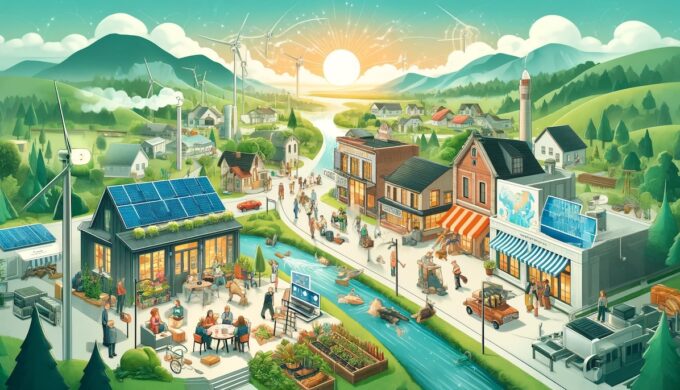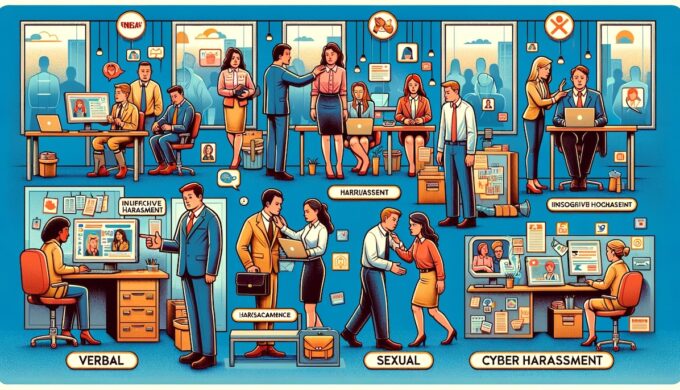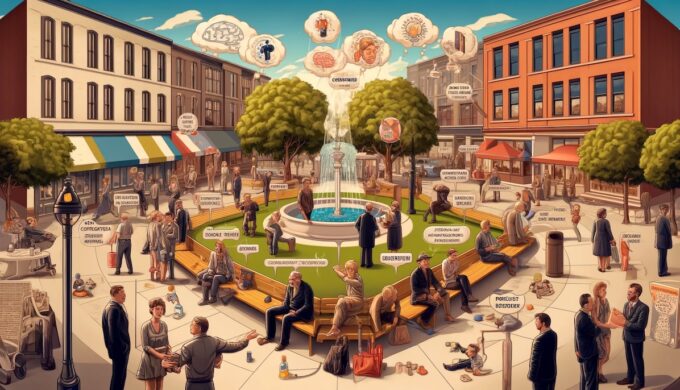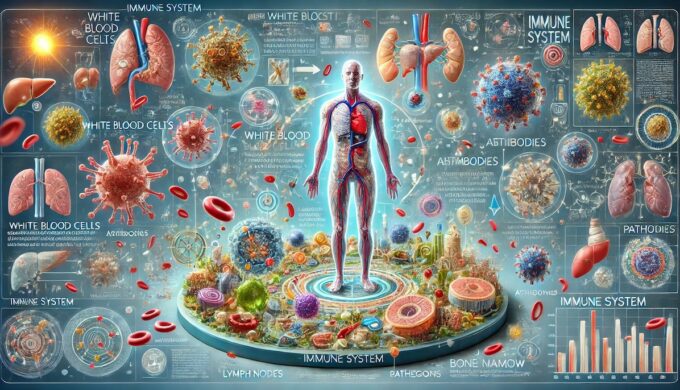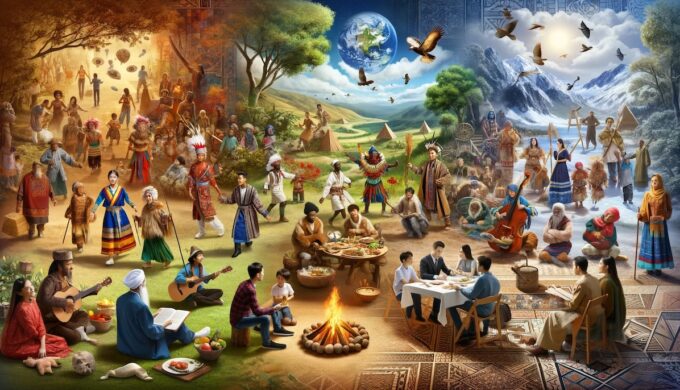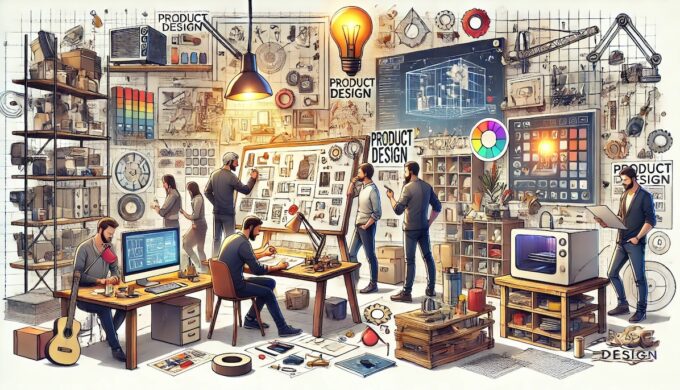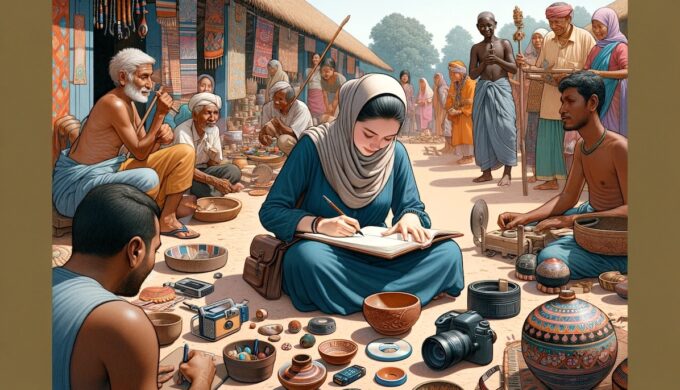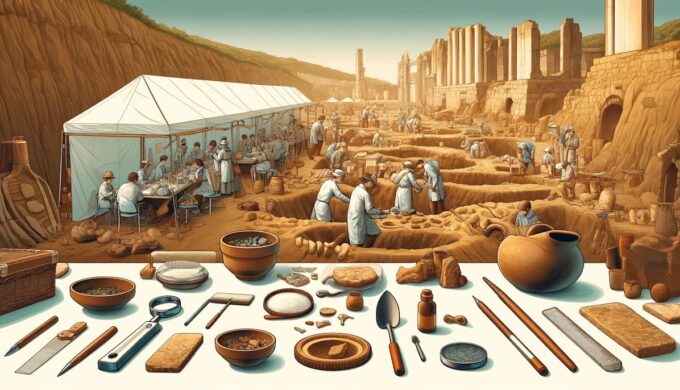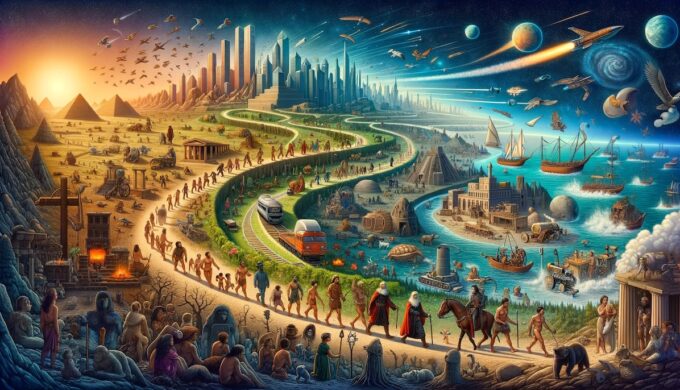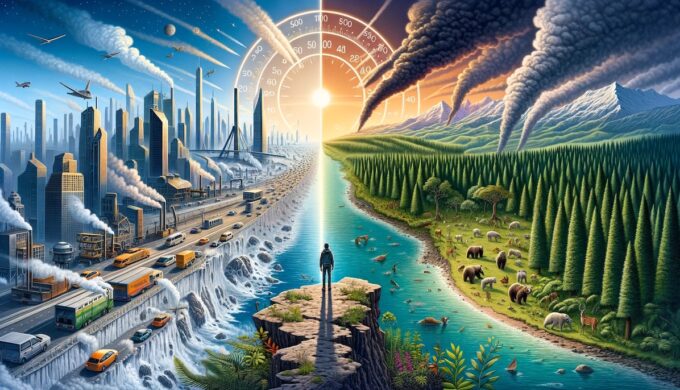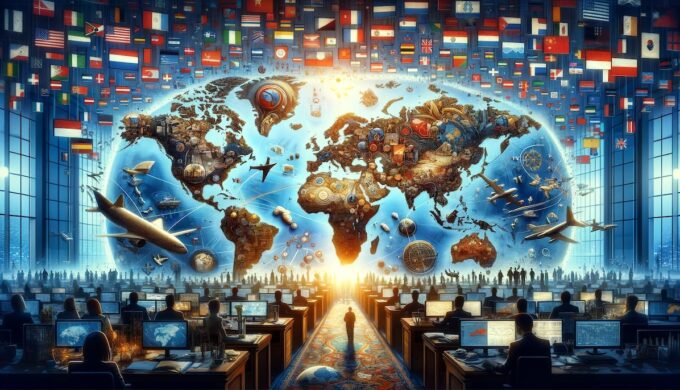文化人類学について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
文化人類学とは、世界中のさまざまな文化を研究し、人々の生活様式、信念、言語、社会構造などを比較・理解する学問。文化の多様性を深く掘り下げ、異文化間の相互理解を促進することを目指します。人類が築き上げてきた複雑で豊かな文化の網の目を解き明かし、人間行動の普遍的なパターンや地域特有の習俗を学びます。
まずはじめに、文化人類学がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 学生:文化人類学の理論、方法論、研究事例を学びたい
- 研究者:異文化間の相互作用や文化のダイナミクスに関する研究を行っている
- 教育者:大学や高等教育機関で文化人類学を教えている
- 社会学者:社会と文化の相互関係に関心がある
- ソーシャルワーカー:多文化的なコミュニティでの実践に役立つ知識を求めている
- ビジネスプロフェッショナル:グローバル市場での文化的感度と理解を深めたい
- 政策立案者:公共政策や国際関係の文脈で文化的要素を考慮したい
- 旅行愛好家:異文化を深く理解し、体験したい
- NGOや国際組織のスタッフ:異文化間の協力や開発プロジェクトに関わっている
- 自己啓発に興味がある一般読者:世界のさまざまな文化についての理解を広げたい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!
最大50%OFF 7月24日(木)まで
Kindle本(電子書籍)準新作本セール
いますぐチェックする
おすすめ5選)文化人類学の本
文化人類学がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
よくわかる文化人類学[第3版]
書籍情報
文化人類学の主要なテーマをやさしいことばで解説し、その面白さと奥深さの両方を伝える定番の入門書に最新版が登場。
近年の研究動向を踏まえた新しいテーマも加えて、学問の全貌をつかむことができる。
amazon.co.jp書籍情報より引用
異文化/他者を鏡として自文化/自己を見つめなおす、オーソドックスかつ斬新なテキスト。
自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門
書籍情報
〈私とは違う誰か〉と生きるための文化人類学入門
「家族にとって血のつながりは大切」「“日本人”とは日本人の親を持つこと」「日本では宗教を信じる人はめずらしい」……
それって本当?自分にとってのあたりまえが、実はあたりまえではなかったことに気づく。
amazon.co.jp書籍情報より引用
多様な人々と共に生きる、未来のための文化人類学入門。
文化人類学入門(増補改訂版)
書籍情報
文化人類学とは、社会・文化・経済・宗教をはじめ諸分野にわたって、またそれぞれに異なる世界の民族を比較検証する広範な研究対象を視野に収めた学問である。
その方法論として、フィールド・ワークによる具体的でしかも忍耐強い実証的な調査が重視される。
本書は、この多岐にわたる学問を系統的に要約整理した入門の書として、1979年刊行以来、多くの読者を得て版を重ねてきたものを増補改訂し、学界の新しい情報を提供する。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
文化人類学の思考法
書籍情報
あたりまえを疑う。
言うは易しだが、これが思うようにできない。手ぶらでやろうとすると気づかぬうちにかつての「あたりまえ」のなかに囚われてしまう。
生活のあたりまえ、男女のあたりまえ、会社や仕事のあたりまえ、経済や文化のあたりまえ、国家のあたりまえが劇的に変わっていこうとしているなか、これまでの「あたりまえ」から出ていくためには、優れた道具が必要となる。
文化人類学は「これまでのあたりまえ」の外へと出ていくための「思考のギア(装備)」だ。
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書はその最先端の道具が一式詰まった心強い「道具箱」だ。
こんなに「使える」本は滅多にない。
ビジネスマンからクリエイター、学生まで、下手な実用書を買うくらいなら、これを常備しておくことをおすすめする。
WIRED日本版元編集長・若林恵氏
評判・口コミ
ヘタレ人類学者、沙漠をゆく 僕はゆらいで、少しだけ自由になった。
書籍情報
「圧倒的な面白さ!」と話題の人類学本、爆誕!
amazon.co.jp書籍情報より引用
山極壽一氏、松村圭一郎氏、中島岳志氏、小川さやか氏…各界より大推薦!!!
「理解不能な出来事を目の前にすると、相手を否定して自分を守ろうとしてしまう。しかし異質なものを、異質なものとして見ていても何も生まれない。偏見や独りよがりな思い込みではなく、『知』に『血』を通わせて、人と接していきたい。
ずっと興味があった人類学の世界。その一歩が踏み出せそう!」
――ジュンク堂書店 藤沢店 小山さん
白と黒ではわけられないこの複雑な世界で、他者とともにあるために――。
今こそ、僕たちには人類学が必要だ。
注目の新刊)文化人類学の本
文化人類学がわかる本の注目の新刊を、1冊、紹介します。
お土産の文化人類学 地域性と真正性をめぐって
書籍情報
「東京ばな奈」は、なぜ東京土産の定番になれたのか?
そして、なぜ菓子土産は日本中にあふれかえるようになったのか?
調査点数1073点、身近な謎に丹念な調査で挑む画期的研究。日本人は旅行に行くと必ず菓子の土産を買って周囲に配る。しかし実はこれは、案外最近定着した振る舞いにすぎない。1970年~80年代を境に、土産はモノから食べ物中心へと劇的に変化した。なぜこれほどまで全国に似たような菓子土産があふれるようになったのか、そもそもなぜ土産を購入するのか。
本書ではその問いをきっかけとして、日本における土産の歴史と現在を詳細な資料調査と、文化人類学の手法によって解き明かす。そこから見えてきたのは、交通網の発展に伴った大量生産、大量消費の時代から、国策も背景とした地元でしか作れない本物性へのこだわりへの転換だった。菓子土産についての初めての学術的研究が誕生。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ロングセラー)文化人類学の本
文化人類学がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
詳論 文化人類学 基本と最新のトピックを深く学ぶ
書籍情報
文化人類学をより深く、詳しく学びたい読者のために、24のトピックから知る最前線の研究
本書の目的は、文化人類学の基礎を学んだ学生を対象に、同分野をより深く掘り下げて解説すると同時に、新たな研究動向についても紹介することにある。
全体を2部に分けて、第Ⅰ部「基本領域」では、姉妹書の綾部恒雄・桑山敬己編『よくわかる文化人類学 第2版』(ミネルヴァ書房,2010年)の内容を詳述かつアップデートし、第Ⅱ部「新たな展開」では最新の理論やテーマを取り上げる。
真剣に学びたい学生のために、学界を代表する研究者が力を結集して書いた入魂の一冊!
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
これからの時代を生き抜くための 文化人類学入門
書籍情報
「人新世」というかつてない時代を生きるには、《文化人類学》という羅針盤が必要だ。
ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」と行動をともにしてきた人類学者による、“あたりまえ"を今一度考え直す文化人類学講義、開講!!本書は、ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」との日々を描いたエッセイ『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』が話題となった人類学者・奥野克巳による、私たちの社会の“あたりまえ"を考え直す文化人類学の入門書になります。
シェアリング、多様性、ジェンダー、LGBTQ、マルチスピーシーズ…といったホットワードを文化人類学の視点で取り上げ、《人新世》と呼ばれる現代を生き抜くためのヒントを、文化人類を通して学んでいく一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
はじめて学ぶ文化人類学 人物・古典・名著からの誘い
書籍情報
未知との出会いを求めて
タイラー、ボアズ、マリノフスキー、レヴィ=ストロース、ギアツ、クリフォード…
約60名の文化人類学者を通して見える、人類学の魅力と奥深さ19世紀後半から現在まで150年に及ぶ文化人類学の展開の軌跡を、主要な研究者の生涯と業績・著作に焦点を当て 読み解く。
文化人類学の初学者にも最適な入門テキスト。
amazon.co.jp書籍情報より引用
古典から最新の研究動向までカバーし、人類学の 大きな学問潮流を捉える道案内(ガイド)を提供する。
文化人類学のエッセンス 世界をみる/変える
書籍情報
私たちの身近な経験とつながる制度や出来事を人類学はどのように見るのか、最新の成果をわかりやすく伝える入門テキスト。
文化と社会の多様性がわかるさまざまなテーマを通じて世界の見方を学び、世界を変えていく手がかりを得るための1冊。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
文化人類学 [カレッジ版] 第4版
書籍情報
人間にとって文化とはなにか。
文化を見つめることで、人間が見えてくる。身体観、死生観、宗教、世界観など、人を理解するうえで欠かせない「文化」をさまざまな切り口で紹介することで、これまでの概念にとらわれない新たな視界をひらく。
いま再びいのちについて考えるための、スタンダードでありながらも新しい文化人類学テキスト。
amazon.co.jp書籍情報より引用
21世紀の文化人類学
書籍情報
『文化を書く』の批判、グローバル化による「未開」の消失などを乗り越えて甦る新世紀の文化人類学。
そのパラダイムシフトの認識=存在地図を、超越論的、不可量部分、生成変化、存在、レジリエンス、リスクなどの新鮮なキーワードで描出。
amazon.co.jp書籍情報より引用
文化人類学キーワード 改訂版
書籍情報
文化人類学という幅広い学問分野の中から、100の基本的なキーワードを厳選し、見開き2頁で解説する。
初版刊行後10年間の社会の変動と学問の進展を反映させるため、各項目のヴァージョン・アップをはかると同時に、必要に応じて新しい項目に入れ替えた。
amazon.co.jp書籍情報より引用
東南アジアで学ぶ文化人類学
書籍情報
東南アジアには11の国々があるが文化の多様性はその比ではない。
ひとつの国でも、多様な言語・宗教・習慣をもつ人々が暮らしている。
いわば文化人類学にとって研究対象の宝庫。あなたも、私たちの当たり前を疑う文化人類学の目を通して東南アジア社会を学んでみよう。
amazon.co.jp書籍情報より引用
そして一緒に「人間とは何か」を問うてみよう。
恋する文化人類学者 結婚が異文化をつなぐとき
書籍情報
私と彼女のフィールドワークーー結婚相手は、アフリカのアイドルだった。
研究者の卵として、ストリート音楽をフィールドワークするためにアフリカに渡った著者。そこで出会ったのは音楽を生業とする一人の少女だった。未知の文化との遭遇、共感、そして結婚ーー。「他者とつながるためには、一度、自分の殻を壊す必要がある。それは痛みを伴う」。
自らの経験を素材として文化人類学へと誘う体験的入門。来日した妻と、ふたつのルーツをもつ娘との日常を綴った補章「ラブロマンスのゆくえ」を収録。
amazon.co.jp書籍情報より引用
文化人類学によくある質問と回答
文化人類学について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
文化人類学とは何ですか?
回答: 文化人類学は、人間の文化的多様性を研究する学問分野です。
これには、言語、宗教、社会構造、芸術、経済システム、日常生活の慣習など、さまざまな文化的側面が含まれます。
文化人類学者は、異なる社会や文化グループを比較し、人間行動と文化的表現の理解を深めることを目的としています。
文化人類学の研究方法にはどのようなものがありますか?
回答: 文化人類学の主な研究方法には、参与観察、インタビュー、文献調査、調査研究、ケーススタディなどがあります。
参与観察は特に重要で、研究者がコミュニティに入り込み、その文化を内側から学ぶ方法です。
これにより、その文化における行動様式や価値観を深く理解することができます。
文化人類学で研究される主なトピックにはどのようなものがありますか?
回答: 文化人類学で研究されるトピックには、家族構造、宗教的信仰と儀式、言語使用、民族間の相互作用、性別役割、経済活動、政治システムなど、人間社会のほぼすべての側面が含まれます。
また、グローバリゼーション、移民、アイデンティティ、環境問題など、現代社会の問題に関する研究も行われています。
文化人類学は他の人類学の分野とどのように異なりますか?
回答: 人類学には、文化人類学の他に、社会人類学、考古学、生物人類学、言語人類学などの分野があります。
社会人類学は文化人類学と密接に関連していますが、より社会的な関係や構造に焦点を当てます。
考古学は過去の人類の遺物や文化を研究し、生物人類学は人間の生物学的進化を扱います。言語人類学は、言語と文化の関連を探ります。
文化人類学の知見はどのように実用的に活用されますか?
回答: 文化人類学の知見は、国際関係、教育、公衆衛生、人権擁護、市場調査、製品開発、多文化間コミュニケーションなど、多岐にわたる分野で実用的に活用されます。
異なる文化間の相互理解を深めることで、効果的な国際協力やビジネス戦略の策定、社会政策の形成に貢献します。
また、多文化社会における教育や公共サービスの質の向上にも役立てられます。
文化人類学のスキルが活かせる職種とは?
文化人類学は、人間の文化的多様性とその背景にある社会構造や信念システムを研究する学問分野です。
この分野の知識や経験を習得することによって、以下のような幅広い職種で仕事を担当することができます:
- 大学教員/研究者:
- 大学や研究機関で文化人類学を教えるとともに、研究プロジェクトを行います。学術論文の執筆や学会での発表など、学問の発展に貢献します。
- 市場調査アナリスト:
- 消費者の行動や嗜好、文化的背景を理解するために、文化人類学の手法を活用します。製品開発やマーケティング戦略の策定に役立つ洞察を提供します。
- NGO/国際機関のスタッフ:
- 開発援助プロジェクトや人道支援活動において、地域社会の文化的背景を理解し、プログラムの設計や実施を行います。
- 文化財保存スペシャリスト:
- 歴史的建造物や文化的伝統を保護・保存するための活動に携わります。地域社会の文化遺産の価値を高めるための研究や教育プログラムを実施します。
- ユーザーエクスペリエンス(UX)リサーチャー:
- ウェブサイトやアプリケーションのデザインプロセスにおいて、ユーザーの行動やニーズを理解するための調査を行います。文化人類学的な視点から、より使いやすく意味のある製品設計に貢献します。
- コンサルタント:
- 企業や組織に対して、組織文化の評価や変革、多様性と包摂性の促進に関するアドバイスを提供します。文化的洞察を活用して、組織のパフォーマンス向上に貢献します。
- ジャーナリスト/ライター:
- 文化的なテーマに関する記事や書籍を執筆します。世界各地の社会や文化に関する深い理解をもとに、読者に新たな視点を提供します。
- コミュニティ開発スペシャリスト:
- 地域社会の発展に貢献するプログラムやイニシアティブを立案・実施します。地域の文化的背景を尊重しつつ、社会的・経済的な課題の解決に取り組みます。
文化人類学の知識や経験は、グローバル化が進む現代社会において、文化的な違いを理解し、様々な背景を持つ人々と協働する能力を高めます。
これらのスキルは、教育、研究、ビジネス、開発、デザインなど、多岐にわたる分野で価値があります。
まとめ
文化人類学について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、文化人類学がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。