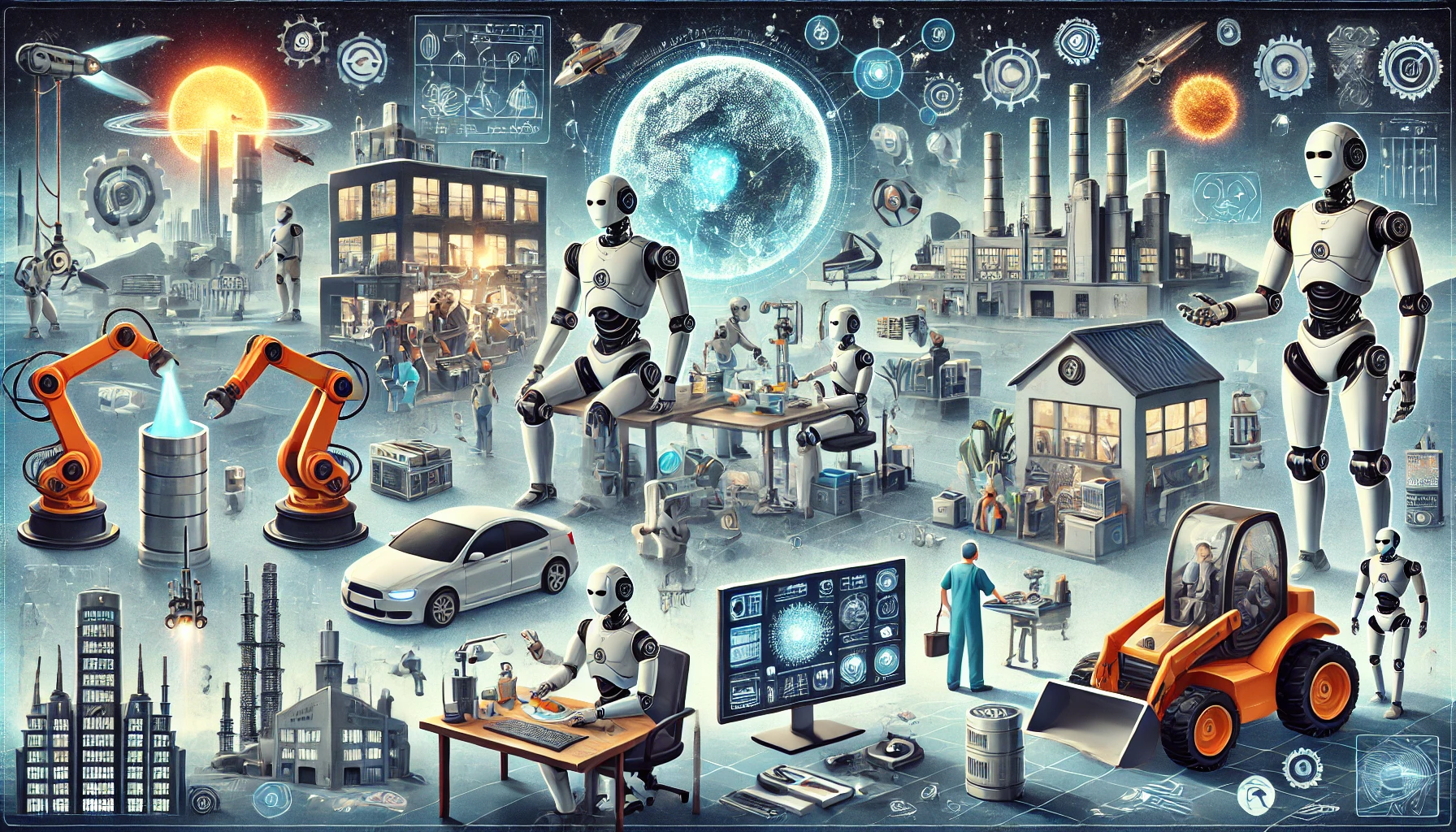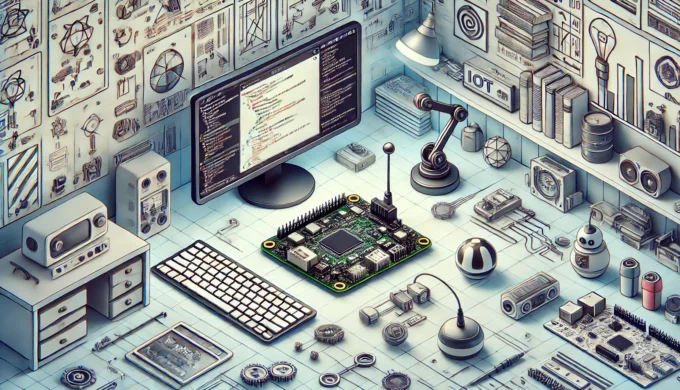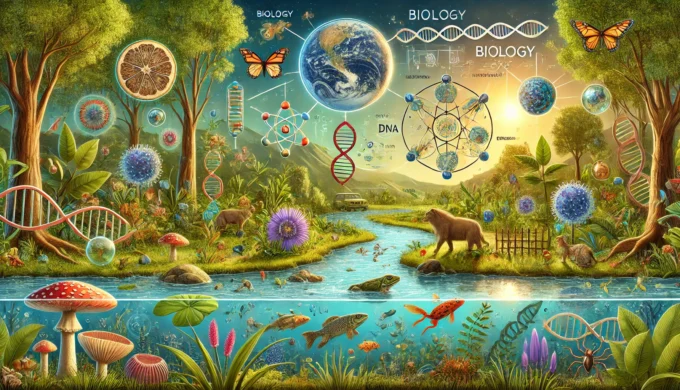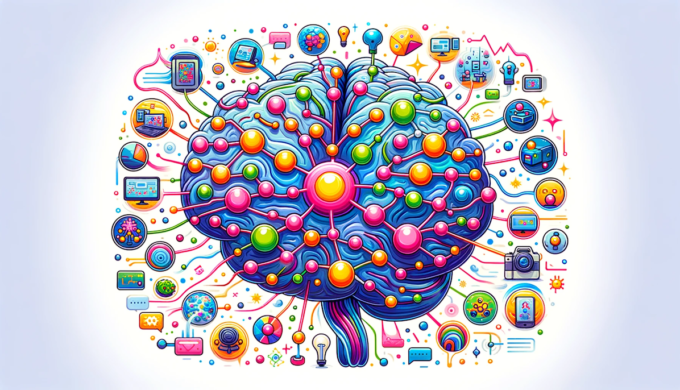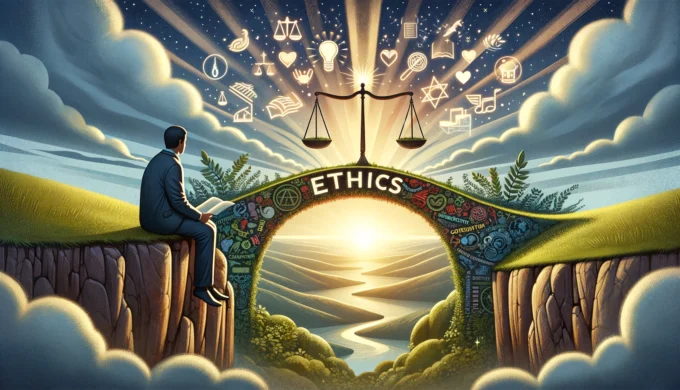ロボットについて知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
ロボットとは、プログラムされた指示に従い、自律的または半自律的に作業を行う機械です。工業生産、医療、家庭作業、探索など様々な分野で活躍し、人間の作業を補助または代替します。センサーや人工知能を搭載することで、環境を認識し複雑なタスクを遂行する能力を持ちます。
まずはじめに、ロボットがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- エンジニア・技術者:ロボットの設計、開発、プログラミングに関する知識を深めたい。
- 研究者・科学者:ロボット工学や人工知能に関する最新の研究成果や技術を学びたい。
- 学生:ロボット工学やメカトロニクスの基本から応用までを学び、将来のキャリアに備えたい。
- 教育者・教師:学生にロボット工学を教えるための教材や教授法を探している。
- 趣味としてロボットを作りたい人:家庭でロボット製作を楽しみたいホビイストやDIY愛好者。
- 産業用ロボットのユーザー:工場や製造現場で産業用ロボットを使用し、効率的な運用方法を学びたい。
- 医療従事者:医療用ロボットの最新技術や応用方法を理解し、患者ケアや手術の支援に役立てたい。
- ビジネスプロフェッショナル:ロボティクスのビジネスチャンスや市場動向を理解し、ビジネス戦略に活かしたい。
- 一般の興味を持つ読者:ロボットの歴史、技術、未来の展望について知りたい。
- SF作家・クリエイター:ロボットの技術や応用について理解を深め、作品にリアリティを加えたい。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう!
最大70%OFF、10月24日(木)まで
Kindle本ストア12周年キャンペーン
今すぐチェックする
おすすめ5選)ロボットの本
ロボットがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
入門 ロボット工学
書籍情報
ロボット工学の基礎事項をひと通り学べる書籍です。
2自由度ロボットアームをおもな題材とし、直感的にわかりやすい内容・説明で読みやすくなっています。
難しい数学表現はなるべく使わず、数式を使う場合も導出過程がていねいに示されています。
例題や演習問題により、理解度の確認もできます。
また、後半にある簡単な数値シミュレーション例を活用すれば、学んだ内容をより具体的に実感することもできます。はじめて学ぶ学生のほか、他書では難しいと感じている方にもおすすめの1冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
イラストで学ぶ ロボット工学
書籍情報
◆◆「 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 部門教育表彰(2020年)」受賞!◆◆
あれから3年、ホイールダック2号が帰ってきた!
大好評書『イラストで学ぶ人工知能概論』の第2弾。・ホイールダック2号@ホームの開発ストーリー仕立てだから、ロボット工学の基本がいとも簡単に理解できる!
amazon.co.jp書籍情報より引用
・重要な数学的記述を可能な限り解説したので、マニピュレータ制御における数学的・物理的なイメージが掴める!
・計算力が身につく章末問題が充実しているので完全無敵! ジークジオン!
評判・口コミ
はじめてのロボット工学 第2版 製作を通じて学ぶ基礎と応用
書籍情報
2足歩行ロボットの製作を通じてロボット工学の基本がわかる!
ヒューマノイドロボットをベースに、できるだけ数式を用いずに、図でわかりやすく説明したロボット工学の入門書です。
前半では、ロボットの歴史や構造から、モータやセンサ、機構や制御までを体系的に学習します。
後半の章では、アルミ加工からモーション作成までのロボットの作り方を解説します。
高校・専門学校・高専・大学などで、実習製作にも利用できる内容です。第2版は、2007年に発行された初版の基本的な構成はそのままに、10年のうちに著しく変化した情報を更新・追加しました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
製品スペックなどの情報を最新のものに差し替え、また、実習で使用する部品も2018年現在容易に入手できるものに変更し、板金だけでなく3Dプリンタによる制作方法も追加しました。
さらに、深層学習などにより飛躍的に進歩した分野について、「Chapter 9 ネットワークによる連携と発展」を新設しました。
評判・口コミ
ロボット大図鑑 どんなときにたすけてくれるかな? 1 くらしをささえるロボット
書籍情報
光村図書令和6年度版小学2年生国語の教科書に掲載されている「ロボット」の著者・佐藤知正先生の監修による最新ロボット図鑑。
生活のどのような場面で活躍しているのか用途別に分類して紹介しているので、調べたいロボットがすぐにみつかります。
また、低学年でも理解しやすいよう、登場するロボットにはすべて「どんなときに何をして人間を助けてくれるのか」という見出しをつけて簡潔に説明しています。1巻では、そうじ用ロボット、介護用サポートロボット、ペットロボットなど、おもに家庭で使用されているロボットを紹介しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
さらに、図鑑の内容を整理できるシートも掲載。
わかりやすいロボットシステム入門 (改訂3版) メカニズムから制御、システムまで
書籍情報
ロボットシステムが包括的に理解できる定番教科書、待望の改訂!
人工知能技術に代表される知能化や開発環境の変化、掃除ロボットの普及、サービスロボットの実用化、自動運転関連技術の進展など、ここ数年、ロボットやその技術を取り巻く環境は大きく変化しています。
本書は、旧版の内容を見直し、これらの技術的・社会的な変化を取りこみつつ、ロボットシステムの基礎から応用技術までを丁寧に解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
注目の新刊)ロボットの本
ロボットがわかる本の注目の新刊を、3冊、紹介します。
改訂新版 ROS 2ではじめよう 次世代ロボットプログラミング ロボットアプリケーション開発のための基礎から実践まで
書籍情報
本書は、2019年に刊行した「ROS2 ではじめよう 次世代ロボットプログラミング」の改訂版です。
ロボット開発のためのミドルウェアROS 2の普及に伴い、改訂版ではROS 2に焦点を当てて、基本概念から応用、実践的な使用方法までを幅広くカバーしています。
ROS 2の歴史と特徴、開発環境のセットアップ、基本機能と応用機能、C++やPythonを使ったプログラミング方法、主要なツールやパッケージの紹介、ROS 2のエコシステムなどについて解説します。
さらに、実際のロボットハードウェアを使用した実践的なプログラミング例も紹介します。本書は、ロボット開発者やエンジニア、研究者、教育関係者、そしてロボットビジネスに関わる人々を対象としています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ROS 2を使ったロボット開発の可能性を探り、製品開発につなげたい読者にとって有用な情報源となるでしょう。
読者がROS 2の理解を深め、革新的なロボットアプリケーションの開発に取り組むきっかけになるような書籍となることを目指します。
〈弱いロボット〉から考える 人・社会・生きること
書籍情報
ロボット=完全無欠な存在、とイメージする人は多いでしょう。
本書に登場するロボットはどれも弱みや苦手を持ち、それゆえ周囲の助けをかりて初めてコトを成し遂げます。
弱さを補いあい、相手の強さを引き出す〈弱いロボット〉は、なぜ必要とされるのか。生きることや他者との関係性、社会の在り方と共に考えます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
くらしをたすけるロボットたち (ここがすごい! ロボット図鑑 2)
書籍情報
光村図書令和6年度版小学2年生の国語教科書で取り上げられる「ロボット」の調べ学習に完全対応!
低学年の児童にも使いやすいように、「ここがすごい!」ポイントをおさえ、ロボットの特徴をわかりやすく説明しています。
QRコードや授業で配布するためのまとめシート等、付録も充実。
厳選された写真で最新ロボットを多数収録!2巻では、掃除から介護、音楽制作など、身の回りのことを中心としたロボットを収録しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ロングセラー)ロボットの本
ロボットがわかる本のロングセラーを、9冊、紹介します。
実践 ロボット制御 基礎から動力学まで
書籍情報
ロボットを自分の思ったように動かす―制御するためには、われわれは何を知ればよいのか?
本書は、ロボット制御の知識を体系的に解説するものです。
ロボット制御に関する従来型の教科書は、ロボットの運動学や動力学を数学的に一般化する、理論的な側面が強いものが主流でした。
制御工学や機械力学に基づく一ジャンルとしてのロボット工学があり、その視点からロボット制御を解説していたとも言えます。ところで近年では、ロボット工学(ロボティクス)はほかの分野から独立して、一つの学問・技術分野として十分に形成されています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
そのため、制御工学や機械力学の知識を取り込みながらも、ロボティクスとして包括的・実践的な教科書・参考書が望まれています。
ロボットを実際に制御するための、情報を提供する教科書です。
未来につながる! ロボットの技術 歴史からしくみ、人工知能との関係までよくわかる
書籍情報
ロボットの技術は日々進歩を遂げ、産業界の分野でも幅広く採用されており、現在の子どもたちが大人になるころには、より目覚ましい発展を遂げていることが予想されます。
本書では、ロボットのなりたちから、現在各方面で活躍するロボット技術の紹介、そして今後の発展について、写真や図版を大きく配した誌面で解説。
どういった種類のロボットがどんなところで働いているのか、産業用ロボット、サービスロボットとはなにか? など、一般的なロボットの知識を網羅。
amazon.co.jp書籍情報より引用
そしてロボット技術の発展によって、未来はどうなる?といった点まで、順序だててわかりやすく解説します。
Raspberry Piでロボット製作 コミュニケーションロボットSIROの製作日誌
書籍情報
家族と一緒に暮らすコミュニケーションロボットを作ってみたい。
「自律移動」「音声認識」「顔認識」、それから「発話」機能を付けてみようか。
ということで、あれこれ機能を組み込んで完成したのがSIROです。本書のロボット製作には、Raspberry Pi、電子工作、Python、コンピュータ、Linux、HTMLなどの幅広い知識が必要となりますが、一つ一つの難易度はそれほど高くありません。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ですのでまだ自信のない初学者の方も、ぜひロボット製作にチャレンジしてください。
産業用ロボット The ビギニング
書籍情報
制御面を中心に初心者(ビギナー)のために機械の仕組みと構成、設計手法などを紹介する「ビギニングシリーズ」最新作。
「ざっと読んで概要を把握したい」という初心者が「産業用ロボット」という専門分野を理解するための入門書。
専門知識が足りない読者が、手っ取り早く最低限の知識を得られるように、その仕組みと種類、構成要素から関連の法律や規則なども含めて、知らなければいけない大事な部分をピックアップして紹介している。
amazon.co.jp書籍情報より引用
豊富なイラストで楽しく読めて、しっかり理解できる。
評判・口コミ
ロボットの確率・統計 製作・競技・知能研究で役立つ考え方と計算法
書籍情報
ロボットの開発・研究は、この世の複雑さとの戦いです。
ロボット自身が壊れないように組み上げるのも大変ですし、ロボットを歩かせようとすると、普段平らだと思っていた地面に実は起伏があることに気づきます。
またカメラには無数のものが映り、しかも映り方には無限にバリエーションがあります。
そんなわけのわからないところで複雑な機械を動かそうというのですから、ロボティクスというのは因果な学問です。どうかしています。ここ四半世紀、この難問の解決に一役買ってきたのが確率論や統計学です、と言ったら皆さんは「本当か?」と思うかもしれません。
しかしこれは紛れもない事実で、最初の頃は動きやカメラでの観測の乱れの起こり方を確率で考えて対策する方法が考案され、今も活用されています。
そして現在は、ロボットが大量のデータから、統計的な法則性を見つけて何かを認識、判断するという段階まできています。
これは、実は動物や人間もやっていることで、確率・統計という道具を得て、ロボットが動物に近づいてきたと解釈することもできるでしょう。また、もっと手前の段階の話として、ロボットに限らず何か実験をしたら、結果を統計処理することになりますし、結果を適切に人に説明しないといけません。
さらには、「ロボットが動かない、壊れる」という偶発的な現象についても「運が悪い」で済ませず、統計を使って分析して対処しなければなりません。
このややこしい世界に立ち向かうには、確率・統計の考え方は、ロボットの作り手にも、ロボット自身にも役に立ちます。ということで、手前味噌も甚だしいですが、本書はロボットを扱う上で知ると役に立つ確率・統計について、基礎から哲学のような話題まで、ひととおり扱ったものです。
内容については、大学1年生が最初の方を読んで確率・統計の基礎を確認できるようにしてあります。
中盤からは読者対象に縛りを設けず、遠慮なく高度な内容を記述してあります。
ただ、その内容については理解する必要はなく、「ロボティクスにはそういう難しい問題があるんだ」と確認してもらい、勉強する動機を持ってもらえるようにしました。
数ヶ月ごと、数年ごとに読み返して、どれだけ自身の理解が進んでいるのか確認したり、随所に仕込まれている雑談だけ読んだりという使い方も考えられます。余談ですが、雑談では動物、人間、人生、そして筆者のギャンブル遍歴、ズルと嘘、手抜きと偏見に満ちた思考の告白など、学術書としてはどうかしている話題を盛り込みました。真面目な方も、不真面目な方も、ぜひ手にとってみてください。
amazon.co.jp書籍情報より引用
UnityとROS 2で実践するロボットプログラミング ロボットUI/UXの拡張
書籍情報
【はじめに】※一部抜粋
本書はUnityとROS を組み合わせて新たな体験を作り出す実践的な入門書として書かれました。シミュレーター上のロボットではなく実機のロボットを使い、ゲームエンジンであり可視化ツールでありXR を作るための開発環境であるUnity とロボットを組み合わせた実践的なサンプルを紹介していきます。
対象とする読者
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書は主に次のような方を対象にしています。
• Unity の開発経験がありロボットの制御に興味のある方
• ROS の開発経験がありUnity を使った操作インターフェースの作成やデータの可視化に興味がある方
• Unity やROS の開発経験はないがロボットを操作するインターフェースの開発に興味のある方
ロボット法 AIとヒトの共生にむけて 増補第2版
書籍情報
生成AIやBMIなど最新トピックをフォローした最新版!
人工知能(AI)技術の急速な発展に伴い、AI搭載ロボットとの共生も夢物語ではなくなってきた今日。
しかし、私たちの社会はその準備ができているでしょうか。
自律的に思考・判断し、行動するロボットが、事故を起こしたら? ヒトを傷つけたら? 「感情」を持ったら?――
高度なAIを搭載したロボットの登場は、法など人間社会のルールにも大きな影響を与える可能性があります。
本書は、「制御不可能性」と「不透明性」を軸に、優れたSF作品の教訓にも触れつつ、「ロボット法」を構想していくことの重要性を伝えます。この増補第2版では、「AI法」が承認されたEUをはじめとするグローバルレベルの議論を踏まえたうえで、採用活動など雇用におけるAI利活用、ChatGPT等の生成AIの問題と規制、メタバース、ブレイン・マシーン・インターフェース、医療分野と司法分野におけるAI利活用などについて加筆。
amazon.co.jp書籍情報より引用
AIガバナンスを考えるための鍵は、ロボット法にあります。
出版社ポスト
産業用ロボット全史 自動化の発展から見る要素技術と生産システムの変遷
書籍情報
・今こそ学ぼう、産業用ロボットの歴史
・これ一冊でロボットの進化過程と今後が全部わかる!日本は産業用ロボット生産台数で、世界シェアの半分を占めています。
一大産業となった産業用ロボットはどんな技術に支えられ、どのような変化を遂げるのか。
amazon.co.jp書籍情報より引用
長年、産業用ロボットの現場にいた著者がロボットの要素技術から自動化までを解説します。
ROSロボットで学ぶ 次世代のIoTアーキテクチャ
書籍情報
本書は、あえて薄く広くなることを厭わずに、ROSを用いたロボットに関する事柄の全貌を描き出すことを目的としている。
ROS自体だけでなく、ハードウェアやロボットを用いたビジネス企画についても触れ、全体が一つの技術物語になるようにまとめてあります。
これによって、大学講義、企業研修等で、今後の活動の基礎となる全体像を提供します。さらに、以下の3つの観点から視点をまとめ、ロボット技術に関して今後取り組むべき目標を提示しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
・ ロボットに基づくAI研究
・ ロボットを支えるフォグコンピューティングを含むシステムアーキテクチャ
・ ロボット技術動向に基づくビジネス戦略
評判・口コミ
ロボットによくある質問と回答
ロボットについて、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
ロボットとは何ですか?
回答: ロボットは、プログラムされた命令に従って動作する機械です。
自動的にタスクを実行するために設計されており、工業用ロボット、サービスロボット、探査用ロボットなど、さまざまな形態と用途があります。
ロボットの主な用途は何ですか?
回答: ロボットは工業、医療、家庭、教育、軍事など多岐にわたる分野で使用されています。
例えば、製造業では組み立てラインの作業、医療分野では手術支援、家庭では掃除や芝刈りなどの日常的な作業を自動化するために活用されています。
ロボットはどのように動作しますか?
回答: ロボットはセンサーで環境の情報を感知し、そのデータをプロセッサが解析して、モーターやアクチュエータを制御することで具体的な動作を行います。
プログラムによっては、人間の指示に従うことも、完全に自動で動作することもあります。
AI(人工知能)とロボットの違いは何ですか?
回答: AIは、学習や推論などの知的な行動をコンピュータで模倣する技術です。
一方、ロボットは物理的な作業を自動で行う機械です。
多くのロボットがAI技術を組み込んでいますが、すべてのロボットがAIを必要とするわけではありません。
ロボットの未来にはどのような展望がありますか?
回答: ロボット技術は急速に進化しており、将来的にはさらに多くの職場や家庭での普及が見込まれています。
特に、自動運転車、介護ロボット、災害救助ロボットなど、人間の安全や生活の質を向上させる分野での発展が期待されています。
また、AIとの統合により、よりスマートで自律的なロボットが開発されるでしょう。
ロボットのスキルが活かせる職種とは?
ロボットに関する知識や経験を習得することによって、さまざまな技術職や管理職で活躍することができます。
ロボット工学の専門知識は、製造業、医療、サービス、研究開発など、多くの分野で重要な役割を果たします。
以下は、ロボットに関する知識や経験を活かして担当できる具体的な仕事の例です:
- ロボットエンジニア:
- ロボットの設計、開発、製造、テストを行います。機械設計、電子工学、制御システム、ソフトウェア開発など、多岐にわたる技術を統合します。
- 制御システムエンジニア:
- ロボットの運動制御や自律制御システムを設計・開発します。制御アルゴリズムを作成し、ロボットの精密な動作を実現します。
- ロボティクス研究者:
- 大学や研究機関でロボティクスの新しい技術や応用方法を研究します。新しいロボット技術やアルゴリズムの開発、論文の執筆、学会での発表を行います。
- ソフトウェアエンジニア(ロボティクス):
- ロボットの制御ソフトウェアや人工知能(AI)を開発します。ロボットの動作計画、画像認識、音声認識などのソフトウェア開発に携わります。
- フィールドサービスエンジニア:
- ロボットシステムの設置、メンテナンス、修理を担当します。顧客先でのトラブルシューティングや技術サポートを提供します。
- プロジェクトマネージャー(ロボティクス):
- ロボット開発プロジェクトの計画、実行、監督を行います。プロジェクトの進捗管理、予算管理、チームの調整などを担当します。
- 産業用ロボットエンジニア:
- 製造業において、産業用ロボットの導入、プログラミング、最適化を行います。自動化システムの設計と実装を担当します。
- 医療用ロボットエンジニア:
- 医療分野で使用されるロボットの開発と改良を行います。手術支援ロボット、リハビリテーションロボットなどの設計と開発に携わります。
- ロボティクス教育者/トレーナー:
- 大学や専門学校でロボティクスの教育を行います。次世代のロボットエンジニアを育成し、理論と実践の両方を教えます。
- エンターテイメントロボットデザイナー:
- エンターテイメント分野で使用されるロボットの設計と開発を行います。アミューズメントパークのロボットや家庭用エンターテイメントロボットの開発に携わります。
- 自動運転車開発エンジニア:
- 自動運転技術の開発に携わり、ロボティクス技術を車両に応用します。センサー技術、制御アルゴリズム、AIを統合したシステムの開発を行います。
- ドローン開発エンジニア:
- 無人航空機(ドローン)の設計、開発、運用を担当します。空撮、配送、農業、災害救助など、さまざまな応用分野で活躍します。
- 人事担当者(ロボティクス企業):
- ロボティクス企業の人材採用、育成、組織運営を担当します。技術者の採用や研修プログラムの開発を行います。
- スタートアップ創業者:
- ロボティクス分野での起業を目指し、新しいロボット製品やサービスを開発・提供します。市場分析、資金調達、製品開発を担当します。
ロボティクスの知識と経験は、技術の進化と共に需要が高まっている分野です。
このスキルを活かして、さまざまな産業や応用分野で革新的な技術開発や問題解決に貢献することができます。
まとめ
ロボットについて知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、ロボットがわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。