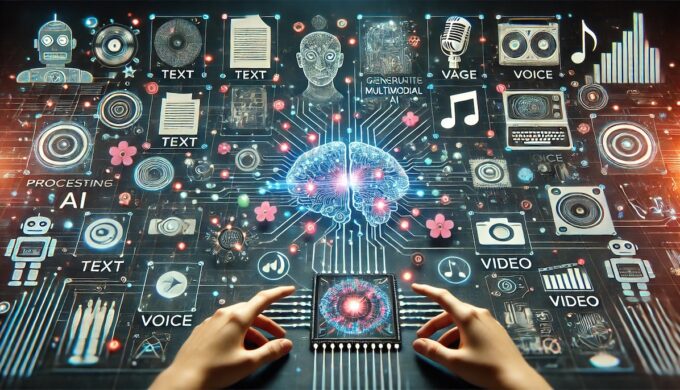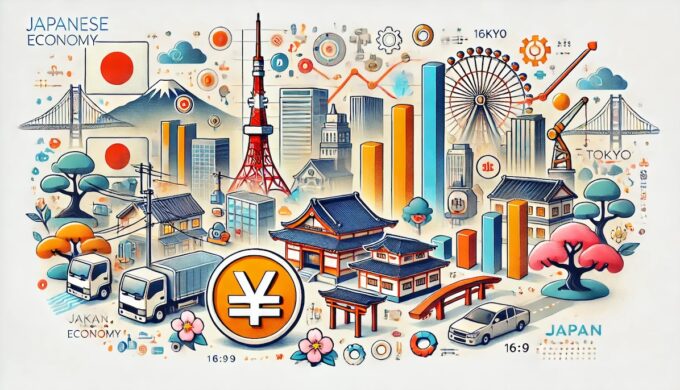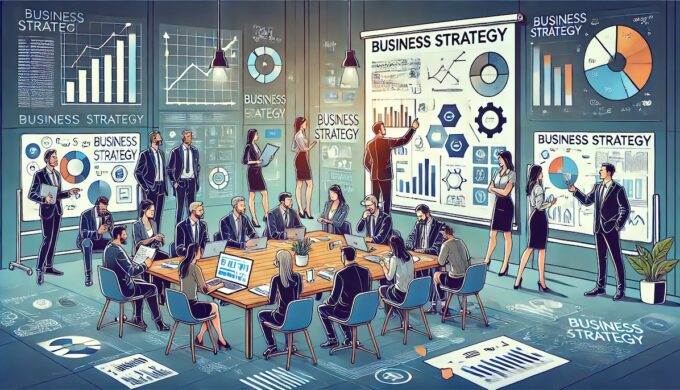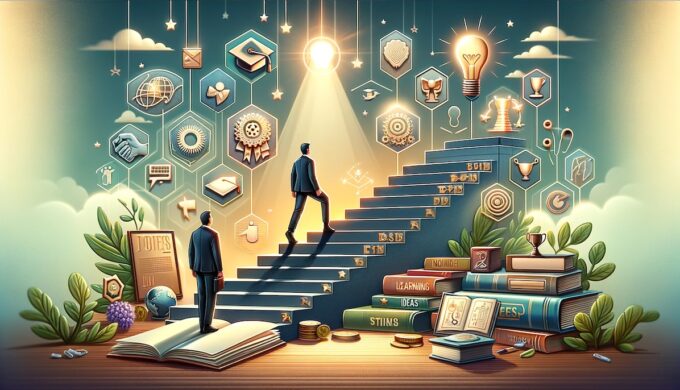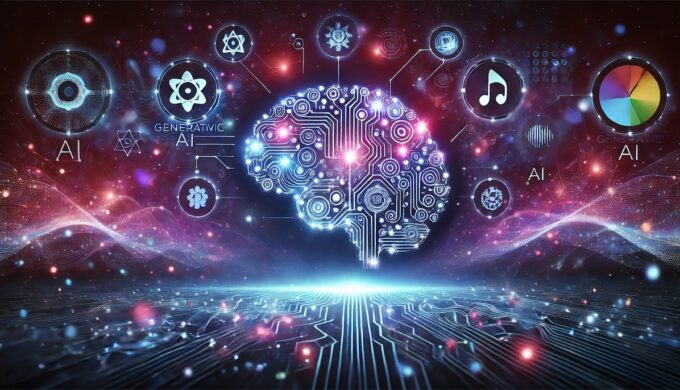リスキリングについて知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
リスキリングとは、変化する職業環境に適応するために新しいスキルを学ぶプロセスです。テクノロジーや市場の進化によって従来の職がなくなる中で、個人が新たなキャリア機会を追求し、雇用可能性を高めるために必要とされます。リスキリングは、継続的な学習と個人の成長を促し、未来の職業に対応する能力を構築します。
まずはじめに、リスキリングがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 従業員や個人:キャリアの変革や新しいスキル習得に興味がある
- 人事部門や組織開発担当者:従業員のスキルアップとキャリアの再設計を支援したい
- 経営者やビジネスリーダー:技術革新に対応し、組織の適応能力を高めたい
- 教育者やトレーナー:労働市場の変化に合わせた教育プログラムを提供したい
- キャリアコンサルタント:個人のキャリア再設計とスキル開発をサポートしたい
- 政策立案者:労働市場の持続可能性と労働者のスキル適合性を高める政策を考えている
- 研究者:労働市場の動向とリスキリングの影響を分析している
- キャリア転職を考えている人:異なる業界や職種への転職を目指している
- ビジネススクールの学生:将来のキャリアに備えたスキルセットを身につけたい
- テクノロジーの進化により影響を受ける業界の従業員:新しい技術トレンドに対応するための知識を得たい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!
最大50%OFF 7月24日(木)まで
Kindle本(電子書籍)準新作本セール
いますぐチェックする
おすすめ5選)リスキリングの本
リスキリングがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング
書籍情報
リスキリングとは、「新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、そして新しい業務や職業に就くこと」で、主に企業の人材戦略の一環として言われる。
今まではこうしたことは新規社員の採用で行ってきたが、近年日本でもリスキリングの重要性が叫ばれ、国や企業でもリスキリングの流れや取り組みが始まっている。
こうした背景のなかで注目されているのが「個人のリスキリング」だ。
とくに近年はDXに関するリスキリングの重要性が注目されている。
本書は、現在注目されている「リスキリング」がわかる&実践できる本。
これからリスキリングを実践しようとしている人だけでなく、リスキリングという言葉の意味やこれからのビジネストレンドを知りたい人、ならびにリスキリングを自社に導入したいと考えている企業担当者にも役立つ一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
新しいスキルで自分の未来を創る リスキリング 【実践編】
書籍情報
リスキリングとは「新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、そして新しい業務や職業に就くこと」であり、重要性が叫ばれつつあったが、岸田総理の所信表明演説以降、国や自治体、企業などで具体的なリスキリングの流れや取り組みが始まっている。
こうした背景のなかで注目されているのが「個人のリスキリング」だ。
リスキリングは、本来は企業などが従業員(個人)に対して提供するものであるが、現実的にこれに対応できる企業は少ない一方で、労働移動はまったなしの状況になっている。本書は、現在注目されている「リスキリング」が実践できるようになる一冊。
amazon.co.jp書籍情報より引用
これからリスキリングを実践しようとしている人だけでなく、リスキリングの意味やこれからのビジネストレンドを知りたい人にも役立つ一冊です。
評判・口コミ
リスキリングは経営課題~日本企業の「学びとキャリア」考
書籍情報
「リスキリング」とはひらたく言えば、業務上の技術や専門スキルを新しく獲得すること、そしてそれを企業が従業員に促進することである。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とあわせて普及しつつあるこの言葉は、「生涯学習」「リカレント教育」などと同じく、広く大人の「学び直し」と捉えられる。
しかし、残念ながら日本の社会人のほとんどは、学びへの意欲が極めて低い。
統計データからも、大人が世界一学ばない国であることが明白だ。
これは決して個人の「やる気」不足のせいではなく、日本企業の働き方やキャリアの「仕組み」に起因する。
大人の「学びの貧困」を解消するために必要な構造改革とは何か。
幅広い調査データや学術知見を基に、日本企業がリスキリングを通じて生まれ変わる方法を提言する。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
リスキリング超入門 DXより重要なビジネスパーソンの「戦略的学び直し」
書籍情報
「日本人よ学ぶか?沈むか? 学び続ける人が生き残る時代のバイブル」
メンタリストDaiGo推薦!
習得スキルを絞り込めば、「キャリアの選択肢」が広がる!
ライフシフト専門家と国際金融のプロが総力提言。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手にいれる
書籍情報
40代でクビを3回経験し、書類選考や面接で落とされた数は100社以上、そんな現実をリスキリングで打破!
amazon.co.jp書籍情報より引用
自らも40歳を過ぎてから取り組んだ実践者でもあるリスキリングの第一人者が、中高年が直面するリアルな課題に応えます。
AIによる自動化、デジタル人材不足、70歳までの継続雇用など、中高年をとりまく労働環境の変化が厳しさを増しています。
特に影響が大きいのが、ヘルスケア、金融、会計、法務等、様々な業界や職業に特化した生成AIサービスの誕生です。
人間の労働が代替される「技術的失業」が起きる未来に備え、将来の選択肢を増やすために、何をどう変えていけばよいのか。
著者の実体験なども紹介しながら、より長く働き続けるために今なすべきことを解説します。
注目の新刊)リスキリングの本
リスキリングがわかる本の注目の新刊を、1冊、紹介します。
今からでも遅くない デジタル・リスキリング入門
書籍情報
「デジタルの壁」を超えて、武器にする!
amazon.co.jp書籍情報より引用
新しいテクノロジーを駆使して「求められる人材」であり続けるために。
キャリアの可能性を広げ、未来を拓くための着実なステップを分かりやすく解説。
本書は、人材育成を手掛ける会社の代表とデジタル人材育成学会の会長が、「そもそも、なぜDXが必要なのか」「学び直しと言われても、何をどう学べばよいのか分からない」と悩むビジネスパーソンに、DXの初歩やリスキリングの足がかりを解説するものです。
現在、国や企業は変化を続ける環境に対応するため、知識やスキルを学び直す「リスキリング」を推奨していいます。具体的には、国が勧める「Di-Lite(ディーライト)」と呼ばれる3つの基礎的な資格にはじまり、AIやデータ分析、クラウド、セキュリティなど、その分野は多岐にわたります。それらを統合的に「求められるスキル」として、ガイドブック的に分かりやすく解説します。
著者は「『DXに対応する基礎的な学び方を詳しく知りたい』という声は多い。効果的な勉強法のコツも含めて、初心者向けのガイドとなるような書籍がなく、またインターネットで調べても、横文字の専門用語が並び、意味が分からず戸惑う方も少なくない」と指摘しています。本書では、リスキリングの基礎的な情報に加えて、企業や地方、学校でのDX関連事例や政府の動向についても紹介。リスキリングの始め方からその効果まで、具体的にイメージできるようになります。
随所に用語解説も添えられ、ITなどの専門知識がなくても簡単に理解できる内容・構成で、デジタルスキル習得に意識のあるビジネスパーソンにとって、示唆に富む一冊です。
ロングセラー)リスキリングの本
リスキリングがわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
東大教授がゆるっと教える 独学リスキリング入門
書籍情報
「本書で皆さんにお伝えしたいのは、いくつになっても、どんな状況になっても、新しい扉を開くための方法です」。著者は、独学ブームの元祖・柳川教授。『独学という道もある』に、いま注目のリスキリング(学び直し)論を増補した決定版。年齢、世代を問わず一生モノの本質だけを集めました。
会社や世間から嫌々やらされるのではなく、自分で自分の新しい可能性を切り開くために学ぶこと。それは自分の未来をマネジメントすることにもつながります。
そして独学のコツの一つは、頑張りすぎないこと。三日坊主に終わった自分にがっかりしてムリだなんて決めつけはもったいありません。「ふまじめ」なほうがいいのです。
異色のキャリア(大検→慶應通信部→東大院)を歩んだ著者ならではの「非常識」な学びのすすめ。
amazon.co.jp書籍情報より引用
マネジメントのリスキリング ジョブ・アサインメント技法を習得し、他者を通じて業績を上げる
書籍情報
働く人々や働き方の多様化、「人的資本経営」への関心の高まりなどを受けて、日本企業は今、従来のマネジメントのあり方を大きく変革する必要に迫られています。
また、そのために、マネジャーのマネジメントスキルの再開発・再教育が喫緊の課題となっています。マネジメントの役割は、「他者を通じて業績を上げる」ことです。
本書は、マネジメントの基本技術である32の「ジョブ・アサインメント」(日常のマネジメント行動)の解説を中核に、マネジメントのポイントをテーマ別に整理し、ジョブ・アサインメントの各項目とつないで詳しく説明しています。マネジメント研修のサブテキストとして、また多面観察評価後の内省機会における思考の整理におすすめの一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
リスキリング大全 キャリアの選択肢が増えて人生の可能性が広がる
書籍情報
今より収入を上げたい! キャリアアップしたい! 転職? 副業? 資格取得? セミナー受講?
でもなかなか最初の一歩が踏み出せない……
・そもそも何をどう身につけたらいいか分からない
・スキルは身についた気がするが、なぜか成果につながらない
・身につけたスキルがちゃんと使えるか自信がない
・学んだことを仕事に結びつけられるイメージが湧かない話題の「リスキリング」でキャリアの選択肢も人生の可能性も広がる!
リスキリング=新たな仕事のために、新しいことを学び、新しいスキルを身に付けることリスキリングの必勝法が分かれば、稼ぐ力はどんどん加速する!
・仕事と学びが両立できる!
・使える知識・スキルが身につく!
・自己効力感が高まる!
・環境の変化に順応できる!3万人以上を指導したリスキリングのプロ直伝!
amazon.co.jp書籍情報より引用
最短でリスキリングが成功する59の鉄則がこの1冊に!
評判・口コミ
リスキリングが最強チームをつくる 組織をアップデートし続けるDX人材育成のすべて
書籍情報
管理職・マネジャー、必読!
組織・チームのためのリスキリングがこれ1冊ですべてわかる!
組織をアップデートし続ける DX人材育成のすべて
本書は、大手自動車メーカーや商社グループなど、多くの企業のリスキリングを支援してきた法人向けリスキリング支援サービス「Reskilling Camp(リスキリングキャンプ)」のメソッドをまとめた一冊。「リスキリングといっても何をどうすればいいか分からない」
「DX人材を育てたいが、メンバーの変化を促すことが難しい」
「eラーニングを導入したが、学習が継続しない」
「通常業務で手がいっぱいで、デジタル活用へ時間を割けない」
そういった組織のリスキリングの課題を解決し、成果を最大化するためのリスキリングのメソッドを公開しています。■リスキリングのスタートから成功までが実感できる事例を豊富に掲載
本書では、実際の事例はもちろん、リスキリングのスタートから成功までを実感できるように、実際の多くの企業で起こりうる状況や、立ちはだかる課題、日々の取り組み方をリアルに描写し、ストーリーとともに学べる構成となっています。本書で紹介するチームリーダーの苦悩、日々の行動、成功を追体験しながら、組織を変えていく「リスキリング」を学んでいきましょう。
amazon.co.jp書籍情報より引用
人的資本を高める日本企業のリスキリング戦略
書籍情報
組織を成長・進化させる仕組みと仕掛け「リスキリング→転職ではない」
組織に「学び続け続ける文化」を植えつけ、全社員のエンゲージメントを高める!本書は、「リスキリング」を「技術革新やビジネスモデルの変化を背景に、社員にこれまでとは異なる業務を行うスキルを獲得させる企業の生き残りの手段」と定義する。
つまり、リスキリングの主体は、個人ではなく会社が主体となると説く。会社が、社員に学ぶ楽しさを実感させていくことで、「学びが組織の文化」となる。
amazon.co.jp書籍情報より引用
学び、貢献することで社員が幸せを感じるウェルビーイングな会社をつくることが、これからの日本企業が生き残る手段である。
リスキリングという人材投資は人的資本経営を実現するための重要な戦略的要素だ。
逆転のリスキリングとサードエイジの時代
書籍情報
★そのリスキリングは未来を変えてくれますか?
amazon.co.jp書籍情報より引用
★AI時代、企業に新たな価値をもたらすスキルとは
本書のテーマはビジネスパーソンの「リスキリング」にありますが、それは手段の一つであり、著者の思いはタイトルにある「逆転」に込められています。
「逆転」には3つの意味があります。
1つ目は、「失われた30年」といわれ、負け続けている日本経済を「逆転」させる意味です。本書の前半は時代を読み解くことにページを割き、未来に向けてどのような考え方をしていけばよいのか、著者の分析が冴えています。AIをはじめとするテクノロジーが時代を変えていくといわれていますが、実は変化は人の側にも起きていて、その変化をつかむことで、未来への一手が見えてくるというのです。
(中略)
2つ目の「逆転」はHR部門目線で、成熟世代は扱いづらいと認識していたが、実は、AI時代に新たな価値をもたらす人々であるという意味です。3つ目は当の成熟世代目線で、本書に書いていることに目を向けてもらえれば、失いかけた自信を取り戻し、将来に向けて明るい道を切り開けるという意味になります。
本書の想定読者は3つの「逆転」の当事者、つまり、経営者、HR部門、成熟世代です。日本社会が置かれている現状を直視すれば、これまでにない新たな考え方が必要です。人口減少社会で自社の未来を悲観しているなら、一度、著者の考え方に触れてほしい。本書では考え方だけでなく、そのための方法論として、AI時代に必要とされる「メタスキル」の習得方法についても具体的に解説しています。
時代の変曲点にいる今、経営者、HR部門、成熟世代にとって、検討する価値のある一つの考え方がここに提示されたのではないかと思います。
オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング
書籍情報
近年、注目を集めるようになったリスキリング。人生100年時代が到来した今、学び直しの必要性はますます高まっています。ただ、そうはいっても、「何をすればいいのかわからない」「自分なりに取り組み始めてみたものの、学んだことを活かす場がなく、なかなか長続きしない」という方も多いのではないでしょうか。「何かやらなければ」と思いつつも、なかなか踏み出せないという方も少なくないでしょう。
そんな方におすすめしたいのが「地方副業リスキリング」です。「地方副業」とは、主に首都圏で働くビジネスパーソンが、地方の中小企業やNPOなどにおいて、「オンラインでリモート中心の副業」をすることです。また「プロボノ」とは、本業のスキルや経験を活かして取り組む社会貢献活動のことです。
副業と聞くと、一瞬小遣い稼ぎのようなイメージを持たれるかもしれませんが、地方副業やプロボノで取り組む仕事は、マーケティング戦略の立案・実行やIT環境の整備、人事制度の構築といった、もっと専門的な仕事です。地方の企業やNPOは何らかの地域課題や社会課題の解決を目指していることが多く、その解決に実地で携われるという魅力があります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書は、この地方副業・プロボノを通じて学び直しをするという、新しいリスキリングの形を提案するものです。
デジタルリスキリング入門――時代を超えて学び続けるための戦略と実践
書籍情報
学ぶこと、学んだスキルを仕事に活かすことが楽しくなる本!
amazon.co.jp書籍情報より引用
将来どうなるかわからない変化の激しい世の中、そこで自分という軸をしっかり保ち、変化に対応できるようスキルを意図的に獲得しておく取り組みがリスキリングです。
ここ30年間の、特にデジタル領域での変化は私たちの仕事に大きな影響を与え続けてきました。人生100年時代と言われていますが、仕事=働く時間はその人生の多くを占めています。多くの時間を占める仕事だからこそ、そこに心理的成功、すなわち幸せを感じられる状態をつくることは重要です。
「働くことで心理的成功を収められる状態をつくること、またそれを維持するために、スキルをアップデートし続ける力」それがリスキリング力です。それは組織から命令されて身につくものではなく、個人の「自分らしさ」「ありたい姿」に添って実現されるものです。
本書では、筆者自身の経験を軸に、自らが主宰するコミュニティ「ノンプログラマーのスキルアップ研究会」などでの実績、また学習に関するいくつかの研究を参照しつつ、ビジネスパーソンがリスキリングを通して成功をおさめるための知識と戦略、実際に行動していくための原則をわかりやすく伝え、自分らしい、ありたい姿になるためのデジタルスキルを身につける術を提供します。
時代の流れに合わせて成長し、価値のある「働く」を実現し続けることができるよう、本書がサポートします。
実践リスキリング DXを成功に導く人材を育成する
書籍情報
DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むほとんどの企業が直面するのがデジタル人材、DX人材の不足だ。
優秀な人材は引っ張りだこの状況で、外部からの採用は非常に難しい。
今、企業がDXを成功させるために必要なのは内部の人材を再教育し、DX人材とすること。リスキリングが強く求められている。
ただデジタル技術によって企業を変革させるDX人材のリスキリングは、デジタルやIT技術を教えればいいというものではない。
変革の道筋を可能にする「ビジネスの仕掛け」を学ぶことがDXを成功させるリスキリングの最も重要な一歩になる。本書は、住友生命でDX推進に関わる筆者が、DXを成功させる17種類の「ビジネスの仕掛け」に加え、DXのビジネス企画のケーススタディー、リスキリングの対象人材と内容、方法と研修事例、リスキリングを成功させる「9つの学びの仕掛け」までを解説する。
amazon.co.jp書籍情報より引用
DXを進め、DX人材不足を解消するために必読の1冊。
子育てリスキリング奮闘記 休職サラリーマン、二児を抱えて教育系大学院で学ぶ
書籍情報
育休中にリスキリングと言うけれど……
大学院生と2児の子育ての両立は、超・激務!!子ども向け新聞社を休職し、幼子を抱え、教育系大学院へ進学した著者が貴重な体験を縦横無尽に語る
amazon.co.jp書籍情報より引用
リスキリングによくある質問と回答
リスキリングについて、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
リスキリングとは何ですか?
回答: リスキリングは、個人が現在の職業や業務に必要なスキルセットを変更またはアップグレードするプロセスを指します。
これは特に、技術革新や産業の変化によって従来の職業が陳腐化する状況下で重要になります。
リスキリングを通じて、個人は新しい職業に適応したり、現在の職場でより高度な役割を担うためのスキルを習得したりします。
リスキリングとアップスキリングの違いは何ですか?
回答: リスキリングとアップスキリングは似ているが、焦点が異なります。
リスキリングは、新しい職種や異なる業務分野に移行するためのスキルを身につけることです。
一方、アップスキリングは、現在の職業内でのスキルセットを強化または拡張することを指します。
アップスキリングは、同じ職種内での進歩や効率化を目指すのに対し、リスキリングは職業の変更やキャリアパスの変更に重点を置きます。
リスキリングが必要とされる理由は何ですか?
回答: リスキリングが必要とされる主な理由は、技術進歩と産業の変化です。
自動化、人工知能、デジタル化などの技術的進歩により、多くの従来の職業が変化または消滅する可能性があります。
リスキリングを通じて、労働者はこれらの変化に適応し、新しい職業機会を探求することができます。
また、経済の変化に対応し、持続可能なキャリアを築くためにもリスキリングは重要です。
個人がリスキリングを進めるための方法は何ですか?
回答: 個人がリスキリングを進めるための方法にはいくつかあります:
- オンラインコース: 多くのオンライン教育プラットフォームが、様々なスキル習得のためのコースを提供しています。
- 業界資格: 特定の業界や職種に関連する資格や認証を取得する。
- ワークショップやセミナー: 対面またはオンラインで開催される短期間のトレーニングプログラム。
- メンタリングやネットワーキング: 業界の専門家や同僚からの知識や経験を学ぶ。
- 実践的経験: インターンシップやボランティア活動を通じて、実務経験を積む。
企業は従業員のリスキリングを支援するために何ができますか?
回答: 企業は従業員のリスキリングを支援するために、以下のような取り組みが可能です:
- 研修プログラムの提供: 新しいスキルや技術に関する社内研修やワークショップ。
- 学習支援: オンラインコースや業界認定資格取得のための費用補助。
- キャリア開発計画: 従業員が自分のキャリア目標に合わせてスキルを習得できるよう支援。
- ジョブローテーション: 異なる部門やプロジェクトでの経験を通じて、新しいスキルを習得。
- メンタリングプログラム: 経験豊富な社員がメンターとして、他の社員の学習をサポート。
リスキリングのスキルが活かせる職種とは?
リスキリングに関する知識や経験を習得することで担当できる仕事を10個、紹介します。
- リスキリング戦略コンサルタント
- 企業のデジタル変革に伴う人材スキル要件分析、従業員のスキルギャップ調査、組織全体のリスキリング戦略立案と実行支援を行い、企業の人材変革を推進します。
- 企業研修・人材開発マネージャー
- 社内のスキル転換プログラム設計、学習カリキュラム開発、研修効果測定、個別キャリアパス設計を担当し、従業員の継続的なスキルアップを組織的に支援します。
- オンライン学習プラットフォーム運営者
- EdTechサービスの企画・開発、学習コンテンツ制作、ユーザー体験改善、学習分析システム構築を通じて、効果的なデジタル学習環境を提供します。
- キャリアコーチ・転職アドバイザー
- 個人のスキル棚卸し、市場動向に基づく学習計画策定、転職戦略立案、キャリアチェンジ支援を行い、個々人の職業人生の再設計をサポートします。
- 人事変革・タレントマネジメント専門家
- スキルベース人事制度設計、社内公募制度構築、タレントマッピング、従業員エンゲージメント向上施策を通じて、組織の人材活用最適化を図ります。
- 学習体験デザイナー
- 成人学習理論に基づく教育プログラム設計、マイクロラーニング開発、ゲーミフィケーション活用、学習継続率向上のためのUX/UI設計を専門とします。
- 政府・自治体リスキリング政策担当者
- 国や地方自治体でのリスキリング支援制度設計、職業訓練プログラム企画、産学官連携推進、労働市場政策立案を通じて、社会全体のスキル向上を推進します。
- リスキリング効果測定・分析スペシャリスト
- 学習効果の定量分析、ROI測定、データドリブンな改善提案、学習アナリティクス活用を通じて、リスキリングプログラムの継続的改善を実現します。
- 業界特化型スキル研修講師
- IT、DX、グリーンエネルギー、ヘルスケアなど特定業界の専門スキル研修を提供し、業界動向と実務経験を活かした実践的な教育サービスを展開します。
- 組織変革・チェンジマネジメント専門家
- リスキリング導入時の組織抵抗の解決、変革推進体制構築、従業員の意識改革支援、組織文化変革を通じて、学習する組織への転換を促進します。
まとめ
リスキリングについて知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、リスキリングがわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下のような記事も紹介しています。