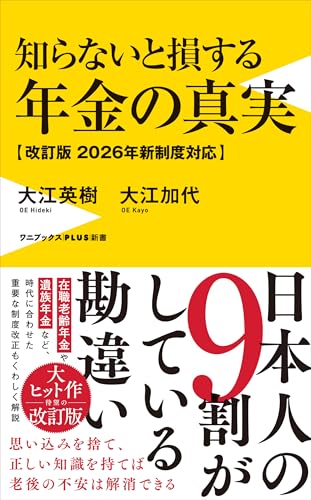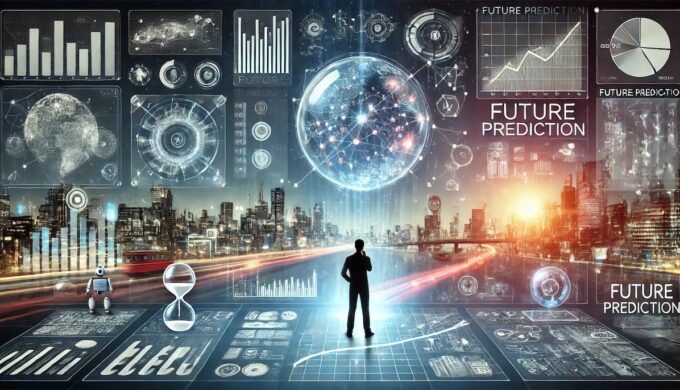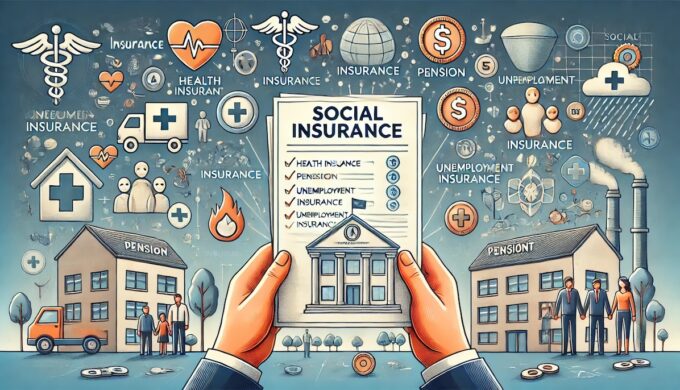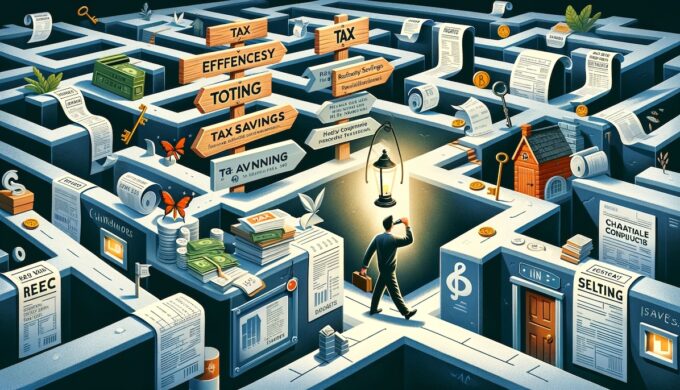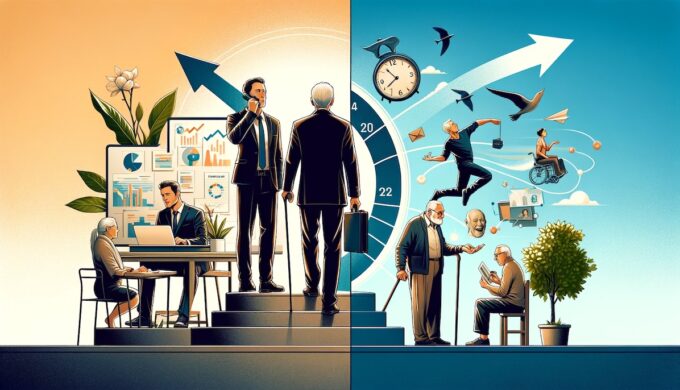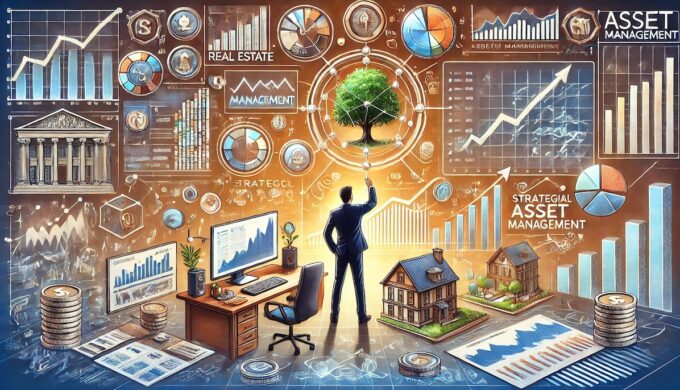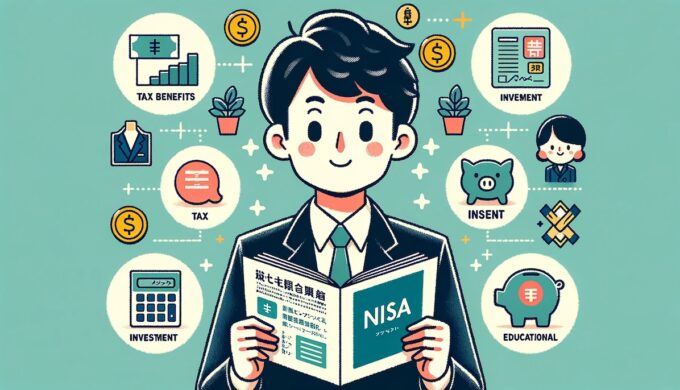年金について知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
年金とは、老後の生活を支えるために、現役時代に積み立てた資金を基に定期的に受け取る給付金のことです。公的年金や企業年金、個人年金などがあり、老後の経済的な安心を提供します。年金制度は、長寿社会において、安定した生活を送るための大切な仕組みです。
まずはじめに、年金がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- リタイアを控えた人:公的年金や企業年金の仕組みを理解し、退職後の生活設計を立てたい
- 中高年層のビジネスパーソン:自分の年金受給額を把握し、退職後に備えた資産形成を検討したい
- 若者・ミレニアル世代:将来の年金制度を理解し、早いうちから老後資金の計画を立てたい
- 自営業者・フリーランス:国民年金や個人年金保険など、自分で年金を準備する必要がある
- 企業の人事・総務担当者:社員の年金制度や退職金制度を管理し、適切な福利厚生を提供したい
- ファイナンシャルプランナー:クライアントに年金や老後の資金計画についてのアドバイスを行うために、専門知識を深めたい
- 退職金や企業年金を管理する担当者:企業年金制度の運用や管理を適切に行うために、年金の制度や法律を理解したい
- 主婦・主夫:家庭の年金受給額を把握し、老後の家計を計画したい
- 社会保障に興味がある人:年金制度の仕組みや改革について理解を深め、将来の社会保障について考えたい
- 学生・研究者:年金制度を学び、将来のキャリアや研究に役立てたい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
紙書籍 まとめ買いキャンペーン
・2〜4冊…2%還元
・5〜9冊…5%還元
・10冊以上…10%還元
詳しく見る 2月12日まで
おすすめ5選)年金の本
年金がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
50代60代のための増やして得する年金の本
書籍情報
ニュースでよく見る年金の話題。なんとなく不安はあるものの、どうしたらいいかわからない人のために、最近の年金制度改正についてより詳しく解説します。さらに、まだ間に合うこれから年金を増やす方法や、少しでも多く年金を受け取る方法なども紹介します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
60分でわかる! 新・年金 超入門
書籍情報
年金の今後と老後のマネー戦略をこの1冊で!
将来あなたは年金だけで暮らしていける?
賢い年金生活をおくるためのヒント、新常識をコンパクトにお届け!
年金制度は、経済の変化、平均寿命の長期化、家族構成やライフスタイルの変化といったことを踏まえ、厚生労働省による財政検証結果をもとに定期的(5年ごと)に改正されます。財政検証とは、5年に一度行われる、年金の健康診断のようなもの。はたして今回の財政検証の結果を受け成立した年金制度改正法により、年金の未来はどうなっていくのでしょうか?本書では、法案の成立を経て、今後の年金制度がどう変わっていくのか、また現在の日本の年金制度の立ち位置やしくみに触れながら、年金を活用したマネー戦略を解説していきます。そして、実は年金を受給しはじめるとわかる「211万円の壁」や、盛んに取りざたされる「年金の繰り下げ」を行うことで生じる諸問題、そこに潜む大きな落とし穴などにも触れていきます。様々なライフスタイルによるシミュレーションを交えながら、年金とそれ以外の老後資金のつくり方などについても紹介します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
年金のてびき 令和7年4月版
書籍情報
◆国民年金と厚生年金の適用と給付のしくみについてわかりやすく解説しています。
◆特に、老齢、障害、遺族の各給付について、詳しくしかもコンパクトに解説した格好の手引書となっています。
◆公的年金制度の基本事項を網羅し、年金額の計算例についても丁寧に解説しています。
◆令和7年度の制度改正、年金額改定についても掲載。年金学習のてびきや年金相談対応の入門書として年金実務ご担当者の皆様にご愛用いただいています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
夫と妻の年金 これなら損しない! 年金相談のプロが教える万全の手続きQ&A大全
書籍情報
\2025年度 年金大改正に対応/
amazon.co.jp書籍情報より引用
年金の落とし穴を回避して、受給額を増やす!
一問一答形式で、わかりづらい年金の疑問を解決!
長い人生の節目には、知らぬまに損する「年金の落とし穴」が無数にあります。
例えば…
◆学生時代や転職時に国民年金保険料の未納があると、年金額は1年未納で年額2万円、5年未納なら年額10万円もの減額に!
◆結婚・中途退職・転職・転居で起こる年金記録の欠落、定年退職後の任意加入、継続雇用後の在職老齢年金で損する人が多い!
◆離婚や妻のパート勤務などで年金の家族手当「40万円加算」をもらえなくなる人が多い!
◆国民年金保険料の未納は定年退職や起業後の任意加入で補え、受給10年で元が取れるが、このチャンスを逃して損する人ばかり!
◆老後だけでなく障害や死亡も保障する3つの公的年金は、受給要件や手続きルールを知らないともらえない!
◆年金をもらうには請求が必要!65歳前支給の特老厚や原則65歳支給の老齢年金のもらい忘れが多いので要注意!
◆年金を早くもらいたい一心で繰上げ受給をすると受給額が大幅に減り、一生後悔することに!
◆繰下げ受給の増額上限84%を狙い、逆に損する人が実に多い!繰下げ請求前に死亡すると増額分は支給されない!
◆配偶者が亡くなると夫婦2人分の年金が1人分に!老後の備えが今すぐ必要!
……など
本書は、こうした年金の落とし穴を回避して受給額を増やす方法を、一問一答形式で図解やマンガを駆使してわかりやすく解説。
これまで年金制度は難しくて理解できなかった人にもオススメです!
年金制度改正の解説 2025年(令和7年)
書籍情報
◆令和7年6月20日に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の解説書です。
◆今回の改正では、公的年金分野において、社会保険の適用拡大や遺族厚生年金の男女差の解消、子どもが受ける遺族基礎年金の給付機会拡大、在職老齢年金制度の支給停止基準額の引き上げ、標準報酬月額の上限の引き上げなどが実施されるほか、私的年金制度では、DB資産運用の見える化やiDeCoの加入可能年齢の引き上げ等も予定されております。
◆本書では、社会保障審議会年金部会の資料を丁寧に読み解きながら、改正条文に基づき、改正に至る背景・経緯から今改正の内容を詳しく解説しています。
◆本文中に改正点の根拠法を記載。年金相談資料としても最適な1冊です。
◆本改正法の新旧対照表は、PDFファイルにまとめ、巻末に記載のURLまたは2次元コードよりダウンロードが可能な仕様にしています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
注目の新刊)年金の本
年金がわかる本の注目の新刊を、1冊、紹介します。
知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】
書籍情報
日本人の多くが勘違いしていた「年金」の真実を明らかにし、大反響を呼んだ新書の改訂版。
新たに法改正の時期を迎えた年金制度の解説など、大幅に加筆修正しました。・年金受給は「繰り上げ」「繰り下げ」どっちが得する?
・65歳以上で働いていても年金は減らない?
・今の現役世代は年金を払うと損するの?
・公的年金は増やすことができる?など、年金制度に何となく疑問を持っている、まもなく定年を迎える、老後のお金で失敗したくないなど、多くの方にとって必読の一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ロングセラー)年金の本
年金がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
図解 いちばん親切な年金の本 25-26年版
書籍情報
■最新の制度改正もバッチリ対応!
amazon.co.jp書籍情報より引用
ややこしい在職老齢年金制度や受給の繰下げ・繰上げのメリットとデメリットも詳しく解説!また、パート・アルバイトで働いている人が年収の壁を気にせずに働き続けるための年収の壁・支援強化パッケージについても解説!さらに、今後の制度変更の見通しも紹介。ライフスタイルを考えて、自分に合った受け取り方を選びましょう!
■巻頭カラーで「年金」の基礎と最新ニュースがまるわかり!
年金の種類、国民年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金、ねんきん定期便、ねんきんネット等の基礎と知っておきたい近年とこれからの年金制度の変更をわかりやすく図解しました。まずは、パパっと年金の基礎を短時間で学びましょう。
■導入マンガがわかりすい!
要所に、概要とポイントがわかるマンガを入れました。何が大切なのか、どのように考え、手続きを行うのかがよくわかります。
■要点がすばやくわかる紙面!
大切な用語やポイントは、色の太文字、色のマーカーで見せています。大切な箇所が、すっきりと頭に入ります。
■「私の年金どうすればいい?」ギモン解消に役立つ特典PDF付き!
3つの特典PDFをダウンロードすることができます。本とあわせて便利に活用してください。
・ゼロから始める年金相談
・社労士への相談ガイド
・最新情報チェックリスト
60歳からの得する! 年金 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本 2025-26年 最新版
書籍情報
2025 年は 5 年に一度の年金法改正が行われる年です。令和 7 年度は、物価の上昇を受けて年金額が前年度から 1.9%引き上げられることが発表されました。また、議論が続いている「パート社員の厚生年金の壁」や、「在職老齢年金の基準上げ」「遺族厚生年金の男女差解消」など、気になる変更点が盛り込まれています。これらの改正を知っているのと知らないのとでは年金受給額に大きな差が!
本誌では、豊富な図版やイラストを使って年金の仕組みと改正をどこよりもやさしく&詳しく解説するほか、「会社員の夫と契約社員の妻」「個人事業主の夫とパートタイマーの妻」「女性のおひとり様」などなど、多様化しているさまざまなライフコースごとの年金受給額を独自にシミュレーションし、公開します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 25-26年版
書籍情報
■親しみやすい巻頭マンガ
amazon.co.jp書籍情報より引用
巻頭「年金くんに聞いてみよう!」では、よくある疑問をマンガで解説。カラー図解で、気になるポイントがすっきりわかります。
会社員、フリーランス、年金受給を目前にした方など、それぞれの立場から、特に詳しくチェックすべき内容を示しているので、知りたいところから読み進めることができます。
■老齢年金を中心に解説
国民全員に関係のある、老齢年金に多くのページを割いて解説しています。
年金制度の改正により、受け取りの自由度が増えています。いつから年金を受け取り、いつまで働き続けるべきか、というのは、多くの方が悩むポイントでしょう。
さまざまなケースの例を挙げ、ベストな選択をサポートします。
■概略が大づかみできる
各章の冒頭には「よくある疑問あれこれ」として、複雑な年金制度を大づかみするまとめのページを設けています。
知っているつもりで、勘違いしていることも多いもの。この見開きを見るだけで、その章の概略が一目でわかります。
■豊富な図解でわかりやすい
全ページにわたり図解を豊富に掲載しています。また、各ページの脚注ではキーワードや補足を解説。
巻末では年金を請求する際に必要な書類の記載例をわかりやすく掲載しています。
改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 年金のしくみと手続きがすっきりわかる本
書籍情報
ロングセラーの入門書が令和五年度に対応して10年ぶりの改訂! 年金生活に関するさまざまな問題にも応えながら、老後の人生設計をサポートします。 本書は、わかりにくい年金の話がスッキリわかる本です。 「ねんきん定期便」のチェックポイントから各種の手続きまで詳細に解説。 会社の総務部・経理部・人事部・労務部ご担当者も必携の内容です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
25訂版 年金相談標準ハンドブック
書籍情報
年金に関する知識を網羅した好評書25訂版。
これまでの年金制度から被用者年金一元化、年金生活者給付金制度、各国との社会保障協定まで、年金のすべてを詳細にわかりやすく解説しています。また、巻頭には、令和7年改正案の主な内容のほか、令和7年度年金額等の数値と情報を反映した資料や、相談業務に役立つ知識が多数盛り込まれています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活
書籍情報
「年金だけじゃ、生活が不安」「65歳で貯金がまったくないんだけど、どうしたらいいですか」こんな悩みをよく聞くようになりました。
「60歳を過ぎた今からでも投資を始めた方がいいんでしょうか?」最近は新NISAなどがブームのせいかこうした話もよく聞きます。
しかし、投資にはどうしてもリスクが伴います。大事なお金がむしろ減ってしまう可能性があるのです(実際に減っている人も多くいます)。また、投資には知識も必要ですし、手続きも面倒です。では、どうすればいいのでしょうか。
その不安に応えるために社会保険労務士でファイナンシャルプランナーで人気YouTuberでもある著者が考案したのがこの本で紹介する「年金最大化生活」です。意外に知られていませんが手間や労力をかけずに「もらえるお金」「増やせるお金」はかなりあるのです。
投資なんてしなくていい、ただ役所に申請すればいいんです。【申請すればもらえるお金の例】
●年金版の家族手当 1年で約40万円
●60歳以降も働くともらえるお金 1年で約36万円
●65歳直前で退職するともらえるお金 約109万円【申請すれば増やせるお金の例】
●65歳前で年金をもらい始めた後で増やせるお金 年6.5万円
●最大限年金を繰り下げて増やせるお金 年126万円【意外と簡単に減らせる支出の例】
●健康保険料 およそ月1万円
●生命保険料 月3.2万円※金額は例です。個人の置かれた状況によって異なります
実は、これだけお金はふやす方法があるのです。
上記の方法は一例で、ほかにもお金を増やす方法は本書にまだまだ、たくさん掲載されています。このように、「もらう」「増やす」「支出を減らす」というやり方を組み合わせれば、投資などのリスキーな手段を用いなくても生活に必要なお金を確保し、少しの余裕もでき旅行をしたり、おいしいものを食べたり楽しく充実した第二の人生を送れます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
「年金最大化生活」をぜひ、試してみてください。
聞くのがこわい年金の話 年金、いくらですか?
書籍情報
◎知らないとこわい!
amazon.co.jp書籍情報より引用
知ってるだけで得する年金の知識が満載!
◎無知が一番こわい!
梅子のアフタートークで、得する、これからの年金生活を指南!
◎この一冊で老後のリアルとお金とのつきあい方が120%わかる!
初めての年金暮らしルポ!
登録者数11万人超え(2025年3月現在)の人気YouTubeチャンネル『梅子の年金トーク!』を、初の書籍化。
「お金がないから今日もアルバイトの面接です」……79歳男性
「年金月2万円、生活保護も断られ」……71歳男性
「会社がブラックで雇用保険かけてなかった」……61歳男性
人には聞けない年金額、年金生活のリアルを、街角の年金受給者20人にインタビュー。
あなたは、老後のお金、どうしてますか?
年金だけで暮らせるの?
お金がないから死ぬまで働き続ける?
これが年金生活の真実。老後とお金のルポルタージュです。
年金制度の理念と構造 より良い社会に向けた課題と将来像
書籍情報
元年金局長が書いた、明日へつなぐ年金制度論
◆少子高齢化が進んでも日本の年金制度が大丈夫な理由とは?
基礎年金加入45年化が実現するとどのように変わるのか?
将来の低年金を防ぐカギは勤労者皆保険の実現にある―◆年金制度の仕組みや考え方、これまでの制度改正の経緯を見やすい図版を多数用いて丁寧に解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
年金制度の基本がわかる、制度改革議論の理解に必携の書。
年金不安の正体
書籍情報
不満につけこみ、不公平を騒ぎ立て、制度が崩壊すると危機感を煽る。
amazon.co.jp書籍情報より引用
不安を利益に変える政治家や評論家、メディアのウソを暴き、問題の本質を明らかにしよう。
いわゆる「老後資金二〇〇〇万円問題」や「マクロ経済スライド」とは何か。消費税と年金の関係は。賦課方式と積立方式はどこがどう違うのか。一部で期待されるベーシック・インカムの現実度は…。国民の不平不満につけこみ、世代間の違いを不公平だと騒ぎ立て、少子高齢化で年金制度が崩壊するなどと危機感を煽る。それらのほとんどは誤解や無理解から起こっているのだが、なかには明らかなフェイクも含まれている。不安を利益に変える政治家や評論家、メディアのウソを暴き、問題の本質を明らかにしよう。
年金によくある質問と回答
年金について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
年金とは何ですか?
回答: 年金は、退職後の収入の一部を補うための公的または私的な支払いシステムです。
通常、労働期間中に支払った保険料に基づいて計算され、定期的に受け取ることができます。
年金制度の種類にはどのようなものがありますか?
回答: 主な年金制度には公的年金と私的年金があります。
公的年金には国民年金や厚生年金が含まれ、私的年金には企業年金や個人年金保険などがあります。
それぞれ支払い条件や受取額が異なります。
国民年金と厚生年金の違いは何ですか?
回答: 国民年金は、すべての国民が加入する基礎的な年金制度で、自営業者やフリーランスも含まれます。
厚生年金は、企業に勤めるサラリーマンや公務員が加入する制度で、国民年金よりも受給額が高いことが一般的です。
年金を受け取るための条件は何ですか?
回答: 年金を受け取るための条件は、加入している年金制度によって異なりますが、一般的には一定期間以上保険料を納付し、定められた年齢に達する必要があります。
国民年金の場合、受給開始年齢は65歳からです。
年金の受給額はどのように計算されますか?
回答: 年金の受給額は、納付した保険料の総額、納付期間、受給開始年齢などに基づいて計算されます。
早期に受給を開始すると受給額が減額される場合が多いです。
年金のスキルが活かせる職種とは?
「年金」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- 年金アドバイザー
- 個人や企業に対して、年金制度や受給方法についてのアドバイスを提供。
- 公的年金や企業年金、個人年金の受給プランを作成し、最適な選択肢を提案。
- ファイナンシャルプランナー(年金専門)
- 個人のライフプランに合わせた年金の受給計画や資産運用を提案。
- 退職後の生活資金や老後の資金計画をサポートし、年金と貯蓄を組み合わせたアドバイスを提供。
- 年金コンサルタント
- 企業向けに年金制度の設計や運用に関するコンサルティングを行う。
- 企業年金制度の見直しや最適化を支援し、従業員の退職金制度を含めた長期的な福利厚生戦略を提案。
- 企業年金プランナー
- 企業内で従業員向けの年金制度の設計や運営を担当。
- 企業年金基金の運用を管理し、従業員の将来の年金受給に向けた計画を立てる。
- 社会保険労務士(年金関連)
- 年金に関する法律や手続きをサポートし、個人や企業の年金に関する手続きを代行。
- 年金請求や受給資格に関する相談に対応し、適切な手続きを支援。
- 年金運用ファンドマネージャー
- 企業年金や公的年金の資産を運用し、リスクとリターンのバランスを保ちながら長期的な成長を目指す。
- 年金資産を株式や債券、その他の金融商品に投資し、運用成果を最大化。
- 年金制度教育インストラクター
- 企業や個人に対して、年金制度に関するセミナーや講座を実施し、年金の基礎知識や制度変更について教育。
- 年金の仕組みや将来の年金受給に関する情報を提供。
- 年金サービスカウンセラー
- 年金に関する相談窓口で、個人が年金受給に関する情報を得られるようにサポート。
- 年金請求書類の作成支援や、受給開始時期に関するアドバイスを提供。
- 公的年金運営機関の職員
- 国民年金や厚生年金の運営機関で、年金制度の管理や受給者のサポートを担当。
- 年金給付に関する手続きやシステムの運営を行う。
- 退職金・年金制度の設計担当者
- 企業の退職金や年金制度を設計・管理し、従業員に対する長期的な福利厚生を構築。
- 従業員の老後資金の確保を目的とした制度改革や最適化を提案。
年金に関する知識や経験は、個人のライフプランニングから企業の福利厚生制度まで、幅広い分野で活用できる職業に結びつき、将来の資金計画や資産管理をサポートする役割を担います。
まとめ
年金について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、年金がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。