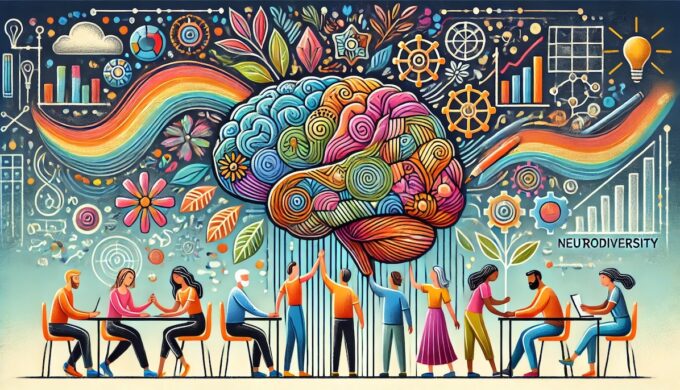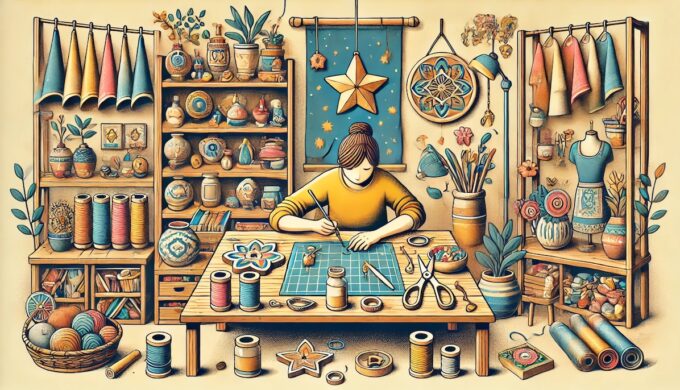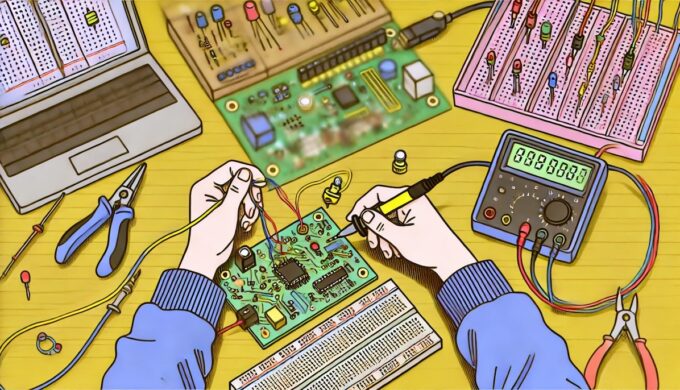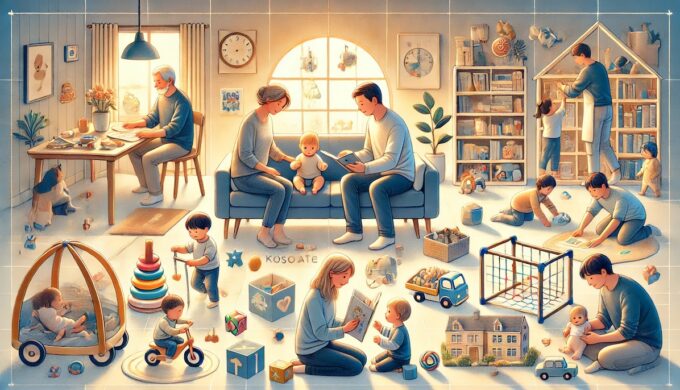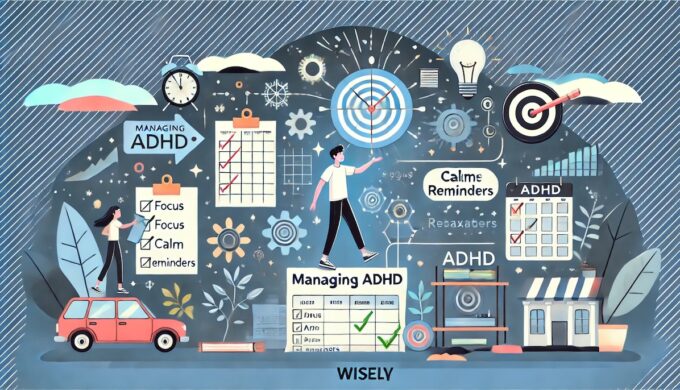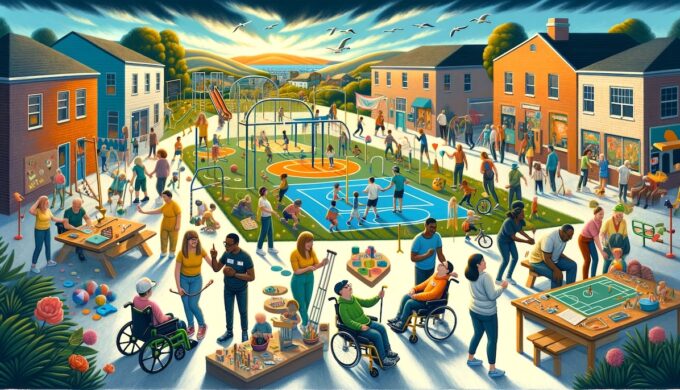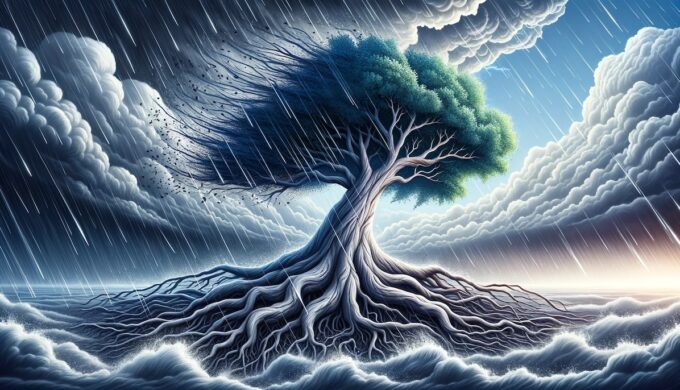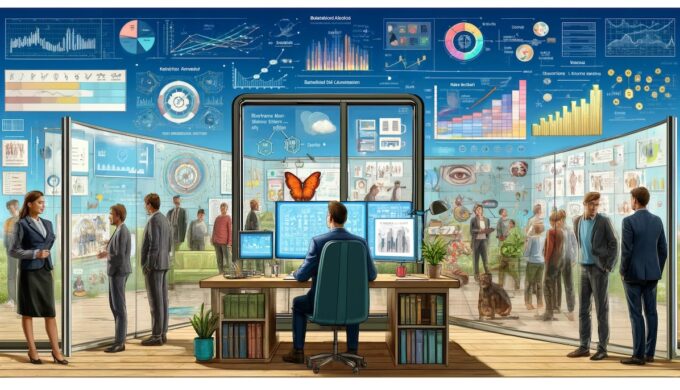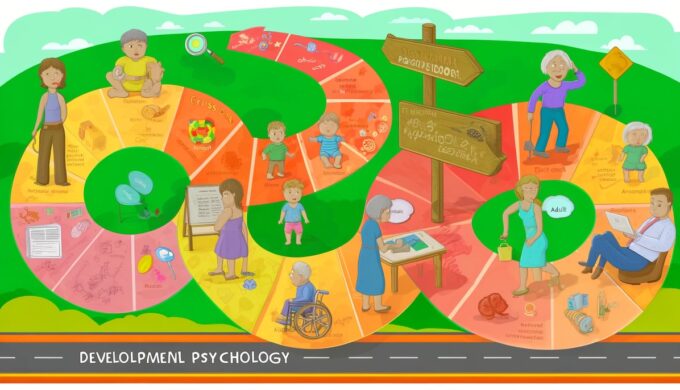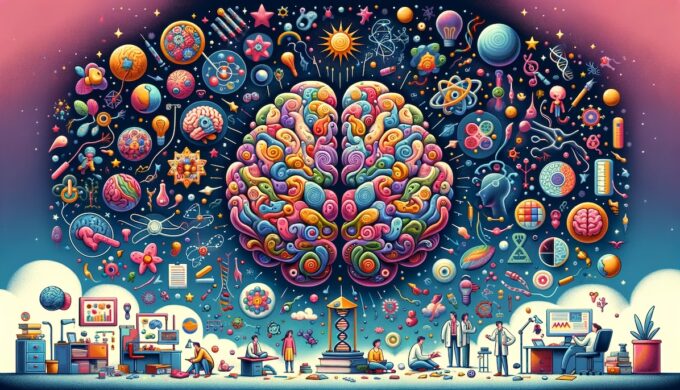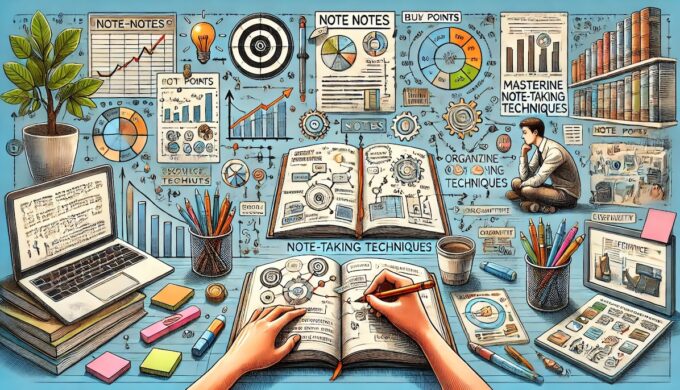子どもの発達障害について知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
子どもの発達障害とは、ADHDやASD、学習障害(LD)など、発達の過程で特性が現れる状態を指します。コミュニケーションや学習、行動に困難を感じることがあり、早期発見と適切な支援が重要です。一人ひとりの特性を理解し、成長をサポートすることが大切です。
まずはじめに、子どもの発達障害がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 発達障害と診断された子どもの親や保護者:子どもの特性を理解し、日常生活や学習をサポートする方法を学びたい
- 発達障害の疑いがある子どもの親:診断前に子どもの行動や特性について理解を深め、適切な対応を検討したい
- 幼稚園や保育園の先生:発達障害を持つ子どもへの適切な指導方法や支援スキルを身につけたい
- 小・中・高等学校の教師:教室で発達障害のある子どもをサポートし、学習環境を整えるための知識を得たい
- 特別支援教育の担当者:発達障害を持つ子どもに対して、個別の教育計画や支援を行うための具体的な方法を学びたい
- カウンセラーや心理士:発達障害を持つ子どもやその家族に適切な心理的支援を提供するために知識を深めたい
- 医療関係者(小児科医、発達障害専門医、看護師など):発達障害の診断や治療に必要な知識を学び、親子をサポートしたい
- 福祉や児童相談所のスタッフ:発達障害を持つ子どもや家族を支援するための具体的な方法を学びたい
- 親戚や家族のサポート役:親や兄弟以外の立場から発達障害を持つ子どもを理解し、支援したい
- 子ども向けのスポーツや習い事の指導者:発達障害の特性を理解し、子どもが安心して参加できる環境を作りたい
- 保護者の仲間やサポーター:発達障害を持つ子どもの親同士で情報を共有し、支援体制を強化したい
- 発達障害の子どもを将来的に支援したい学生:教育、心理学、福祉などの分野を学び、実践に備えたい
- 一般の関心がある人:子どもの発達障害について正しい知識を身につけ、偏見をなくして理解を深めたい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
最大45%還元
紙書籍 ポイントフェア
3/2(月)まで
今すぐチェック
おすすめ5選)子どもの発達障害の本
子どもの発達障害がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと
書籍情報
臨床経験30年以上の専門医が現場から伝えたい“本当のこと"
「グレーとは白ではなくて薄い黒」
「『友達と仲良く』と言ってはいけない」
「『せめてこれくらい』はNGワード」
「宿題は百害あって一利なし」
など、「発達障害」当事者の親にしてみるとぐっと心に刺さることを笑顔でおっしゃる本田先生。ただし、その解説をうかがうと非常に腑に落ちて、合理的で、子どもの発達に不安や悩みを抱える親御さんには、目からウロコの本になると思います。
amazon.co.jp書籍情報より引用
親や支援者たちの認識をコペルニクス的に変える!新たな知見を授け、支援の意味に気づかせる一冊です。(編集担当)。
評判・口コミ
子どもの発達障害がよくわかる本 これ1冊で理解もサポートも!
書籍情報
臨床経験20年以上の児童精神科医が本当に伝えたいこと
「はじめに」より
この本は、発達障害を持つお子さんや、その疑いがあるお子さんを支援したい方々のために書かれたものです。
今回、疑問にお答えする形で100個分、すべて私が書きました。
まだまだ内容的に書き足りない、伝えきれないところもありますが、一応、特性の理解、接し方、支援、進学の現状まで、幅広い範囲を書いたつもりです。これは私の考えなのですが、【環境や人間関係のバランスには「ちょうどよい」というラインがある】と思うのです。
発達障害の子ども本人は、頑張りすぎてはいけません。そんなことを続けていたら、いつか倒れてしまうからです。かといって、発達障害であることを理由に、何も頑張らなければ本人のためになりません。
周囲もそうです。全然寄り添わないのはいけませんが、寄り添いすぎてもいけません。周囲が疲れすぎてしまったらダメです。
だから、そんな【バランスのよいところを、試行錯誤しながら探していってもらえたら】と思っています。(中略)
子どもたちは無限の可能性を秘めています。あのキラキラした瞳をくもらせたくはありません。ひとりでも不幸にさせたくない。生まれてきてよかったと思ってほしい。それが私の願いであり、保護者や支援者の皆さんも同じ思いであることでしょう。
この本が、多くの方々の【道しるべ】になれたら、この上なくうれしいです。
amazon.co.jp書籍情報より引用
こどもの発達障害 僕はこう診てきた
書籍情報
発達障害とは何か。どう診断されるのか。どんな種類があるのか。医療や教育はどうおこなわれているか。小学校入学から中学進学、思春期から成人への成長過程を踏まえ、さらなる将来をどう考えるか。
発達障害をめぐっては、さまざまな考え方、さまざまな対応があります。本書では、発達障害をめぐる現状をつまびらかにしつつ、課題や将来の方向性について概説していきます。
まず、障害、発達障害に対する現在のわが国および国際的な考え方を整理し、自閉症スペクトラムやADHD、発達性学習症、発達性協調運動症、知的発達症など、代表的な障害について説明します。さらに、発達障害を抱える子どもが利用できる社会資源、年齢層に応じて抱える課題や、将来展望まで概観します。
著者の50年近くにわたる臨床経験を凝縮した一冊です。最新のICD-11(国際疾病分類11版)での診断要件(著者訳)も掲載しました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本
書籍情報
「落ち着きがない」「友だちと上手に接することが出来ない」「何度言っても忘れてしまう 」こうした症状は、もしかして、発達障害かもしれません。そして、困らせてる子供自身が、「困っている」のです。まずは気づく、そして理解し、寄り添うことが大切です。
本書では気になる症状から、その特性を理解できるようやさしく解説し、具体例を交えてアドバイスしてくれます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル
書籍情報
★親も教員も必携の1冊★
教えたいことが確実に届く! 子どもが変わる! 成長する!
これまで2000人を超える人の支援に関わってきた特別支援教育のエキスパートが送る「支援スキルの大全集」イライラ、パニック、暴言・暴力など、解決の難しい問題にも効果あり。
amazon.co.jp書籍情報より引用
多くの発達障害・グレーゾーンの人と関わるなかで磨き上げられた、子どもたちへの「声のかけ方」「接し方」、そしてアセスメントの方法を100集めました。
注目の新刊)子どもの発達障害の本
子どもの発達障害がわかる本の注目の新刊を、紹介します。
今月は該当する新刊が見つかりませんでした。
ロングセラー)子どもの発達障害の本
子どもの発達障害がわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
子どもの発達障害と支援のしかたがわかる本
書籍情報
本書は、はじめて「発達障害」や「特別支援教育」、「インクルージョン」を学ぶ以下のような方のために書かれています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
◎大学生や保護者、幼稚園から高校までの教員、特別支援教育支援員、保育士、児童発達支援センターや放課後等デイサービスの指導員の方々
◆子どもの発達障害の特徴と支援方法をコンパクトに解説
発達障害には、自閉症(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)、知的障害などの種類があります。
本書では、子どもの発達障害の特徴と支援方法のポイントを「1項目見開き2ページ」でコンパクトにまとめました。
◆予備知識のない方でもしっかりと理解できる
よくある子どもの言動の例や、発達段階に応じた接し方などについても丁寧に解説していますので、予備知識のない方でも基本からしっかりと理解できます。
子どもの発達障害と感覚統合のコツがわかる本
書籍情報
発達障害の子どもがのびる「感覚統合」の支援のコツを解説!
人は、「感覚」の発達を土台にして「運動」「行動」「学習」などさまざまな力を獲得していきます。「感覚統合」は、この感覚のつまずきにアプローチして発達を促すことでより高度な動作の改善につなげていく支援方法です。本書では、感覚統合の基礎知識や実際の支援のコツをイラストを交えてまとめました。識別感覚や原始感覚など、さまざまな感覚の特徴を説明したうえで、気になる子どものケースを挙げながら丁寧に解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
この1冊で、子どもの発達を促す「感覚統合」の全体像がわかります。
医療現場の悩みを解決! 子どもの発達障害Q&A
書籍情報
発達障害が広く認知され、医療的介入の重要性も明らかになる中、発達の相談で医療機関を受診する子どもが増えています。
かつては専門機関を予約するケースが多かったものの、最近では、まずかかりつけ医に相談する家庭が増えてきました。
まさに「発達障害はCommon Disease(ありふれた疾患)」となりつつあります。
一方で、多くのかかりつけ医は発達障害診療のトレーニングを受けておらず、普段の「病気を治す」診療とは異なる、「子どもの人生を扱う」診療に戸惑いを感じています。本書は、筆者の「発達障害に関わる医師が増えてほしい」という思いから生まれました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
各Q&Aの冒頭では【原則&エビデンス】を提示し、次に具体的な【症例】を紹介。
その症例を通じて、原則&エビデンスを詳しく【解説】しています。
ここまでが発達障害診療で守るべき枠組みです。
さらに、【私はこうしている】では、筆者自身の経験や先達からの教えをもとに、診療方法が決まっていない部分について、どのような判断をしているのか、実際の「さじ加減」を紹介しています。
外来で診る子どもの発達障害〜どこまでどのように診るか?
書籍情報
非専門医がフォローすべき範囲や専門医紹介の基準・タイミング、教育現場との連携など、小児の発達障害診療を行うための実践的なコツを豊富なケーススタディで解説。
子どもや家族との寄り添い方が学べる実践書!
amazon.co.jp書籍情報より引用
子どもの発達障害とソーシャルスキルトレーニングのコツがわかる本
書籍情報
本書は、「発達障害の子どもの特徴」や「必要なスキル」などを紹介したうえで、学校や家庭などで実践できる「トレーニングの考え方とコツ」をまとめました。最初の1冊にぴったりな先生や保護者の方に向けた入門書です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
発達障害の子どもを伸ばす 魔法の言葉かけ
書籍情報
親子が笑顔になれる「言葉かけ」「行動のコツ」がわかります!!
親からの適切な「言葉かけ」で、発達障害の子どもは大きく伸びる!
家庭で楽しみながら行える、ABA(応用行動分析)を利用した「言葉かけ」の方法を具体的にわかりやすく紹介。《毎日の生活のなかで、すぐできる!》
amazon.co.jp書籍情報より引用
・手を洗うときの言葉かけ
・散歩のときの言葉かけ
・いっしょに料理をするときの言葉かけ
・食事をしながらの言葉かけ
・遊びながらの言葉かけ など
子どもの発達障害と環境調整のコツがわかる本
書籍情報
◎子どもを伸ばす「環境調整」の方法がわかる!
amazon.co.jp書籍情報より引用
子どもたちが学校で安心して過ごすためには、3つの「環境」を整えることが必要です。
3つの環境とは、①教師の関わりなどの「人的環境」、②教材などの「物的環境」、③教室などの「空間的環境」です。
環境調整を行うことによって、子どもたちの困り感を成功体験へとつなげることができます。
本書では、環境調整の特徴や進めるコツを説明したうえで、子どものケースごとの環境調整の具体例を豊富な写真やイラストで解説します。
★気になる子どもへの支援方法
◎言語理解が苦手な子どものケース
◎大きな音が苦手な子どものケース
◎読むことが苦手な子どものケース
◎書くことが苦手な子どものケース
◎片づけることが苦手な子どものケース
◎集団参加が苦手な子どものケース etc.
発達障害の子どもに伝わることば
書籍情報
"なぜか伝わらない"を"伝わる!!"に
amazon.co.jp書籍情報より引用
「ちょっと待ってね」は待ってくれないのに、電子レンジのチンは待てるのはどうして?
「ダメでしょ!」「もうやめて」と言っても、困った行動を繰り返すのはどうして?
ことばとコミュニケーションの発達と、発達障害の特性を持つ子どもたちに伝わる声かけ・コミュニケーション。
発達障害のわが子を持つ保護者の方々はもちろん、子どものコミュニケーションに悩むすべての人に贈る、気鋭の専門家、初の新書。4人の専門家が寄稿したコラムを併録。
子どもの発達障害と二次障害の予防のコツがわかる本
書籍情報
発達障害などの生まれつきの個性を「一次障害」と呼びます。そして、その人に合わない環境で無理に適応しようとして、精神症状の発症や不登校などの二次的な問題が起きている状態を「二次障害」と呼びます。本書では、子どもの二次障害の特徴や対応のコツを、支援事例を交えながら丁寧に解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
イラストでわかる 特性別 発達障害の子にはこう見えている
書籍情報
大人の発達障害者と定型発達、双方から見た世界を解説し人気を博した『イラストでわかる シーン別 発達障害の人にはこう見えている』の第2弾。今回は「発達障害を持った子ども」の世界を解説します。
発達障害という診断は下されていなくてもそうした行動に困っている親御さんは多いのではないでしょうか。
本書はそうした方たちに役立つ解決メソッドが満載の一冊です。内容としては前作同様、周りの人と当事者の双方から見た世界をイラストで理解できるのはもちろん、「立ち歩きやイライラしやすいなどの特性が出ているときその子はどんな気持ちでいるのか?」がよくわかります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
またそうした行動を変える「言葉がけ」や対応法・お助けアイテムについても詳しく学ぶことができます。
発達障害の子に関わる人たちの理解を深める一冊であるとともに、あまりそうした知識のない人への入門書としてもおすすめできる一冊です。
子どもの発達障害によくある質問と回答
子どもの発達障害について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
子どもの発達障害とは何ですか?
回答: 子どもの発達障害は、認知、言語、運動スキル、社会的相互作用など、さまざまな発達領域に影響を及ぼす一連の条件を指します。
これには自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害などが含まれます。
子どもの発達障害の原因は何ですか?
回答: 発達障害の原因は多岐にわたりますが、遺伝的要因、出産時の合併症、環境要因などが関与していると考えられています。
しかし、多くの場合、特定の原因を特定することは難しいです。
子どもの発達障害の早期兆候は何ですか?
回答: 発達障害の早期兆候には、名前を呼んでも反応しない、他の子どもたちとの相互作用が少ない、言葉の発達が遅れている、繰り返し行動をするなどがあります。
これらの兆候が見られた場合、専門家に相談することが推奨されます。
子どもの発達障害はどのように診断されますか?
回答: 子どもの発達障害の診断は、通常、親や保護者の報告と医師による評価を基に行われます。
発達の遅れを評価するためにさまざまなスクリーニングツールや診断基準が用いられます。
子どもの発達障害をサポートするために家族ができることは何ですか?
回答: 家族は、子どものニーズを理解し、支持的な環境を提供することが重要です。
子どもの強みを活かし、困難に直面したときには適切なサポートと資源を提供すること。
また、定期的な治療セッションや専門家のアドバイスに従い、家庭での活動を通じてスキルを練習することも助けになります。
子どもの発達障害の知見が活かせる職種とは?
「子どもの発達障害」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- 特別支援教育の教員
- 発達障害を持つ子どもの教育を担当し、個別の学習ニーズに応じた指導を行う。
- 支援教育のカリキュラムを作成し、学習や社会性の向上を支援。
- 児童発達支援管理責任者
- 発達障害を持つ子ども向けの支援施設で個別支援計画を作成し、スタッフと連携して適切な支援を提供。
- 子どもと保護者に対して、日常生活や社会参加のためのサポートを行う。
- 保育士(特別支援保育)
- 発達障害を持つ子どもが過ごしやすい環境を整え、日常生活や社会性の発達をサポート。
- 保護者とも密に連携し、家庭での育児支援も行う。
- 臨床心理士・カウンセラー
- 発達障害を持つ子どもとその家族に対し、心理的な支援やカウンセリングを提供。
- 子どもの発達段階や特性に応じた心理療法を実施し、問題解決をサポート。
- 作業療法士
- 発達障害を持つ子どもが日常生活で必要なスキルを習得できるよう、感覚統合療法や動作訓練を実施。
- 自立した生活を目指した支援を行う。
- 言語聴覚士
- 発達障害に伴う言語やコミュニケーションの課題に対し、言語訓練やコミュニケーション支援を提供。
- 発語や理解力の向上を目指し、保護者と協力して家庭でのトレーニング方法も指導。
- ソーシャルワーカー(児童福祉)
- 発達障害を持つ子どもとその家族が利用できる福祉サービスを紹介し、適切なサポートを提供。
- 生活環境の改善や、必要な資源へのアクセスをサポート。
- 療育プログラム開発者
- 発達障害を持つ子どもの成長を支援するための療育プログラムを設計・運営。
- ゲームや活動を通じて子どものスキルを育てるための新しい方法を開発。
- 教育・研修講師
- 教育関係者や保護者に向けて、発達障害に関する知識や支援方法を伝える講座を担当。
- 子どもの特性や支援の重要性を広める活動を行う。
- ライター・コンテンツクリエイター
- 発達障害を持つ子どもに関する情報を発信し、保護者や支援者向けに役立つ記事や動画を制作。
- 自身の経験や専門知識を基に、情報発信を通じて社会的な理解を促進。
子どもの発達障害に関する知識や経験は、教育、医療、福祉、カウンセリングなどの分野で活用され、子どもの成長を支援し、生活の質を向上させるための重要な役割を担います。
まとめ
子どもの発達障害について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、子どもの発達障害がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。