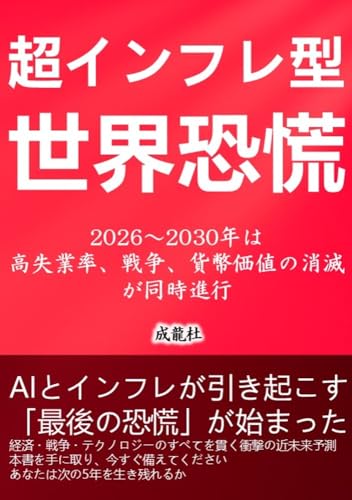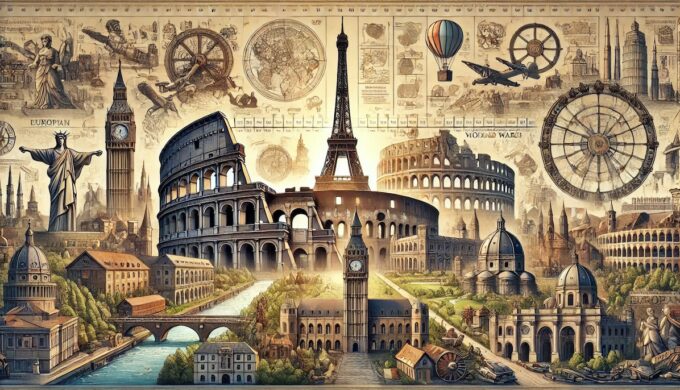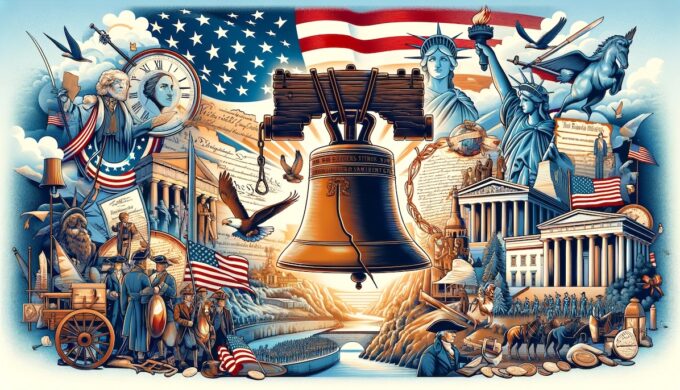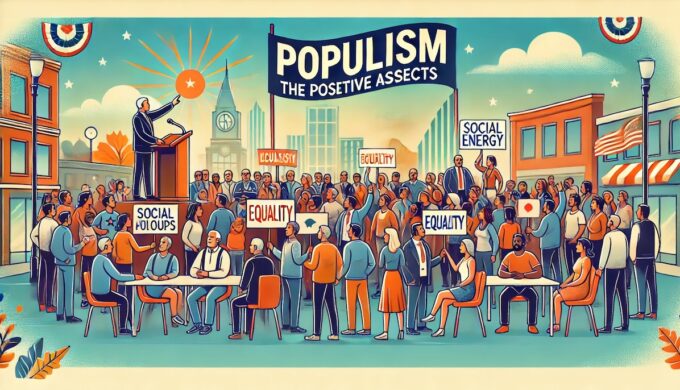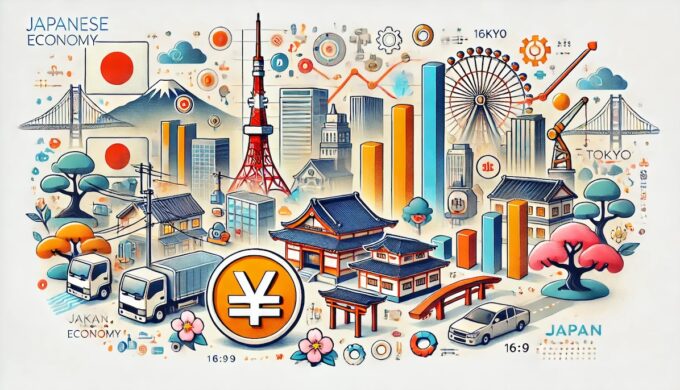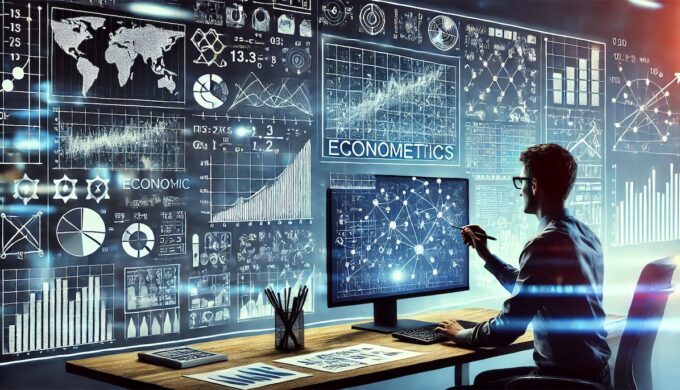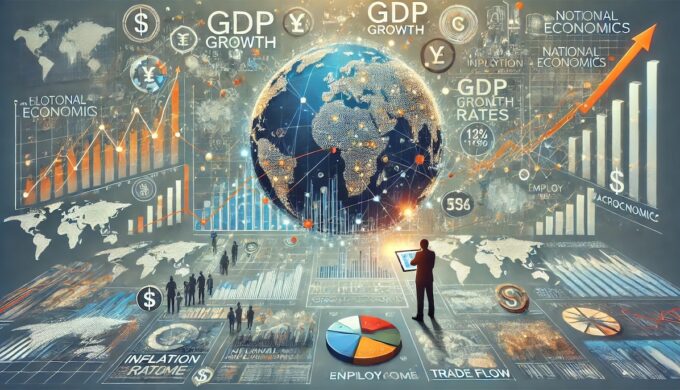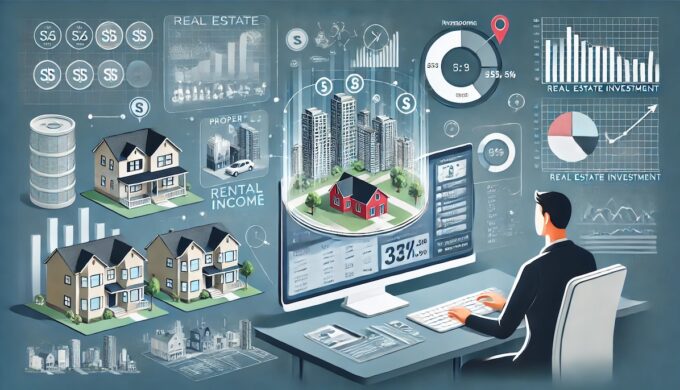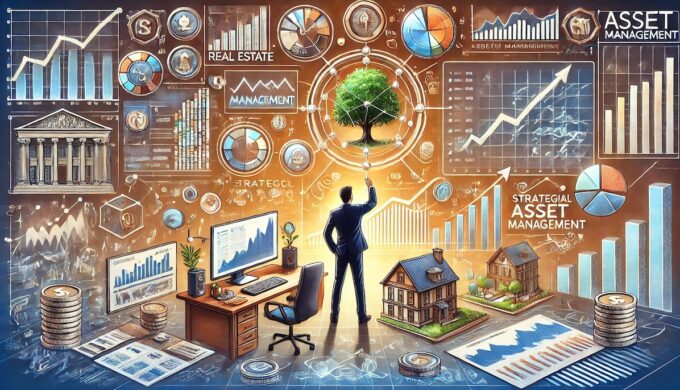インフレについて知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
インフレ(インフレーション)とは、物価が持続的に上昇し、お金の価値が下がる現象です。生活費の増加や購買力の低下につながり、経済全体に影響を及ぼします。適度なインフレは経済成長に寄与しますが、過度なインフレは問題を引き起こします。
まずはじめに、インフレがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか?
- 経済学を学ぶ学生や研究者:インフレーションの原因や影響、経済全体との関連性を深く理解したい
- 金融業界のプロフェッショナル:インフレの動向を分析し、投資や金融政策に活かしたい
- 経営者やビジネスリーダー:インフレが事業コストや利益率に与える影響を理解し、適切な経営判断をしたい
- マーケティングや価格設定に携わる人:インフレに応じた価格戦略や市場の需要変化に対応したい
- 投資家や資産運用を行う個人:インフレに強い資産(不動産、株式、コモディティなど)への投資戦略を学びたい
- 公務員や政策立案者:インフレが国民生活や経済に与える影響を把握し、適切な政策を策定したい
- 教育者や講師:インフレーションのメカニズムを理解し、学生や受講者に効果的に教えたい
- 生活設計や家計管理を考える一般消費者:インフレに備えて、家計の見直しや節約術を学びたい
- 年金生活者や高齢者:インフレが生活費に及ぼす影響を理解し、資産を守る方法を探している
- スタートアップや中小企業の経営者:インフレによるコスト上昇を予測し、資金繰りや価格設定を適切に管理したい
- コンサルタント:クライアントの事業や投資計画に対して、インフレへの対応策を提案したい
- 経済ニュースに興味がある人:日常のニュースや経済動向を深く理解し、生活や仕事に役立てたい
- 国際ビジネス関係者:海外市場のインフレ率を把握し、貿易や輸出入の戦略に活かしたい
- 社会問題に関心のある人:インフレが貧困層や経済格差に与える影響について理解したい
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
紙書籍 まとめ買いキャンペーン
・2〜4冊…2%還元
・5〜9冊…5%還元
・10冊以上…10%還元
詳しく見る 2月12日まで
おすすめ5選)インフレの本
インフレがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
物価を考える デフレの謎、インフレの謎
書籍情報
物価・金利はどう動くのか? 経済の大転換を読み解く。
amazon.co.jp書籍情報より引用
物価研究の第一人者が、最先端の理論・データ分析をもとに日本経済最大の謎に迫る!
なぜ日本だけデフレは慢性化したのか? 慢性デフレはなぜ突然終わり、インフレが始まったのか? 異次元緩和はなぜ失敗したのか? インフレやデフレはなぜ悪なのか?
・日本の慢性デフレは現代経済学の大きな謎
・デフレとインフレの統一理論とは?
・カギを握る人びとのインフレ予想
・従来の経済学の常識が成り立たなくなった
・腕力から便乗へ。植田・日銀で大きく変化した政策手法
・日銀の政策金利は、2027年末には2%を超えるところに到達すると予測される
・日銀は人びとが望むだけマネーを供給すべき
多くの謎に包まれた日本のデフレとインフレ。従来の経済学の常識を超え、大胆な仮説で日本経済の謎を読み解く。
僕たちはまだ、インフレのことを何も知らない デフレしか経験していない人のための物価上昇2000年史
書籍情報
世界は、インフレの恐怖を忘れてしまった――
デフレしか経験していない人に贈る、おカネの価値が減り続ける時代の経済サバイバルガイド!この30年間の大半の時期を通じて、政策立案者と投資家はいずれも、デフレーション(デフレ、物価下落)の危険性のほうにずっと目を光らせていた。(中略)
実際、ヨーロッパと北米では、高齢化が進行し、債務が膨らみ、資産価格が(当初)暴落し、銀行が続々とつぶれ、成長が停滞し、ますます多くの物価が下落していった。
こうした状況下では、1970年代と1980年代の経済の主な筋書きを形づくったインフレとの戦いは、もはや遠い過去の記憶にすぎなくなった。(中略)
インフレはおおむね冬眠を続けてきたが、本当の意味で死んだわけではなかった。本書の執筆時点でも、インフレは新たな復活を遂げつつある。
なぜこのような現象が起きているのか? 取るべき対策は?
この2つは間違いなく、現代最高の経済的(ひいては政治的)疑問と呼ぶにふさわしいだろう。(はじめにより)
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
新型インフレ 日本経済を蝕む「デフレ後遺症」
書籍情報
スタグフレーションの前触れか?
amazon.co.jp書籍情報より引用
「失われた40年」の始まりか?
個人消費は停滞しているのに物価上昇の勢いが止まらず、実質賃金は下がり続けている。
一方で金利は上昇基調にある。
この“歪んだインフレ" は、なぜ日本だけで起きているのか?
今後スタグフレーション(物価高騰と景気後退の同時進行)は起きるのか?
トランプ関税はどれほどの影響があるのか?
人気エコノミストがあざやかに分析する!
ハイパーインフレの悪夢 ドイツ「国家破綻の歴史」は警告する
書籍情報
貨幣価値の下落と物価の上昇が限度を超えたとき、私たちの日常は激変する。
破綻の前触れから末路までを生々しく描き出した迫真の記録。
紙幣を刷ることで危機を脱せると信じた国の末路――今から100年前、第一次世界大戦に敗北したドイツは、政府の財政支出をまかなうため、大量の国債を発行した。
amazon.co.jp書籍情報より引用
通貨安で輸出がさかんになって、企業はうるおい、失業率は低下、株式市場も活性化するが、やがて深刻な物価高騰が庶民の生活を襲う。
失業と破産が増え、モラルが失われ、ありとあらゆる対立が噴出するなかで、ひとびとはどう行動し、社会がどう崩壊していったのか。
財政破綻国の過去が警告する、この国の「明日」。
評判・口コミ
注目の新刊)インフレの本
インフレがわかる本の注目の新刊を、3冊、紹介します。
インフレ・円安・バラマキ・国富流出 (日経プレミアシリーズ)
書籍情報
円の価値が毀損し続ける中、どのように自分の資産を守るべきか
amazon.co.jp書籍情報より引用
「いつか円高に戻る」という過去の経験則は通用しない
本書は、為替の第一人者が、円安の根本原因を解き明かし、今後起こりうるシナリオと防衛策を提示する。静かに進行する危機の本質を把握し、インフレの時勢を生き抜くための一冊。
インフレの時代 賃金・物価・金利のゆくえ
書籍情報
世界で先行していた物価の高騰=インフレーションが、日本でも2022年春から始まった。
amazon.co.jp書籍情報より引用
それまでの慢性デフレから一転したのはなぜか――。
物価研究の第一人者がその謎を解く。物価高騰は私たちの生活を圧迫するが、同時に賃上げを達成すれば、市場は価格メカニズムを取り戻し、日本の経済は好循環で回り始める。
どうすれば賃金を上げられるのか? 政策金利は、財政はどうなるのか?
直撃するインフレの実態に迫る。
超インフレ型世界恐慌 2026~2030年は高失業率、戦争、貨幣価値の消滅が同時進行
書籍情報
AI革命、戦争、通貨崩壊――2026年から始まるのは「成長の時代」ではなく「価値の崩壊」の時代だ。
amazon.co.jp書籍情報より引用
米中の金融戦争、AIによる雇用喪失、そして各国が進めるマネー供給の暴走が、かつてない「超インフレ型世界恐慌」を引き起こす。
物価は暴騰し、資産は溶け、国家の信用すら消滅する。
本書は、AI革命・地政学・マネー構造・国家債務・社会秩序の崩壊までを俯瞰し、個人と国家が直面する「貨幣文明の終わり」を描く。
さらに「恐慌後の社会設計」までを描く警鐘の書である。
経済書であり、同時に文明論であり、未来予測書でもある。
あなたがこれからの5年間をどう生きるか、その答えがここにある。
未来を生き抜く知的サバイバルの必読書。
ロングセラー)インフレの本
インフレがわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
世界インフレ時代の経済指標
書籍情報
今、時代が大きなパラダイムの転換点を迎えています。
相場の大局観は、経済指標で手に入れよう!
いま最も影響力のあるエコノミストによる、経済金融の教科書。
景気、金利、為替、株価、物価… 経済と金融のなぜ? がスッキリ!
物価や原材料の高騰、サプライチェーンの混乱、金利上昇をはじめ、現在の私たちを取り巻く経済と社会は大きな変化に見舞われ、近年にないほど先行きが不透明です。
政治的対立や戦争が、金融相場のみならず「インフレ」という形で私たちの「日常」「暮らし」へと影響を及ぼしています。現状を正確につかみ、未来を読む手がかりとなるのが「経済指標」です。
シグナルを知ることで景気の変動に左右されることなく大切な資産を守り、着実に増やすことができます。本書は、投資家や金融機関が参考にするオーソドックスな指標、指標を読む際に役立つ「複合指数」、景気を読むうえで指標となる企業などを解説する1冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
投資家やグローバルビジネスに携わる人のみならず、これから経済を学びたい人を対象としていて、経済を読み解く羅針盤としての1冊となります。
評判・口コミ
世界インフレと戦争 恒久戦時経済への道
書籍情報
世界が物価高騰に襲われている。この高騰は、景気の過熱に伴う「デマンドプル・インフレ」ではなく、景気後退・政情不安を招く「コストプッシュ・インフレ」の性格が強い。その背景にあるのは、グローバリズムの終焉という歴史的な大変化だ。
このようなときには安全保障の強化や財政支出の拡大が必須だが、それらを怠ってきた日本は今、窮地に陥っている。世界秩序のさらなる危機が予想されるなか、もはや「恒久戦時経済」を構築するしか道はないのか。インフレの歴史と構造を俯瞰し、あるべき経済の姿を示した渾身の論考。
amazon.co.jp書籍情報より引用
トランプ・インフレが世界を襲う
書籍情報
「この本は読んではいけない!」森永卓郎氏非推薦!
amazon.co.jp書籍情報より引用
インフレ格差を解消し金融資産を増やす
日本人が豊かになる方法!
お金が紙クズになる前に株を買うしかない
【崖っぷちの日本経済再生法!】
世界を見渡せばインフレは止まらない!
日本人はますます貧しくなっていく!
日本経済と日本人を豊かにする方策を探る!
世界インフレ 日本はこうなる
書籍情報
世界インフレとは? 日本はいつからこんなに安い国になったのか?
安すぎる国、日本の行方を徹底解説!「日本は豊かな国」「日本は経済大国」、それはもはや過去の話。
いま、世界経済における日本の現在地は、モノの値段・給料・不動産の価格などから見ても「安い国」になります。
世界の優良企業トップ50社でも、日本の企業でランクインしたのは0。すっかり「稼げない国」「競争力の低い国」「安い国」になってしまった日本の経済は、これからどうなるのか?
池上さんが、世界各国の「モノの値段」「賃金」「不動産価格」から世界経済の流れを読み解きます。◎世界的に物価があがっている「インフレ時代」ってどういうこと?
◎いま日本が安い国って、どういうこと?
◎そもそも日本経済がずっと不景気だった理由は?世界の潮流のなかで、日本の経済が停滞している理由や、今後の日本経済が復活するポイントを説く1冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
超インフレ時代の「お金の守り方」 円安ドル高はここまで進む
書籍情報
1ドル150円は「序の口」に過ぎない。
amazon.co.jp書籍情報より引用
今すぐ「資産防衛」を!
急激な物価上昇、進む円安。円ドル相場は一時1ドル150円を超えるなど、1年で40円近くの円安に。まさに異常事態である。
しかし、著者は「これはまだ序の口に過ぎない」と主張する。今の日本と世界を取り巻く状況、そして日米の実力差を考えれば、1ドル180~200円、さらには400~500円かそれ以上になってもおかしくないというのだ。
なぜ、ここにきて全世界的な物価上昇が起きているのか。円安ドル高はどこまで進むのか。日本経済の先行きはどうなるのか。「ハイパーインフレ」は本当に来るのか……本書はこうした疑問にすべて答えていく。
また、急激なインフレが続くアメリカを現地取材し、その知見をベースに、円安ドル高の「真因」を解き明かしていく。
そして、多くの人の最大の関心事である「資産の守り方」を説く。持つべきはドルか円かユーロか。株式は、金は、不動産はどうなのか。資産を守るために最も大事なこととは……。
来たる大激動の時代に生き残るために必須の一冊。
インフレ・ニッポン 終わりなき物価高時代の到来
書籍情報
●半世紀ぶりの大インフレ、四半世紀ぶりの円安
コロナ禍とウクライナ戦争を背景におよそ半世紀ぶりの大インフレが世界を襲った。低インフレにあえいできた日本も例外ではない。「輸入インフレ」の深刻度は米欧をしのぐ。資源高に根ざす物価高に拍車をかける円安が同時に広がったためだ。世界的なインフレの波のなかでも、日本は賃金デフレの流れが終わらず、日銀は金融引き締めに動けない。輸入インフレと、なお残る賃金デフレ。そのダブルパンチが通貨安を生み、さらなる物価高を生む悪循環になった。
本書は、日本と海外に広く目を向け、市場をウオッチしてきたベテランの日経記者によるもの。ファクトを積み上げ、幅広い取材から総合的な視点で日本の今後を占う。
●ピンチはチャンスになるか
苦境の日本にチャンスはあるか。モノの値段が上がるということは、停滞してきた日本経済を動かすことになる。よい値上げはモノやサービスの付加価値をあげることであり、脱炭素、デジタル時代においてのより一層のイノベーションが期待できる環境となる。例えば物価連動の賃金制度を取り入れるなどして、消費者の効用をあげるという策も必要だ。
また、4月からの日銀新総裁の就任は、脱アベノミクスを掲げたものになる必要があるだろう。円安誘導で企業業績は向上したものの、賃金は下落し、格差は助長された。今後も資源インフレが予想されるなかでの円安は、もはや限界を迎えている。正常な金融政策を取り戻し、成長に向けて舵を切っていくことが求められる。
amazon.co.jp書籍情報より引用
高金利・高インフレ時代の到来! エブリシング・クラッシュと新秩序
書籍情報
2025年の4月2日、アメリカのトランプ大統領が世界に向けて発表した関税政策は、世界中に衝撃を与え、世界同時株安を招いた。
NYダウやS&P、nasdaqなどの米国の株価の主要指数の暴落は一週間ほど続き、日経平均も一時は500兆円のもの時価総額を失うほどの暴落となった。いわゆる「トランプショック」である。
今回の経済危機は、まさにこの本の校了中のできごとであり、日々、情報をアップデートしながら、この本は完成した。
ただ驚くことに著者は、すでにこの本において経済危機が来ることを予測し、4つの兆候について詳しく分析していたのだ。
それは2000年代のITバブル崩壊やリーマン・ショックの際にも表れた、いくつもの経済指標の変化を読み解いた結果だった。また日々の経済データの分析のみならず、経済の歴史も深く研究している著者は、今回のトランプショックを単なる一時的なものとは捉えず、世界経済や国際政治が大きく変化するパラダイム・シフトと考えており、その理由も本書では明らかに語られている。
中国のみならず、BRICS諸国も台頭する今、私たちは大きな歴史的か転換期に生きているのだ。
米国と中国の新冷戦、それによる経済のディカップリングを早くから予見していた著者は、常に著書やSNSで最新の情報を発表してきた。本書は、それらを集大成し、世界が変わる重大な局面において発想の転換を促す書でもある。
ますますひどくなる新冷戦によって経済がブロック化し、世界中がより高インフレに悩まされ、インフレ下の不況、すなわちスタグフレーションに陥りかねないことに著者は警鐘を鳴らしている。こんな先行きが見えない時代に、自分の資産を守るにはどうしたら良いか、歴史を学び長期的な視点を持つことの大切さを説く。
amazon.co.jp書籍情報より引用
さらにこの新冷戦の中、再び注目を浴びるのが日本であることにも言及し、危機をチャンスととらえるべきことを教えてくれる。
世界が日々、変化する現代に生きる私たちが、経済危機をいかに乗り越え、未来に希望をもつべきか? 多くのヒントを教えてくれる必読の書である。
高くてもバカ売れ! なんで? インフレ時代でも売れる7の鉄則
書籍情報
「高くても、売れます」その秘訣を知りたいあなたへ
あらゆるモノやコトが値上がりする今、多くの消費者の購買意欲は低下傾向にあります。
この時代背景をふまえて、
「良い商品でも買い控えによって正しく売れないのでは?」
「原価の高騰で、消費者に寄り添いたくても製造上むずかしい」
・・・そんな悩みを抱えているマーケターや営業職のビジネスパーソンの方々は、多いのではないでしょうか?しかし、そのような状況下でも、確固たる利益を担保している商品やサービスは数多く存在します。
本書では、マーケティング視点から見た主に国内の成功事例を元に、「時代に適応しながらモノを売るための方法論」と「打ち手」をまとめた1冊です。
各章で登場する「キーワード」は、既存の売り方にこだわり、ビジネスチャンスを逃していた“もったいないビジパ=あなた”の救世主となり、あなたが関わっている事業を成功へと導くヒントになるでしょう。モノが売りにくい時代でも、見せ方・売り方の工夫次第で、ヒット商品・サービスを生み出すことは可能です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
さあ、本書でマーケティングの新常識をともに学びましょう!
世界インフレと日本経済の未来 超円安時代を生き抜く経済学講義
書籍情報
●世界インフレ、日本の円安・物価高、ウクライナ危機……
amazon.co.jp書籍情報より引用
●加速・複雑化する現代経済の要点を整理し、平易に解説!
●〝安い日本〟に負けない「日本の勝機」が見えてくる!
長引いたデフレの終焉と、世界的なインフレ時代への突入。
消費者も企業も対応に迫られる、日本の円安・物価高。
地政学リスクの高まりに反応し、変容するグローバル経済――。
経済学者の伊藤元重氏は、これらの社会情勢を、物価も賃金も上がらなかった「停滞と安定」の時代から、「変化と不確実性」の時代へと移行とみなし、その変化の先を見通すことの難しさを語る。
しかし、「予測不可能な未来を見通すためには、経済学の力が必要である」とも語り、さまざまな経済学の視点から、これら「難問」の解明に挑む。
読めば加速・複雑化する社会情勢が理解でき、日本再興の「勝機」が見えてくる!
増税とインフレの真実
書籍情報
「財政難ゆえ防衛増税やむなし」「物価上昇が家計直撃」「ハイパーインフレと国債暴落のリスクも」と連日報じられている。しかし「増税しなくても財源はある。増税やむなしは大ウソ」「世界標準で見れば、日本はインフレではない。金融引き締めは尚早」「ハイパーインフレや国債暴落も大ウソ」と著者は説く。
なぜ政府は「大ウソ」をついてまで増税をしたがり、インフレだと危機感をあおるのか。その裏には「増税が手柄、勲章になる財務官僚」と、「その言いなり・岸田首相」連合の思惑があった。どのような思惑のもとに、国民は騙されてきたのか。そして本当に知るべき真実とは?
著者は財務官僚を約30年務め、日本政府のバランスシートを史上初めて作成した。日本経済の裏の裏まで知り尽くす数量政策学者が、増税、インフレ、国債、為替といった経済のメインテーマを真正面から取り上げ、真実を明らかにする。この本を読めば、今後ウソや恣意的な情報に騙されず、自分の目で経済の本質を見極めることができる。Youtube「髙橋洋一チャンネル」で登録者数87万人を誇る著者渾身の書き下ろし。
amazon.co.jp書籍情報より引用
インフレによくある質問と回答
インフレについて、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。
インフレとは何ですか?
回答: インフレとは、一般的な物価水準が持続的に上昇する経済現象を指します。
これにより、通貨の購買力が低下し、同じ金額で以前より少ない商品やサービスしか購入できなくなります。
インフレが発生する原因は何ですか?
回答: インフレには主に二つの原因があります。
一つは需要が供給を超える「需要引きインフレ」、もう一つは生産コストの上昇が原因の「コストプッシュインフレ」です。
需要引きインフレは、経済が過熱し消費者の支出が増えることで発生し、コストプッシュインフレは、原材料費や賃金の上昇が原因で起こります。
インフレ率とは何ですか?
回答: インフレ率は、一定期間における物価水準の上昇率をパーセンテージで表したものです。
たとえば、インフレ率が1年で2%だった場合、平均的な物価がその年に2%上昇したことを意味します。
ハイパーインフレとは何ですか?
回答: ハイパーインフレは極端なインフレ現象で、物価が非常に高い割合で上昇します。
月に50%以上の物価上昇がハイパーインフレと定義されることが多いです。
ハイパーインフレは通貨の価値を急速に減少させ、経済的混乱を引き起こします。
インフレとデフレーションの違いは何ですか?
回答: インフレは物価が上昇する現象で、デフレーションはその逆で物価が下降する現象です。
デフレーションは消費者が支出を抑えることが多く、経済活動の低迷を招くことがあります。
インフレの知見が活かせる職種とは?
「インフレ」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- エコノミスト
- インフレの影響を分析し、経済政策や市場動向について提言を行う。
- 消費者物価指数(CPI)や生産者物価指数(PPI)の変動を予測。
- 金融アナリスト
- インフレの影響を考慮して投資戦略を立案し、顧客に対して投資先やポートフォリオの提案を行う。
- 債券や株式市場のリスクとリターンを評価。
- 中央銀行職員
- 金融政策の策定に携わり、インフレ目標の達成に向けた金利政策や量的緩和を実施。
- インフレが経済全体に与える影響を監視。
- 経済政策アナリスト
- 政府や地方自治体で、インフレの進行状況に応じた政策提言や分析を行う。
- インフレ抑制や所得再分配に関する戦略を立案。
- 財務アナリスト
- 企業の財務構造におけるインフレの影響を分析し、収益性やコスト管理の改善を提案。
- インフレの影響を考慮した価格戦略やコスト削減プランを作成。
- 投資コンサルタント
- インフレに対するヘッジ戦略や資産運用プランを顧客に提案。
- ゴールド、インフレ連動債(TIPS)などの投資商品の利点を説明。
- 市場リサーチャー
- インフレが特定の市場や業界に及ぼす影響を分析し、企業や投資家向けにレポートを作成。
- 価格変動の要因や消費者行動の変化を追跡。
- コストアナリスト
- インフレによるコスト増加を分析し、企業の原価計算や価格戦略を支援。
- 効率的なコスト管理手法を提案。
- 商品プライシング担当者
- インフレを考慮した商品の価格設定を行い、企業の利益最大化をサポート。
- コスト上昇を適切に反映し、競争力のある価格戦略を立案。
- ジャーナリスト(経済分野)
- インフレに関するトピックを取材し、消費者やビジネスリーダー向けに解説記事を執筆。
- インフレが家計や企業活動に与える影響を伝える。
インフレに関する知識や経験は、金融、政策立案、リスク管理、マーケティングなど幅広い分野で活用され、経済の安定や持続的な成長を支援する役割を果たします。
まとめ
インフレについて知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、インフレがわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など(目次を参照)を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んで学んでみましょう!
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。